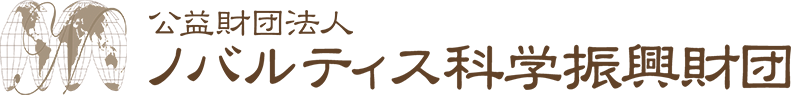受賞者コメント
成果報告によせて - 2022年度受賞者から
-
(受付順、敬称略)
心不全の悪化に関連する Y 染色体遺伝子の特定とそのメカニズムの解明
佐野 宗一(大阪公立大学 大学院医学研究科循環器内科学・特任講師)
男性は加齢と共に、血液細胞の中のY染色体を失うことがあります。このことを「Y染色体の喪失(LOY)」と呼んでいます。私たちの以前の研究では、このY染色体の喪失が心不全を悪化させることがわかっていましたが、その具体的な理由は明らかではありませんでした。今回の研究で、血液細胞のY染色体に含まれる「Uty」という遺伝子が失われることが、心不全を悪化させる原因の一つかもしれないことが示されました。この遺伝子の喪失がどのように心不全に影響を与えるのかを詳しく理解することで、心不全の治療法に新たな光が当たるかもしれません。これは男性だけでなく女性にとっても良いニュースです。
造血幹細胞指向型脂質ナノ粒子を活用した生体内遺伝子治療法の開発
合山 進(東京大学 新領域創成科学研究科 先進分子腫瘍学分野・教授)
血液疾患を治すための新しい方法として、遺伝子治療が注目されています。本研究では、ゲノム編集を行うためのCas9やガイドRNAを脂質ナノ粒子で包んだ新しい薬物送達システムを用いて、全ての血液細胞の元となる造血幹細胞でゲノム編集を行うための基盤となる技術を確立しました。また、MECOMという遺伝子の変異によって引き起こされる骨髄不全症候群のモデルマウスを作製しました。今後も、この造血幹細胞指向形LNPと骨髄不全症候群モデルマウスを活用して、生体内遺伝子治療法の開発を進めていきます。
植物葉面の毛状突起トライコームが活性化する免疫応答の分子機構解明
野元 美佳(名古屋大学 遺伝子実験施設・助教)
植物に感染する病原体は、その多くが雨によって媒介されることから、雨の危険性は認識されているが、植物の雨に対する応答は不明であった。私たちは、植物は雨によって負荷される機械刺激を葉面の毛状突起(トライコーム)によって感知し、トライコームを中心としたカルシウムウェーブを発生させることで、免疫を活性化することを示した。現在までに、トライコーム依存的に生じるカルシウムウェーブの起動や伝播を担う、チャネルや酵素などの制御因子を同定し、その機能解析を進めている。本研究成果によって、機械刺激応答性免疫を標的とした分子育種に繋がることが期待される。本手法は全く新しい植物の形質を提供するものであり、減農薬といった持続的な農業の推進や食料の安定確保などの極めて有効な手段の一つとなることが期待できる。
シグナル感知型エピゲノム修飾因子によるミトコンドリア生合成を標的とした抗肥満効果の解明
酒井 寿郎(東京大学先端科学技術研究センター 代謝医学分野・教授)
私たちは、寒冷環境に晒されるとエネルギー貯蔵を担う白色脂肪を、脂肪を燃焼し熱を作るベージュ脂肪細胞に変化させる仕組みを備えています。ベージュ脂肪細胞はエネルギーの燃焼に重要なミトコンドリアを多く持ち、その誘導が生活習慣病の新規治療・予防戦略として注目されています。本研究では、遺伝情報の後天的修飾であるエピゲノムの書き換えを行う酵素JMJD1Aの活性を制御することで、ベージュ化が誘導され、太りにくくなることを見出し、そのメカニズムとしてベージュ化の過程で、JMJD1Aがミトコンドリアの数を増やす遺伝子の働きを調節していることを明らかにしました。肥満や生活習慣病に対する新たな治療法や予防法への応用につながる成果です。
自然免疫シグナルSTING経路の活性化機構の解明
向井 康治朗(東北大学 大学院生命科学研究科 細胞小器官疾患学分野・助教)
自然免疫は、先天的に備わっている、異物に対する応答機構です。自然免疫応答タンパク質STINGは、DNAウイルスの感染に応答して炎症応答を誘導します。それによってSTING経路はDNAウイルス感染から身体を守っていますが、その一方で、異常な活性化は自己免疫疾患、神経変性疾患、がんなどの疾患を引き起こします。今回我々は、STINGが細胞内で活性化する分子機構を1分子レベルで解析し、DNA刺激時にSTINGが平均20分子以上のクラスターを形成して下流分子を活性化することを見出しました。本研究成果は、上記疾期の新規治療戦略の開発につながることが期待されます。
シングルセル解析と空間的トランスクリプトーム解析から捉える肝臓2型自然リンパ球の新たな糖代謝調節機構の解明
田中 知明(千葉大学 分子病態解析学講座・教授)
免疫系にはたくさんの種類がありますが、その中の「2型自然リンパ球 (ILC2)」は、喘息やアレルギー反応などの病気に関わる関与することが知られています。特に、血糖値や代謝に対して、良い改善効果を持つことが明らかにされており、注目を集めています。 しかしながら、免疫細胞を多く含む肝臓での働きや、血糖を下げる仕組みとの関係については、未だ明らかになっていません。 そこで、本研究では、肥満や糖尿病と関わりの深い肝臓組織に着目して、最先端の技術であるシングルセル解析という手法を用いて、肝臓に存在している2型自然リンパ球がどのようなメカニズムで血糖を下げる役割を果たしたり、糖尿病を改善させるのかを明らかにします。この研究成果は、糖尿病や肥満症に対する全く新しい治療薬の開発につながります。
肺胞形成機構における血管内皮細胞の役割の解明と肺胞再生治療への応用
高野 晴子(日本医科大学 先端医学研究所 病態解析学部門・助教)
肺は、呼吸における酸素と二酸化炭素の交換を担う生命維持に欠かせない臓器であり、このガス交換を担う場が「肺胞」です。肺胞は小さな袋状の構造をしており、内面を覆う肺胞上皮細胞とそれを裏打ちする血管内皮細胞が密に接着することで、肺胞内の空気と血液の間のガス交換を可能としています。今回私達は、血管内皮細胞だけでRap1遺伝子を破壊したマウスの解析から、血管内皮細胞のRap1が基底膜の形成を促進することで、肺胞形成を制御していることを発見しました。本研究成果は難治性の呼吸器疾患等において、肺胞の再生を促す新しい治療法を生み出す可能性があります。
ペプチドのピンポイント修飾を可能にする三成分連結反応の開発
金本 和也(東北大学大学院 薬学研究科・助教)
ペプチドはタンパク質を構成する構造であり,多彩な生命科学研究において,蛍光分子や生物活性分子などの機能性分子の精密な導入が重要である.一方で,様々な反応部位が存在するため,均一な品質でこれらを導入することは容易ではない.本研究課題では,通常1カ所しか存在しないペプチドのN末端に対して,ピンポイントで複数の機能性分子を導入できる三成分反応の開発に成功した.本手法は,完全な選択性と高い変換効率を示し,26残基からなる長鎖のペプチドへの適用にも成功した.これらの結果から,本手法の様々な生命科学研究への応用が期待される.
非コードRNAを創出するがん特異的な転写終結機構の解明
野島 孝之(九州大学 生体防御医学研究所・准教授)
本研究から、がんと転写終結には繋がりがあることが示唆された。例えば、メチル基転移酵素活性を失ったSETD2 遺伝子変異を有する腎臓がん患者細胞では、転写終結破綻とDNA 損傷レベルの上昇が確認されている。このDNA 損傷は、新たな体細胞遺伝子変異を引き起こすことが考えられる。そのため今後、転写終結の調節を介したDNA 損傷抑制アプローチの開発にも取り組む。未成熟転写終結がどのように制御されているのか、今後特に、RNA スプライシング依存的・非依存的な分子機構についても明らかにする。さらに、未成熟転写終結によって産生されるncRNA の同定とそれらの機能解析を行うことにより、医学的に応用可能なncRNA をリスト化することを目指す。
食事介入による慢性閉塞性肺疾患モデルマウスに対する治療法の確立
宮本 潤基(東京農工大学 大学院グローバルイノベーション研究院・テニュアトラック准教授)
慢性閉塞性肺疾患は国内外で主要な死亡原因の一つであり、治療法の確立が積極的に行われている。気管支拡張薬や吸入ステロイドをはじめとした抗炎症薬の投与は呼吸機能、自覚症状の改善は得られるが生命予後の改善効果は報告されていない。そのことの原因の一つに慢性閉塞性肺疾患の主病態である肺気腫は不可逆的であり、こうした薬剤の効果が乏しいことが考えられる。そこで新規の治療薬の開発及び、肺気腫・慢性閉塞性肺疾患の発症及び進行を予防する介入が望まれている 。本研究成果は、単なる食事の摂取が腸内環境の変化を介して慢性閉塞性肺疾患の病態改善に寄与することから、世界に先駆けた慢性閉塞性肺疾患における腸内細菌を標的とした治療法の確立に繋がることが期待される。
マイクロサテライト高度不安定性子宮体がんの免疫回避のメカニズム解明
河津 正人(千葉県がんセンター 研究所 細胞治療開発研究部・部長)
近年、免疫チェックポイント阻害剤のがん治療における有用性が着目されており、とくにマイクロサテライト不安定性の高い(MSI-H)腫瘍で効果的です。しかし、同じMSI-H腫瘍でも、臓器によって抗腫瘍免疫の状態が異なり、臓器に応じた治療戦略を考える必要があります。そこで、さまざまな組織型の81症例の子宮体癌について、組織型による遺伝子異常や遺伝子発現プロファイルの違いを詳しく調べました。その結果、MSI-H子宮体癌とMSI-H大腸癌の免疫応答性の違いを見出しました。さらなる研究で子宮体癌における効果的な治療法の開発につながることが期待されます。
Caイオンを基軸とした、がん細胞の栄養取り込み機構の分子基盤
広瀬 久昭(京都大学 化学研究所・特定准教授)
私たちは細胞が外部からものを取り込む経路の一つであるマクロピノサイトーシスという現象について研究しています。私たちの最近の研究によって、マクロピノサイトーシスには細胞内でシグナル伝達物質として重要なカルシウムが関与していることが分かってきました。そこで、本研究ではカルシウムに関連する遺伝子に着目して研究を行ったところ、マクロピノサイトーシスを制御する遺伝子を新たに見つけることができました。マクロピノサイトーシスはがん細胞での栄養取り込み経路としても重要であることから、本研究の成果が、新規がん治療法への応用につながることも期待されます。
濾胞性リンパ腫特異的免疫環境の探索
安部 佳亮(筑波大学 血液内科研究室・大学院生・日本学術振興会特別研究員)
本研究は、頻度の高い悪性リンパ腫の組織を最新の高解像度解析技術を複数用いて調査したものです。この解析により、リンパ腫の組織内に存在する特異的な免疫T細胞を複数種類同定することに成功し、そのユニークな組織内での分布パターンや機能、そして臨床的影響を明らかにしました。今後の臨床応用を目指したいと思います。
ミトコンドリア病を標的とした新規ホスホフルクトキナーゼ(PFK1)阻害剤開発
小林 大貴(東京薬科大学 生命科学部 腫瘍医科学研究室・助教)
指定難病であるミトコンドリア病に対する根本的な治療法は確立されていません。私たちは解糖系律速酵素ホスホフルクトキナーゼ(PFK1)阻害剤が患者由来細胞のミトコンドリア機能を回復させることを見いだしてきました。この発見は従来の概念からは想定できなかったことであり、非常に独創性の高い治療標的であると考えています。本研究をさらに発展させ、ミトコンドリア病治療薬開発を目指します。
生殖細胞系列の分化を支えるセルトリ細胞の極性化メカニズムの解明
菊池 浩二(熊本大学 染色体制御分野・講師)
造精機能障害は精巣における精子生成機能の低下や不全が原因であり、その多くは先天的なものである。これまでの研究で、一部の造精機能障害と遺伝子変異との関連が示唆されているが、多くのケースでは発症メカニズムが不明である。そこで、私共はヒト病態をミミックするような疾患モデルマウスの開発・解析を進めてきた。その中で、精子形成を支える細胞であるセルトリ細胞の形態と機能の連関について、新たな発見につながる研究成果が得られた。今後は、その分子メカニズムの解明を目指したい。
力学的負荷を感知する心臓特異的スーパーエンハンサーCR9によるナトリウム利尿ペプチド遺伝子発現制御機構の解明
塚本 蔵(大阪大学大学院生命機能研究科 医化学講座・准教授)
ナトリウム利尿ペプチドは心臓で特異的に発現する遺伝子で、心不全に際してその転写が劇的に誘導されます。この心臓特異的かつ病態特異的な転写誘導のメカニズムにスーパーエンハンサーCR9が関与していると考えられます。この分子メカニズムの解明は、心臓特異的に発現する分子の転写制御機構の解明のヒントになり、さらには心臓遺伝子治療への応用にもつながります。
NLR免疫受容体の進化と活性化機構の解明
河野 洋治(岡山大学 資源植物科学研究所・教授)
植物は、非常に多くのNLR型免疫受容体を持ち、この遺伝子数の多さが免疫の堅牢性に貢献していると推測されている。しかしながら、増加したNLR遺伝子がどのような進化の過程を経て新しい機能を獲得し、植物免疫に貢献しているかは十分に理解されていない。本研究により、イネいもち病菌に対するNLR型免疫受容体Pit1と、そのパラログPit2では、「パラログ抑制」と「新機能獲得」と呼ばれる遺伝子重複後に見られる特徴的なイベントが起きたことが示唆された。この2つのイベントにより、Pit1とPit2は、ペアNLRタンパク質として一つの免疫受容体として働くことが示唆された。本研究により、植物免疫の中心的なシステムの一つであるペアNLR型免疫受容体が生み出された進化過程の理解が可能となり、その成果により高性能な人工免疫受容体の設計などに繋がる可能性がある。
膵β細胞におけるマイトファジー不全による糖尿病発症機構
青柳 共太(杏林大学 医学部 細胞生化学・准教授)
2型糖尿病では、インスリンを分泌する膵臓のβ細胞が疲弊して、インスリン分泌量が減少することがきっかけとなり、血糖値が上昇することが知られています。本研究では新規経口糖尿病薬であるイメグリミンが膵β細胞のミトコンドリアに対してどのような影響を及ぼすかについて検討を行いました。その結果、イメグリミンは膵β細胞のミトコンドリアを保護することで、膵β細胞が疲弊することを防いでいることがわかりました。この結果は、膵β細胞におけるミトコンドリア保護の重要性を示しており、今後の糖尿病治療薬開発への新たな視点を提供するものと考えております。
正常・異常造血幹細胞におけるカルシウムシグナルによる幹細胞性制御機構の相違点の解明と治療応用
田中 洋介(熊本大学 国際先端医学研究機構 幹細胞制御研究室・特任講師)
造血システムにおいて最も重要な機能は止血であると言える。この止血を担っているのが血小板である。血小板は迅速に傷口に集積し、傷口をふさぐ。近年、造血幹細胞は前駆細胞を介さずに巨核球を経由して血小板を作ることが知られてきた。迅速な傷口への対応には前駆細胞を経由していては処置が後手に回ることを考えれば納得である。本研究において急激な血小板減少を人工的に起こすと造血幹細胞が2時間以内に反応することを突き止めた。この迅速な反応には造血幹細胞が枯渇するリスクがあるために厳密に制御される必要がある。これを担っているのがPlcl1というタンパクである。いわば造血幹細胞の増殖・分化のブレーキ的な役割を担っている。したがって、このPlcl1を中心としたブレーキのメカニズムを理解することで、急性・慢性骨髄性白血病幹細胞の増殖・分化のブレーキとして利用する新たな治療戦略への貢献が期待できると考え研究を行なっている。
根から花成を制御する分子機構の研究
岡本 暁(新潟大学 農学部・助教)
植物にとっていつ花を咲かせるかは、その個体の一生において重要です。また、農作物が花を咲かせる時期は、収穫の時期に大きく影響します。これまでに、植物の花を咲かせる時期は、葉や茎頂が調節することが知られており、それらに関する分子機構も詳細に研究されてきました。その一方で、根が花を咲かせる時期を調節する仕組みは、それが存在するかどうかも含めて、これまで明らかにされていませんでした。これに対して、私は根で発現するペプチド遺伝子FPとそのホモログが花を咲かせる時期を負に調節することを見出しました。
マウス胎仔期雄性生殖細胞におけるエピゲノム再構築原理の解明
山中 総一郎(東京大学 理学系研究科 生物科学専攻・准教授)
生殖補助医療の需要は年々増加していることから、「不妊症」は現代社会が取り組むべき課題の一つである。不妊症の15%は、その原因が未解明(原因不明不妊)であるなど治療法確立に向けた取り組みは十分でない。生殖細胞は適切な分化を経ることで生殖能を獲得する。不妊症の原因の中には、成体ではなく胎仔期の生殖細胞で起きるイベントに由来するものがある。このようなイベントの一つに、クロマチン構造変化が挙げられる。胎仔期生殖細胞における特異なクロマチン構造変化を起こさないマウスは不妊の表現型を成体期で示す。さらに、この胎仔期生殖細胞でのクロマチン構造変化に伴ってゲノム中のトランスポゾンが活性化し、生殖細胞の“質”が変化することがマウスで示唆されている(Yamanaka et al., 2019, Developmental Cell; Uneme et al., 2024, PNAS)。本研究は、この胎仔期の生殖細胞のクロマチン状態と、生殖能との関係性を明らかにすることで、ヒトの不妊症の原因を解明することを目指したものである。
CMP-シアル酸合成酵素が神経形成を制御する新奇相互作用分子であることの研究
呉 迪(名古屋大学 動物細胞機能研究室・助教)
シアル酸は脊椎動物の細胞表面を覆う糖鎖の末端を修飾する単糖残基です。私達はシアル酸の発現に必須な酵素CSSの遺伝子の点変異がメダカの発達途上で脳の細胞死を起こし、致死となることを見出しました。この変異体メダカの致死性の原因を調べた結果、CSSが細胞の生存に関与するFXR1と相互作用すること、このCSS変異がFXR1のコンホメーションを異常化させて致死性が誘導されることが明らかになりました。この変異は酵素活性に影響しないことから、本研究はCSSが細胞の生存維持というシアル酸代謝以外の機能をもつことの初めての証明となりました。
膵島と肝臓、脂肪、マクロファージとの相互作用による膵β細胞量調節機構
白川 純(群馬大学 生体調節研究所 代謝疾患医科学分野・教授)
インスリンは体内で唯一血糖値を下げることができるホルモンです。血糖値が上がってしまう糖尿病が発症および進展する原因の1つは膵臓の膵島という組織にあるインスリンを産生する膵β細胞が減少することです。我々の研究により、糖尿病状態で膵島の中に入ってくるマクロファージという炎症細胞が、膵β細胞と相互作用することによって、肝臓から血液中に放出されるアミノ酸の取り込みが変化して、結果として膵β細胞が増えにくい状況が起こっていることがわかりました。すなわち、このマクロファージを介した膵島での炎症を抑えることが膵β細胞を増やす新たな糖尿病治療につながることが期待されます。
交尾経験に着目した脊髄GRP受容体ニューロンによる性機能制御メカニズムの解明
越智 拓海(神奈川大学 理学部生物科学科・特別助教)
本研究課題では、脊髄に存在する未知の性機能調節ニューロン(神経細胞)の発見を目指しています。今回はガストリン放出ペプチド受容体(GRPR)という遺伝子を発現するニューロンが性機能に関わることを新規に見出しました。ストレス社会の現代日本では、成人男性の4人に1人が性機能障害に悩んでいますが、神経性の勃起障害のメカニズムはよくわかっていません。性機能の神経制御メカニズムを明らかにすることで、将来、心因性の勃起障害をはじめとした性機能障害の病態解明・治療法開発につながると期待しています。
ウイルス由来遺伝子がもたらした哺乳類胎盤初期分化メカニズムの解明
志浦 寛相(山梨大学 大学院総合研究部・助教)
胎児と母親をつなぐ「胎盤」は胎児の正常な発生・成長に欠くことのできない組織であり、原因不明の胎児期の発生・成長異常の中には、胎盤異常が原因となっている例も数多く存在すると考えられます。しかし、 胎児組織の分化・発生メカニズム研究が大きく発展しているのに対し、胎盤の発生については理解が進んでいません。本研究では、哺乳類の祖先に感染したウイルスが元となり誕生した新しい遺伝子PEG10に着目し、この遺伝子の機能解析を軸として哺乳類胎盤の初期発生メカニズムの解明を進めています。これまでの解析から胎盤を形づくるうえでのこの遺伝子の重要性が徐々に明らかとなってきており、本研究をさらに発展させることで、胎盤組織に起こるあらゆる異常・疾患の病因の解明、その治療法の開発に大きく貢献できると考えています。
免疫遺伝学的メカニズムの解明に基づく高血圧性疾患の新たな予防・治療法の開発
大原 浩貴(島根大学 医学部病理学講座病態病理学・講師)
降圧剤は脳卒中などの高血圧性疾患の予防に効果的ですが、既存の薬では十分な降圧が得られない患者さんも多く存在するという事実があります。高血圧性疾患の制圧には、「なぜ高血圧になるのか?」という根本的な問いを解明する必要がありますが、高血圧の発症には多くの遺伝的・環境的要因が関わり、容易ではありません。私は日本で開発された高血圧性疾患のモデルラット (SHRSP) を用いて、その問いに答えるための研究に取り組んでいます。最近、SHRSPにおける病気の発症や進行に強く関わり得る2つの候補遺伝子を見つけ、ここでは免疫系への影響に着目して研究を行いました。高血圧ラットの健康維持につながる手法の開発を通じて、ヒトを対象とした医療の充実に貢献したいと考えています。
プロテアソーム維持機構の解明と創薬への応用
濱崎 純(東京大学大学院薬学系研究科 蛋白質代謝学教室・助教)
細胞内タンパク質分解を担う真核生物に必須のプロテアソームの機能変化が多様な疾患の発症に関わることが最近の研究から明らかになるとともに、プロテアソーム阻害剤が抗がん治療に使われるようになり、新たな創薬標的として注目されています。しかしながら、正常細胞のプロテアソームも阻害することによる副作用や薬剤耐性細胞の出現など、まだまだ治療アプローチとしては課題が多く基礎研究に立脚した改善が必須です。本研究ではプロテアソーム阻害時の細胞内恒常性維持にO-GlcNAc化亢進が重要であるという発見を端緒として、新たなプロテアソーム制御因子を同定するとともに、これらの機構を利用したプロテアソーム阻害剤との併用アプローチの有用性について明らかにしつつあります。まだまだ萌芽的な部分を持つ研究ですが、発展性や臨床的な実現性は高いと思われることから、今後も着実に研究を推進していきたいと考えています。
ミトコンドリア恒常性に必要な新規リン脂質輸送因子の破綻による疾患発症機構の解明
堀端 康博(獨協医科大学 医学部生化学講座・准教授)
ミトコンドリア膜はホスファチジルコリン(PC)を主とするリン脂質二重層で構築されている。しかし、ミトコンドリア自身にはPC合成能がないため、リン脂質合成器官である小胞体からの供給に依存している。これまで申請者はPCを小胞体からミトコンドリアへ輸送するタンパク質StarD7を先駆けて見出した。本研究では、骨格筋特異的に本タンパク質が欠失したマウスの解析を行なった。骨格筋から単離したミトコンドリアのリン脂質を調べた結果、欠損マウスではリノール含有PCと、それから合成されるカルジオリピンが著減しており、ミトコンドリアの異常が認められた。骨格筋を病理解析した結果、ミオパチーの発症を示唆するいくつかの病変が確認された。以上から、StarD7はミトコンドリアミオパチーの新たな原因遺伝子であることが示唆された。
臨界期脳の樹状突起リモデリングを制御する分子シグナルの解明
見學 美根子(京都大学 高等研究院 物質-細胞統合システム拠点・教授)
幼若期の脳神経回路は余計に形成される傾向にありますが、感覚刺激による活動レベルで要不要の選別が起こり、個体の生活環境により最適化される仕組み(臨界期機構)を備えています。本研究では、臨界期のニューロンの樹状突起が神経活動により剪定される過程に関わることが分かっているBTBD3分子の動作機構の解析を行いました。本研究により、BTBD3が神経活動により細胞内での局在を変えることが樹状突起の剪定に必須であることを見出し、この局在変化の分子基盤の一部が明らかになりました。
内在性RNAの可視化・制御法で解き明かす病原性RNA顆粒の相分離動態
高井 啓(東京大学大学院 医学系研究科細胞生物学分野・助教)
本研究は、ガンや神経変性疾患などの難治性疾患の発症メカニズムの1つである病原性のRNA顆粒に注目し、そのRNA顆粒の形成を阻害する方法を探索することで将来的な難治性疾患の治療に役立てようとする基礎研究です。公益財団法人ノバルティス科学振興財団のノバルティス研究助成金のおかげで本研究が飛躍的に推進され、難治性疾患の治療に役立つ可能性を持つ多くの知見が明らかになりました。本研究成果が難治性疾患に苦しむ多くの患者様の治療法へと役立てることを心より祈念いたしております。
LKB1/KEAP1遺伝子変異に伴うKRAS G12C阻害剤治療抵抗性の誘導とその分子機序解明
北嶋 俊輔(公益財団法人がん研究会 がん研究所 細胞生物部・研究員)
肺がんは世界で最も罹患数の多いがん種であり、肺がんを引き起こす「ドライバー遺伝子変異」を標的とした新薬が次々と開発されてきました。しかし肺がんで最も高頻度に観察されるKRAS遺伝子変異に対する有効な薬がこれまで存在しませんでした。しかし、2022年度より日本国内において初めてKRAS阻害薬の1つであるソトラシブの使用が開始され、生体内での詳細な作用機序や薬剤耐性のメカニズム、有効な患者を選別するための奏功マーカーの開発は今後の重要な研究課題となっています。本研究では、これまで研究代表者が行なってきた肺がん細胞に対する研究成果を基盤としてこれらの課題にアプローチしています。
進化工学的アプローチによる人工mRNAのタンパク質アミノ(N)末端領域の最適化
宇田川 剛(名古屋市立大学 大学院薬学研究科遺伝情報学分野・准教授)
mRNA医薬は新型コロナウィルスのmRNAワクチンの登場で一躍注目を集めましたが、この他にも、遺伝子治療、がん免疫療法など多様な目的での応用が期待されています。しかし、人工mRNAからのタンパク質合成効率の低さが、その妨げとなっています。本研究ではこの課題に取り組むため、これまであまり注目されてこなかったタンパク質末端配列の最適化により、タンパク質発現効率を上昇させることを目指しています。これまでに複数の発現高効率化配列を同定しており、今後さらにスクリーニングを進め、mRNA医薬の分子基盤の構築に貢献したいと考えています。
cAMPの高時間分解能計測による光活性化cAMP産生酵素の探索と創製
平野 美奈子(岡山大学 学術研究院ヘルスシステム統合科学学域・准教授)
細胞のはたらきを光で操作する技術の高度化を目指し、その技術で用いるツールの探索と改良を行っている。ツールである光感受性タンパク質の一種である光感受性アデニル酸シクラーゼ(PAC)は生物界に数多く存在している。本研究では、それらの特性、特に光応答性を正確に比較するための測定系を確立した。様々なPACの特性を比較・改変することにより、細胞の光操作ツールとして選択できるPACの種類を増やし、生命現象の機序の理解や疾患の原因解明の進展に貢献したい。
角質層セラミドの恒常性に不可欠な新たな脂質代謝機構の解明
大垣 隆一(大阪大学 大学院医学系研究科 生体システム薬理学・准教授)
皮膚のバリア機能は、異物の侵入から身を守ったり、体内の水が失われるのを防いだりしています。特に重要なのが、皮膚を覆う角質に存在するセラミドと呼ばれる脂質です。我々は、セラミドを保つ働きをもつ新規酵素を発見し、その分子機能の一端を明らかにしました。この酵素の機能によって生じる脂質は、バリア機能の破綻を回復させる可能性があるため、本研究の成果は、アトピー性皮膚炎等、関連する疾患の治療の提唱にも繋がるものと期待されます。
膵癌の前癌病変を高感度に検出できる多機能性分子プローブ開発
淵上 剛志(金沢大学 医薬保健研究域薬学系 臨床分析科学研究室・准教授)
膵臓がんは、全がんの中で最も予後が悪く、その治療成績向上は喫緊の課題です。臓がんは、進行性のがんになる前に、特徴的な前癌病変が見られることがあります。これらを早期に発見できれば、治療成績が大幅に改善される可能性があります。本研究では、血液検査から画像診断まで一貫した診断により、迅速かつ高精度に膵臓がんを前癌病変の状態で発見できる画期的な診断薬開発を目指しました。研究期間に、いくつかの前癌病変へ強固に結合する化合物の開発に成功しました。また、血液検査に用いることのできる金ナノ粒子型の新たな素材の開発にも成功し、今後の更なる展開が期待されます。
統合的マルチオミクス解析によるアルツハイマー病の層別化
間野 達雄(国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第四部・室長)
アルツハイマー病は、アミロイドβとリン酸化タウという2つのタンパク質の蓄積が特徴ですが、実際の症状や進行速度は患者さんによって大きく異なります。この研究では、最先端の分子生物学的手法を用いて、アルツハイマー病の多様性の原因を遺伝子やタンパク質のネットワークレベルで解明することを目指しました。
ネジル化修飾を介したPMLボディの凝集と腎組織再生促進の研究
越智 陽城(山形大学 医学部 メディカルサイエンス推進研究所 生化学解析センター・准教授)
ヒトは失った組織や器官をまるごと取り替える能力、再生能を持っていないが、動物の中にはそれができるものがあります。この研究は、ヒトと比べると高い再生能を持つカエルを使って、腎組織がどのように再生するのか明らかにすることを目的としています。細胞の中の核には体の設計図と呼ばれるゲノムが存在します。ゲノムの中には、「遺伝子」と「遺伝子以外の領域」があります。我々の体は様々な状況に応答して、「遺伝子以外の領域」にあるオン・オフ・スイッチを利用して、遺伝子を使う・使わないと決めています。カエルが再生する時に使う遺伝子はヒトも持っています。このことは、遺伝子があるだけでは再生できないこと、つまりヒトではオン・スイッチがうまく働かないことを示しています。この研究は、再生を可能とさせるオン・スイッチに着目して、その全容の解明に取り組んでいます。
乾癬病態形成におけるケモカインELC/CCL19の新規受容体の病理的役割の解明
松尾 一彦(近畿大学 薬学部 化学療法学研究室・講師)
現在、乾癬などの炎症性疾患に対して効果のある治療薬が多数あります。しかし一部の患者では既存の治療薬が効かない場合もあるのが現状です。この研究では、乾癬が発症する新しいメカニズムを明らかにすることで、既存の治療薬とは異なる作用を示す新しい治療薬を開発することを目的にしています。この研究が進めば、既存薬で効果のない患者にも有効な治療薬ができることが期待されます。
シクロプロパンが縮環した複素多環式化合物の立体選択的合成法の開発と応用
辻原 哲也(岩手医科大学 薬学部 薬科学講座 創薬有機化学分野・准教授)
シクロプロパン環は、その特異な反応性や構造的な特徴により、有機合成や医薬化学の中で重要な部分構造です。シクロプロパン環をもつ窒素を含んだ環状化合物は、生物活性天然物や医薬品に多く存在し、その立体構造を制御する合成法の開発が望まれていました。本研究では、簡便な実験操作かつ合成中間体の精製を必要としないワンポット合成にて抗HIV活性を示す化合物の骨格構築法を確立しました。本法から得られる生成物は更なる化学変換により様々な誘導体の合成が期待できるため、本研究成果は創薬研究や医薬品の製造に有効であると考えています。
成果報告によせて - 2021年度受賞者から
-
(受付順、敬称略)
TFEBによる損傷リソソーム修復機構の解明
中村 修平(大阪大学 大学院生命機能研究科・准教授)
リソソームは細胞内の分解を担うのみならず様々なシグナル伝達の司令塔として働き、細胞や個体の恒常性維持に必須の役割を果たす。リソソーム機能の破綻は神経変性疾患や感染症など多くの疾患に加えて老化の要因になることが示唆されているが、リソソーム恒常性がどの様に維持されているかはあまりよくわかっていない。本研究ではリソソーム恒常性維持に必須の働きを持つTFEBの制御機構について解析を行い、いくつかこの制御の鍵を握る因子を同定することができた。今後、これら因子の病態や老化モデルを用いた機能解析を進めることで、リソソーム機能不全を伴う疾患の新たな治療法や老化そのものの抑制法確立のシーズ創出につながる可能性があると考えている。
CD73発現細胞による骨髄微小環境の細胞ダイナミクスの解明
木村 健一(筑波大学 生存ダイナミクス研究センター・助教)
間葉系幹細胞 (MSCs) は、再生医療のツールとして骨疾患治療への実用化に向けた研究が進んでいます。しかし、治療の有効性や作用機序についてはまだ明らかとなっていないことが多く残されています。MSCsがどのような性質を持っているのかが分かれば、MSCsを利用した新たな治療法の開発に繋がります。この研究では、MSCsの局在とその性質を制御する微小環境について明らかにすることを目指しています。これによって、MSCsの生体内の機能解明につながり、安全で効果的な治療法確立へ貢献できると考えています。
新規lncRNAの心臓保護作用に着目した心不全(HFpEF)への挑戦
佐藤 迪夫(熊本大学 生命資源研究・支援センター・特任助教)
日本を含めた先進各国において、心不全患者は増加の一途を辿っています。心不全は、様々な要因・疾患により、心臓の機能が低下した状態です。心不全の死亡率は、主要な悪性腫瘍に劣りません。しかし、心不全の根本的な治療法は確立していません。そのような状況の中で、私はミトコンドリアに着目した研究を行っています。加齢や心負荷により、ミトコンドリア機能が低下すると、心不全の進展に繋がります。私は、タンパクを作らないRNA (non-coding RNA) を用いて、心臓ミトコンドリアを増やすことにより、心機能を改善できるのではないかと期待して、研究を進めています。
転写開始点のスイッチングによる植物の早期老化開始抑止機構の解明
肥後 あすか(名古屋大学 遺伝子実験施設・特任助教)
動くことのできない植物は、周囲の環境変化や自身の成長段階を感知して応答し、それぞれの器官および個体全体の成長を調整する必要があります。そのような応答の一つに、老化開始時期の制御がありますが、植物が、様々な情報を統合して老化の開始時期を調節するための分子機構はわかっていません。本研究で機能解析を進めた受容体キナーゼは、その遺伝子が欠失すると老化開始時期が早まることから、老化開始の調節に関わっていることが示唆されます。本研究での成果を足がかりに、今後さらに機能解明を進めることで、植物が老化開始時期を調節する仕組みを明らかにし、将来的には、人工的に操作する技術の開発にもつながることが期待されます。
新規の光温度遺伝学技術で探求する生体自律化メカニクス
茂木 文夫(北海道大学 遺伝子病制御研究所 発生生理学分野・教授)
生物は細胞集団の空間パターンを組織・器官スケールで秩序化することで、生体の形と機能を創生する。この細胞集団の秩序化では、細胞が機械的力の発生を感知・応答することで化学シグナル伝達を調節する「力学化学カップリング」を必要とすることが示された。しかしながら、力作用は直接可視化することができないので、この仕組みと役割には未だに不明な点が多い。本研究では、力発生の役割を解明するための技術開発を目的とし、細胞内温度変化を利用して、力発生に関わる標的因子の機能を素早く阻害する「温度遺伝学法」を開発し、線虫多細胞期胚における非対称分裂を司るメカニクスの機能を解析した。この技術を活用して、細胞自律的な自己組織化に対して、細胞非自律的な力学的作用が及ぼす影響を調べることで、マクロスケールの生体秩序化を司る基盤原理が解明できる。
カチオン能動輸送体の構造機能解析と機能獲得変異体による基質特異性の解明
阿部 一啓(国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 創薬科学研究科・准教授)
細胞膜を隔てたイオンの不均衡分布は、例えば神経の情報伝達や栄養素の細胞への取り込み等、生命現象と深くかかわっています。これはATPのエネルギーを利用してイオンを輸送する非常によく似たタンパク質、能動輸送体によって形成されています。しかしながら、輸送されるイオンの種類やその個数は厳密に決まっていて、決して間違えたりはしません。我々はプロトンポンプをナトリウムポンプに変換することに挑戦し、たった4つのアミノ酸を置換するだけで、Na+を輸送するポンプを創る事に成功しました。構造解析によって、3つのNa+と2つのK+を結合していることが確認できました。この研究によって、プロトンポンプとナトリウムポンプがどのように輸送するイオンの種類を認識しているかが詳しく理解できました。
ミトコンドリアに着目した老化造血幹細胞多様性の解析
松村 貴由(自治医科大学 分子病態治療研究センター 炎症・免疫研究部 兼任 循環器内科・講師)
造血幹細胞は全ての血液細胞になる(分化する)ことが可能な特別な細胞です。悪性腫瘍化することなく生涯にわたる血液の産生を維持するために、造血幹細胞の機能は厳密に制御されなければいけません。しかし、残念ながら、造血幹細胞の機能は老化とともに低下し、悪性腫瘍化の危険性は上昇します。今回の研究で、年老いたネズミの造血幹細胞を詳細に解析したところ、年老いたネズミの中にも比較的その機能が保たれた、いわば、“まだ若い”造血幹細胞がいる可能性があります。今後は、このような“若い”細胞をヒトからも精製する方法を確立したいと考えております。
非アルコール性脂肪肝炎におけるリン脂質代謝異常の意義とその空間的理解
中川 勇人(三重大学 大学院医学系研究科消化器内科学・教授)
非アルコール性脂肪肝炎(NASH)は、肝臓への脂肪沈着(脂肪肝)をきっかけに、炎症・線維化がおこり、肝硬変や肝癌に至る進行性の疾患です。今回の研究から、進行したNASHでは肝細胞内の脂質、特にリン脂質のバランスが崩れ、細胞が障害されやすくなっていることが明らかとなりました。リン脂質の補充やリン脂質バランスの改善が、進行NASHの治療法の一つとなると期待されます。
iPS細胞由来3D血管を用いた血管老化メカニズムの解明
豊原 敬文(東北大学 分子病態医工学分野・特任助教)
血管は年齢とともに老化し動脈硬化のリスクとなりますが、その原因は解明されておらず、治療法もありません。我々はiPS細胞を用いて3D血管を作製し、血流が血管老化に及ぼす影響を解析しています。本研究によって血管老化を起こす要因を明らかにすることで、血管の老化を予防、治療する方法を開発していきたいと思っております。
腫瘍内高浸潤型CD8T細胞分化機構の解明
高村 史記(近畿大学医学部 免疫学教室・講師)
組織滞在型メモリーCD8T細胞(TRM)は粘膜組織に定着し、感染防御免疫の第一線を担う。これに極めて類似した特徴もつCD8T細胞(TRM-like TIL)は強力な抗腫瘍活性を持つことが知られているが、この細胞が腫瘍内にてどのように分化するのかは不明である。我々はヒト腫瘍組織にてその分化部位を特定すると共に、TRM-like TIL局所抗原刺激が重要であること、また、分化部位に存在するマクロファージが抗原刺激の供給源となっている可能性を示唆する結果を得た。今後はこのマクロファージがTRM-like TIL分化誘導に果たす役割を追及する。
急性リンパ性白血病誘導モデルを用いた初期リプログラミング機構の解明
伊川 友活(東京理科大学 生命医科学研究所・教授)
近年、急性リンパ性白血病(ALL)の治療成績は飛躍的に向上したものの、未だに予後不良な転座型も存在します。我々は、難治性ALLの一つである1;19転座型(TCF3-PBX型)B細胞性ALL(B-ALL)に着目して研究を行いました。独自に開発した動物モデルを用いて、発症初期の分子メカニズムの一端を解明しつつあります。今後は本研究で見出した分子機構をB-ALLの新規治療法の開発に結びつけたいと考えています。
高感度化亜鉛蛍光イメージングプローブを活用する細胞内亜鉛ホメオスタシスに干渉する化合物の探索
奥田 健介(神戸薬科大学 薬化学研究室・教授)
亜鉛ホメオスタシスの崩壊とアルツハイマー病、糖尿病、がんなどの多様な疾患との関連性が明らかとなっており、亜鉛ホメオスタシスを維持あるいは介入するために使用可能な治療薬の発見を加速するためには、亜鉛の細胞内の状態を効率的に可視化できるアッセイ系が必要である。本研究では私たちが開発した高感度細胞内亜鉛蛍光プローブの改良を行って本アッセイ系の構築を試みるとともに、個体レベルでの生体イメージングに適したMRIプローブへの展開を図ったところ、第一世代の亜鉛MRIプローブの開発に成功した。
クライオ電子顕微鏡を用いた色素性乾皮症発症メカニズムの解明
松本 翔太(東京大学 定量生命科学研究所 胡桃坂研究室・助教)
私たちの遺伝情報はゲノムと呼ばれるDNA配列に保存されています。遺伝子の設計図とも言われるDNAは、ほぼ全ての細胞に等しく保存されており、それは安定に子孫へと引き継がれていきます。ところが紫外線など外から強力なエネルギーを受けると、DNAが損傷を受け、遺伝子が変異を起してがんが発生するリスクが高まります。この損傷を修復するメカニズムの一つが、ヌクレオチド除去修復であり、絶えず私たちに生じた損傷を取り除き続けています。 ヌクレオチド除去修復に異常が起こると、紫外線による損傷を修復できなくなり、さまざまな疾患が引き起こされます。色素性乾皮症もその一つであり、特定難病に指定された治療法がない遺伝病です。私たちはクライオ電子顕微鏡という最先端の顕微鏡により、この修復メカニズムを可視化して理解することを目指しています。この研究が進めば、紫外線によるがんの発生を抑制できると期待され、将来的に色素性乾皮症の治療法の確立へと繋がることも夢ではありません。
“核-軸索クロストーク制御システム”の破綻による脳機能老化
桑子 賢一郎(島根大学 医学部 神経・筋肉生理学・准教授)
私たちの脳は、痴呆症などの神経疾患に罹らなくても、加齢に伴って徐々にその機能が衰えていきます。しかし、どのようにしてその生理的変化が起こるのかはよくわかっておらず、有効な予防法もありません。今回の研究では、これまで知られていなかった神経細胞の活動レベルを制御する新たなしくみを発見し、さらに老化によってその機構が破綻することで脳機能の衰退が起こる可能性を見出しました。今後は、今回発見した機構を老齢期でも正常に維持することで加齢による脳機能の低下を抑止できるかどうかを検証していきます。そして、将来的には、これらの知見を脳老化の予防法の開発につなげたいと思います。
網羅的ゲノム解析に基づく造血細胞移植後2次固形がんのゲノム医療の実現
井上 聡(愛知県がんセンター研究所 腫瘍免疫応答研究分野・ユニット長)
同種造血細胞移植は、白血病などの難治性血液疾患の根治を可能とする治療法です。移植技術の向上に伴い、長期生存者数が増加しています。しかしながら移植治療による副作用として正常細胞がダメージを受けてしまい、口腔や食道などの2次固形がんの発症に至ってしまいます。しかしその原因や病態は不明であるため、1次がんに準じた治療法が選択せざる得ないのが現状です。そこで大規模2次がん検体バンクと空間・経時的マルチサンプリングゲノム解析を組み合わせることで、移植症例に対するゲノム医療による個別化至適治療の実現に向けた分子基盤を構築することを目的としました。その結果、2次がんに特徴的なゲノム異常が認められ、免疫チェックポイント阻害剤などの個別化至適治療法の適用対象になり得る可能性が示唆されました。
生物学的等価体としてのスルホキシイミン類縁体の不斉合成法の開発
加納 太一(東京農工大学 大学院工学研究府・教授)
医薬品や農薬などの生物活性物質には、硫黄原子を含むスルホキシイミンと呼ばれるものがあります。スルホキシイミンにはその鏡像となるものが存在するため、どちらか一方だけを合成する不斉合成法の開発が必要となります。本研究では、スルホキシイミンの酸素原子を窒素原子で置換したスルフィンアミジンの不斉合成法を開発し、新しい生物活性物質の合成が可能となりました。今後は医薬品開発への応用が期待されます。
1型糖尿病発症機序の包括的な理解とその予防法の開発
三根 敬一朗(佐賀大学 肝臓・糖尿病・内分泌内科・特任助教)
本研究は血糖値を下げるホルモンであるインスリンを作る細胞が破壊され糖尿病(1型糖尿病)になる機序を解析することで、有効で安全な1型糖尿病の発症予防法を確立することを目的としています。1型糖尿病は生涯にわたってインスリンを補充する以外に治療法がなく、現在のところ不治の病です。我々の研究によって1型糖尿病の発症を防ぐ方法を開発し、患者数の減少と人々のQOLの向上へ貢献したいと考えています。ある遺伝子とその遺伝子から作られるタンパク質の働きを阻害することで、1型糖尿病の発症が抑制されることが明らかになりました。その発症抑制機序を詳細に解析し、標的として最適だと考えられる細胞の種類を特定することができました。この研究成果は、副作用を限りなく抑えた1型糖尿病発症予防法の開発へ繋がると考えられます。
アミノ類の網羅的合成とSARS-CoV2 Pro阻害剤の開発
今野 博行(山形大学 大学院理工学研究科・教授)
アミノ酸は最も重要な部分構造の一つであり、医薬品、農薬、食品添加物などに利用されている。アミノ酸は多彩な側鎖構造を持つことから需要が高く、その効率的な製造技術の開発は重要課題となっている。それらの製造プロセスにおいて、一般性があり、環境にやさしく、なおかつ安全、安価な方法論の確立が求められていた。筆者は光学活性なニッケルリガンドを用いて安価なL体を高価なD体に変換しつつ、保護基を効率的に導入しうる方法の開発に成功した。この結果は従来法と比較して様々な利点があり、社会実装への展開が期待される。
新たな心血管病治療標的としての多機能プロテアーゼNRDC酵素活性の意義
大野 美紀子(国立大学法人 滋賀医科大学 薬理学講座・准教授)
我々は、プロテアーゼの一つであるナルディライジンについて、生体内でどのような役割を持つのか長年研究しています。遺伝子改変マウスの解析系やヒト血清ナルディライジン値を測定できるシステムを立ち上げ、様々な病態での役割を明らかにしてきました。今回の研究ではナルディライジンによる心臓の拍動(心拍数)調節のしくみを明らかにしました。また、その酵素活性による意義を明らかにするために、ナルディライジンの酵素活性を持たない変異型ナルディライジンを持つマウスや、ナルディライジンの酵素活性を抑制する小分子化合物を解析し、心筋梗塞やタコツボ型心筋症などの心臓病において、ナルディライジンが新しい治療薬開発の標的となり得るかどうかを検討しました。今後、ナルディライジン酵素活性を抑制することによって、実際に心臓病の改善が見込めるかどうか、また、さらに詳細なメカニズムを解析し、将来の治療薬候補を探索していきます。
抗老化マトリクスFibulin-7に着眼した皮膚幹細胞老化メカニズムの解明
佐田 亜衣子(熊本大学 国際先端医学研究機構・特任准教授)
皮膚は、外的・内的ストレスを常に受けながらも、柔軟に応答し、組織を回復する力を持つレジリエンスの高い臓器の一つですが、加齢とともに徐々にその能力を喪失していきます。本研究では、細胞外ではたらくタンパク質であるfibulin-7が、表皮幹細胞周囲の微小環境を構築することで、皮膚の老化を防ぐ鍵になる因子の一つであることを解明しました。本研究成果は、老化した表皮幹細胞や環境因子を標的とした皮膚の老化予防・制御法の創出へとつながることが期待されます。
若年発症心臓刺激伝導障害の遺伝子基盤解明とそれに基づく個別化医療の実践
林 研至(金沢大学 医薬保健研究域保健学系・准教授)
若年発症徐脈性不整脈の原因遺伝子の詳細は明らかにされていない。また、遺伝子解析によって見いだされるバリアントの中にはその病的意義が不明なものが数多く含まれる。我々は次世代シーケンサーを用いて65才未満で発症した徐脈性不整脈51症例に対して拡大候補遺伝子解析を行った。遺伝子解析の結果、15症例に15個の病的バリアントを見出し、15症例に25個の病的意義不明のバリアントを見出した。病的意義不明のバリアントに対してゼブラフィッシュあるいは動物培養細胞を用いて機能解析を行ったところ、6個のバリアントの機能異常を確認した。最終的に若年発症徐脈性不整脈51症例のうち、20症例に21個の病的バリアントを見出し、陽性率は39%であった。その中にはLMNA遺伝子とSCN10A遺伝子のバリアントが多く含まれ、若年発症徐脈性不整脈の主要原因遺伝子であることが示唆された。
アルツハイマー病治療を目指したタウ分子の細胞外放出機構の解明
荒若 繁樹(大阪医科薬科大学 医学部内科学IV教室脳神経内科・教授)
アルツハイマー病の発症には、タウタンパク質の細胞間伝播が深く関与している。本研究では、細胞間伝播に必須のステップであるタウタンパク質の細胞外放出機構に焦点をあてて解析を行った。その結果、マウス大脳皮質初代神経細胞において、タウタンパク質は生理的にオートファジーを介して細胞外に放出されること、この放出はオートファジーの分解機能を阻害すると代償的に亢進することを見出した。これらの所見は、オートファジーの機能異常は、タウのタンパク質恒常性維持を乱し、アルツハイマー病の病勢進展に関与する可能性を示唆していた。
ミクログリアの機能障害と神経変性疾患の発症機序の研究
城谷 圭朗(長崎大学 ゲノム創薬学研究室・准教授)
アルツハイマー病の根本治療薬はアミロイドの抗体医療薬のみが米国で上市されている。しかし認知機能改善効果は弱いので他の作用点の治療薬開発が必要である。脳の免疫細胞ミクログリアが発症や進行に関わっているという最近の知見から本研究ではミクログリアが持つTREM2というタンパク質を標的とした創薬を行っている。これまでの研究上の問題点はアルツハイマー病の発症頻度を高めるTREM2R47H変異を導入したモデルマウスではTREM2自身が発現しないことであった。本研究ではこの問題点を克服しモデルマウスの作製に成功し、実際にTREM2が発現していることを確認した。また初代培養細胞の実験ではTREM2の変異があっても貪食機能に大きな影響を与えないことがわかった。これよりモデルマウスでの機能解析研究が非常に重要であることが示唆され、今後は本研究で作製したマウスでアルツハイマー病の発症機序あるいは治療薬開発研究を進めていく。
神経ー免疫連関による痒み抑制機構の解明
原 博満(鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科免疫学分野・教授)
アトピー性皮膚炎に代表される慢性の痒みは患者のQOLを著しく低下させる。今回の我々の研究により、これまでアトピー性皮膚炎などの炎症を抑制するサイトカインとして知られていたIL-27が、痒みを伝達する感覚神経にも直接作用して痒みを抑制することが明らかとなった。これは、免疫細胞が産生するサイトカインが痒み感覚の抑制に働くことを示した初めて発見であり、この研究をさらに進めることで、新しい掻痒治療薬の開発につながるものと期待される。
転写物の配列に依存しない非コードRNA 転写と共役した普遍的染色体機能調節機構の解明
廣田 耕志(東京都立大学 理学部化学科・教授)
本研究では、子孫に遺伝子を繋ぐ機構、減数分裂における、配偶子の多様性の創出機構を新規に解明しました。子孫の多様性は、環境変動への生物種としての対応や進化の原動力として重要であることは皆さんご存知のことと思います。例えば、接木で全国にクローン増殖した「桜」の木は、一度病原菌や虫におかされると全滅してしまいますね。本研究をさらに発展させ、減数分裂期の「組換え」による子孫の多様性創出の秘密をさらに解明し、効率的な品種改良技術など応用研究にも繋げたいと思います。
脳腫瘍を悪性化させる腫瘍細胞―神経細胞間コミュニケーション
上阪 直史(東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 認知神経生物学研究室・教授)
脳が正常に働くには脳内の環境が安定していることが必要不可欠です。脳疾患の原因や病態として、脳内の局所環境が乱れていることが考えられています。脳腫瘍は脳内の局所環境が乱れている疾患の1つです。脳腫瘍は、腫瘍細胞自体が持つ性質だけでなく、周りに存在する正常細胞が進展や悪化に影響することが分かっています。しかし、腫瘍細胞と周囲の脳内環境にある正常細胞とがどのように相互作用して脳腫瘍を進行させるのかはほとんど分かっていません。この研究では、正常な神経細胞やグリア細胞と腫瘍細胞との相互作用に注目しています。腫瘍細胞は、正常な神経細胞やグリア細胞と相互作用して、腫瘍細胞にとって必要な脳内環境を形成していると考えられています。この研究では、腫瘍細胞が神経細胞やグリア細胞からの物質を悪用して腫瘍を進行させる可能性を調べました。今後、それらの物質を標的とする脳腫瘍の新規治療法の開発につなげることを目指しています。
組織成熟化誘導法樹立による多能性幹細胞から成体組織形成の実現
中西 未央(千葉大学 大学院医学研究院・講師)
本研究ではヒト多能性幹細胞由来の未熟な細胞を試験管内で短期間に成人の細胞へと成熟させることを目的に、造血幹細胞をモデルとして成熟化誘導法の開発をおこなった。従来の方法でヒト多能性幹細胞から得られるのは、CD45陰性のprimitiveなpre-HSCに留まっていたが、研究代表者は造血細胞の更なる成熟の場である胎児肝臓内のニッチ因子同定をおこない、同定された胎児肝臓ニッチ因子を使って造血再構築能をもった細胞に特異的なCD201陽性の胎児肝臓造血幹細胞様の細胞を得た。現在、これらの細胞の機能を詳細に解析中であるほか、胎児型幹細胞から成人幹細胞へと成熟化技術をより進化させるため、さらなる研究を進めている。
多発性硬化症患者に存在する血液脳関門破綻の遺伝的素因の解明
西原 秀昭(山口大学 神経・筋難病治療学講座・助教)
血液脳関門という脳を守るバリアシステムに着目して多発性硬化症の病態解明,創薬研究を行いました.本研究では患者さん由来の血液脳関門モデルをiPS細胞の技術を用いて実験室に再現しました.また,健常人由来の血液脳関門モデルを人為的に改変することで多発性硬化症患者にみられる変化を再現することができました.これらの発見は,今後血液脳関門を標的とした,血液脳関門を強固にする治療法,もしくは脳内に薬物を届ける薬物輸送研究に発展できると期待しています.
膵癌の新たなoriginの同定 ~膵ランゲルハンス島を由来とする膵癌発生新仮説の提唱~
藤谷 与士夫(群馬大学 生体調節研究所 分子糖代謝制御分野・教授)
膵がんは早期発見が困難な癌種であり, 本邦における5年生存率は7%と他の癌に比べて極端に低い. 従って、膵がんの発生進展様式を理解することは喫緊の課題である.膵臓は腺房細胞, 膵管細胞そして膵ランゲルハンス島(内分泌細胞)という3つのパートから成るが, 膵がんは腺房細胞あるいは導管細胞を源として発生すると現在は考えられている. 我々は, 膵ランゲルハンス島に存在する内分泌細胞の一つであるPP細胞を起源として再現性よく膵がんを発生するユニークな動物モデルを開発した. このモデル動物を詳細に分子レベルで調べることによって, これまでには報告されていない, ユニークな膵癌の発症様式が存在することが明らかになった. 我々の発見は, あらたな膵がんの診断や治療法の開発につながる可能性がある.
核医学治療と新規ホウ素中性子捕捉療法を融合した革新的診断治療法の開発
小川 数馬(金沢大学 新学術創成研究機構・教授)
BNCTは,2020年に世界に先駆けて日本で承認された最先端のがん治療法です。ホウ素(10B)をがんに集積させて中性子線を照射し、ホウ素の分裂により放出される放射線によりがんを殺傷する治療法であるため、ホウ素をがんに運ぶ薬剤が非常に重要です。本研究コンセプトのような同一構造化合物によるPET診断情報を利用した精密な治療計画を行うことにより、それぞれの患者により最適なBNCT治療の供給へつながると考えられます。現在、構造を最適化した更なる薬剤開発など、実用化を目指した研究を進めています。
ペプチドエマルションのアジュバント効果の検証
若林 里衣(九州大学 工学研究院応用化学部門 後藤・神谷研究室・助教)
ワクチンは、感染症の感染予防あるいは感染による症状の重篤化を抑えるために有効です。ワクチン効果を高めるために、アジュバントと呼ばれる添加剤が使われます。本研究は、水の中に油滴が分散したエマルションという形状が示すアジュバント効果に着目しました。特に、水中で繊維状の構造体を形成する自己組織化ペプチドを用いて、水と油の界面に抗原となるタンパク質を集めることが可能な、新しいワクチンアジュバントを開発し、免疫細胞へ効率的に抗原タンパク質を運ぶことに成功しました。
O-結合グリコシル化制御に基づくサルコペニアの新規治療法の開発
絹川 真太郎(九州大学 大学院医学研究院 循環器内科学分野・准教授)
本研究において、加齢に伴う骨格筋萎縮の進展に骨格筋タンパクのO-GlcNAc化が関係していることを明らかにした。骨格筋萎縮の新たな分子機序を明らかにした点が極めて意義が高く、今後O-GlcNAc化を制御する薬剤の開発により、現代の社会的な問題である老化によるサルコペニアの克服に貢献できると考える。
脳梗塞から神経細胞を守る分子メカニズムの解析
高橋 弘雄(香川大学 分子神経生物学・助教)
脳梗塞により、脳では大規模な神経細胞死が起こります。一度失われた神経細胞は再生しないため、神経細胞を守ることが予後の改善に極めて重要です。私達は、脳梗塞の直後に、脳が自身を守るためのメカニズムを活性化することを見出しました。これらのメカニズムを人為的に強く活性化することができれば、新たな脳梗塞の治療法に繋がると考え、その基盤となる基礎研究を進めています。
神経筋接合部の形態形成における細胞膜融合蛋白質群の役割
大河原 美静(名古屋大学大学院 医学系研究科 神経遺伝情報学・准教授)
本研究の目的は、身体の中で比較的大きな細胞で、多核である筋肉細胞が胎生期にどのように発達し、領域を決定しているのかを、最新の技術であるシングル核RNA-seqという手法で明らかにしたものです。本研究の結果は各発生段階の筋細胞の特徴を明らかにしただけでなく、今後筋肉の病態研究を行う際の基盤となる知識を含んでいます。
AM-RAMP2系とAM-RAMP3系の選択的制御による癌転移抑制法の開発
田中 愛(信州大学 医学部 循環病態学教室・博士研究員)
この研究から、AM-RAMP2系が血管の恒常性維持作用を介して癌の転移を抑制するのに対して、AM-RAMP3系が癌関連線維芽細胞の悪性度を高め、癌転移を促進させることが分かりました。選択的なAM-RAMP系の制御が、癌転移を抑制する治療法に繋がることが期待されます。
マクロファージの「動き」と「活性化」の相互連関メカニズム
遠田 悦子(日本医科大学 解析人体病理学・助教)
私たちはこれまで、炎症・免疫反応において重要な働きを担う単球・マクロファージの遊走を促進する分子、FROUNTの機能について解析してきました。新たに、FROUNTが活性化に伴う炎症性サイトカインの発現にも関与することを明らかにしました。ラットの腎炎モデルにおいては、FROUNTの阻害活性をもつ既存の嫌酒薬ジスルフィラムが腎炎を強力に抑制することを見出しました。単球・マクロファージの遊走と活性化は相互に関連しており、これらが過剰に働きすぎると組織傷害や病的な線維化の原因ともなることから、FROUNTはこれら双方を制御可能な標的分子として期待されます。
RNA修飾代謝による生体シグナル応答の機序解明にむけて
小川 亜希子(東北大学 加齢医学研究所 モドミクス医学分野・助教)
近年、DNAやタンパク質だけでなく、RNAもメチル化やアセチル化といった化学修飾を受けることが明らかになり、RNA修飾がエピジェネティクスに次ぐ新たな研究分野として定着しつつある。本研究ではRNA修飾代謝に着目し、その網羅的検出の最適化を行い、更にこの手法を用いて様々な検体を解析することにより成果を得た。更にm6Aの新たな代謝経路についても現在解析を進め、投稿準備中である。また、世界的パンデミックCOVID-19ワクチンのRNA修飾動態あるいは核酸治療薬の副作用の受容体活性についても明らかにすることができた。
インドール類の触媒的不斉ハロ環化反応による生物活性骨格構築
浅野 圭佑(北海道大学 触媒科学研究所 分子触媒研究部門(浦口研究室)・准教授)
医薬品などの機能性分子を効率よく合成することは、その安価・安定供給や新物質創成につながる基盤技術になり、人々の生活を豊かにします。不斉触媒はそれを実現する武器になりますが、速すぎる反応にはこれが利用できませんでした。この問題を解決するために、反応をあえて遅くする触媒を開発し、ハロゲン化反応による生物活性分子の合成を短工程化する反応原理を創り出しました。これをきっかけに、不斉触媒による医薬品合成がこれまで以上に発展すると考えています。
植物細胞核内アクチン繊維の構造および機能の解明
稲田 のりこ(大阪府立大学 大学院生命環境科学研究科・教授)
細胞骨格の一種であるアクチン繊維は、人や植物などの生物を構成する細胞内において、主に物質の輸送を制御する器官である。最近の動物における研究で、アクチン繊維が細胞核の中でも遺伝子発現制御に働くことが明らかになっている。私たちは本研究で、これまで一部の動物細胞でしか解析されていなかった細胞核内アクチン繊維が、植物細胞でも存在し、遺伝子発現制御を通して植物の病害応答や成長に寄与していることを強く示唆した。今後は、植物生理機能の制御における植物細胞核内アクチン繊維の役割を更に明らかにしていきたい。
胎生動物胚の体外培養を目指した発生休止誘導技術の開発
高岡 勝吉(徳島大学 先端酵素学研究所発生生物学分野・准教授)
本研究では、発生休止というこれまで分子学的に研究されてこなかった現象の分子メカニズムを明らかにします。得られた知見は、将来の胎生動物胚の完全試験管培養といった夢のような技術の開発につながります。
成果報告によせて - 2020年度受賞者から
-
(受付順、敬称略)
生体内における記憶ヘルパーT細胞の役割
常世田 好司(鳥取大学 医学部 免疫学分野・教授)
ワクチンは免疫記憶を誘導するためのものであり、記憶ヘルパーT細胞は免疫記憶や二次応答の中枢を担う細胞です。我々は、記憶ヘルパーT細胞は主に骨髄で維持されていることを示してきましたが、脾臓にも少数残っていることもわかっています。そこで、本研究では、骨髄と脾臓のどちらが二次応答時に主に働くのかを解明することを目的としています。これがわかることにより、ワクチン作製において、どちらの組織の記憶ヘルパーT細胞の形成・維持を指標にすれば良いのかが明らかになり、大変価値のある研究になります。本研究期間中には、骨髄の記憶ヘルパーT細胞が少なくとも非常に重要であることが明らかになり、大変有意義な研究になりました。
スプライシング変異白血病に対する新規ASO治療法の開発
吉見 昭秀(国立研究開発法人国立がん研究センター 研究所 がんRNA研究ユニット・独立ユニット長)
DNAの情報はmRNAに転写され、その後蛋白質に翻訳されることによってその蛋白質が細胞の中で様々な役割を果たします。未熟なmRNAは当初IntronとExonという2種類の配列を含みますが、スプライシング因子の働きによりIntron部分が除去され、成熟したmRNAになりますが、Intronを除去するこの働きをスプライシングと呼びます。近年、がんにおいてはスプライシングの異常が発がんに重要な働きをすることがわかってきました。本研究ではスプライシング異常を持つがんに対して、COVID-19ワクチンでも知られるようになった核酸医薬という新しいクラスの薬剤を開発する試みです。私たちの研究グループは、がんに対する核酸医薬を患者さんにお届けするため、今後も研究開発を続けて参ります。
脳形成における胎生期・発達期の獲得免疫細胞の意義
伊藤 美菜子(九州大学 生体防御医学研究所 アレルギー防御学分野・准教授)
発達期の脳形成における免疫細胞の影響について研究を行った。母体のウイルス感染などを模している母体免疫活性化モデルや、遺伝的な自閉症モデルの胎児や新生児の解析から、正常の胎児や新生児とは脳内免疫細胞の数や種類が異なることが分かってきた。今後は、この免疫細胞を制御することで、治療法の開発を目指していきたい
胎生期マウス大脳新皮質形成におけるサブプレート層の機能解明
丸山 千秋(公益財団法人東京都医学総合研究所 脳神経回路形成プロジェクト・プロジェクトリーダー)
胎児期に脳ができる際、数百億のニューロンの移動、配置や、神経回路形成は正確に制御されており、サブプレートニューロン(SpN)はそのキープレイヤーとして脳構築を促します。SpN活動の不具合は発達障害等の原因になると考えられますがメカニズムは不明なままです。本研究は、マウスモデルを用いてSpNの役割を明らかにすることで、 SpNの神経活動ダイナミズムによる脳発達過程の全容解明を目指しています。そのためにSpNの分子発現の特徴とサブタイプについてシングルセル解析を行い、新規の分子マーカーを同定しました。
感染防御における樹状細胞系譜早期運命決定の機序解明
黒滝 大翼(横浜市立大学 免疫学教室・講師)
私たちは『どのようにして造血幹細胞から数十種類もの血球細胞が産生されるのか』ということについて研究を行っています。最近の私たちの研究によって、造血幹細胞の上流の前駆細胞集団の中には、樹状細胞と呼ばれる免疫細胞のみを産生する亜集団が含まれることがわかってきました。私たちは、この造血早期における樹状細胞産生の仕組みが感染時に活性化することで樹状細胞のより素早い産生を可能にし、効果的に病原体を除去することに貢献しているのではないかと考えています。
IgM陽性形質細胞を伴う新腎炎のメカニズムの解明と血中に存在するIgM型自己抗体の網羅的解析
髙橋 直生(福井大学 医学系部門 腎臓病態内科学分野・診療准教授)
2017年私たちは、免疫グロブリンM (IgM) を作り出す細胞が多く腎臓内に存在する「新腎炎」を発見しました。その特徴を明らかにし、腎臓病学雑誌に報告しました。しかしこれは新しい病気のため、どういった要件が揃うとこの病気と言えるのかがまだ定まっていません。そこで、私たちは全国の施設から患者さんの検査情報や腎組織を集め、かなりの確率で診断できるような基準を作成しました。この結果、この腎炎が全国のどの施設でも診断できるようになります。また、この腎炎がなぜ、どのように起こってくるのかが全く分かっていません。今回、患者さんの血液を用いた解析から、本疾患の患者さんにのみ多く存在する分子の情報が分かり始めました。今後さらなる検討を行い、病気のメカニズムを明確にし、メカニズムに応じた治療法を考えて行きたいと思います。
アミロイドβ凝集抑制作用を有するフラバンポリフェノール類の合成と機能開拓
大森 建(東京工業大学 理学院化学系・准教授)
緑茶やワイン等に多く含まれるポリフェノール類には、様々な生理作用が認められている。例えば、複雑な環状構造を持つフラバンオリゴマーには、最近、アミロイドβの凝集を抑制することが明らかにされている。このことはポリフェノールの科学に新たな可能性を示すものであるが、より詳細な研究を進めるためには、多種多様な類縁化合物を高純度サンプルとして得、それらを用いて系統的に生理活性評価を行ってゆく必要がある。本研究では、これらの一連の化合物の合成研究を行い、これまで天然から得ることの難しかった複雑なポリフェノール類の供給の道を拓いた。さらに、これまで未知であったある種のフラバンオリゴマーが顕著なアミロイドβ凝集抑制作用を示すことを明らかにした。
植物の気孔腔形成メカニズムの分子遺伝学的解析
吉田 祐樹(熊本大学 大学院先端科学研究部・特任助教)
植物の葉は光合成の際に二酸化炭素を吸収し、その取り入れ口である気孔については研究が進んでいます。気孔から取り込んだ二酸化炭素を、光合成を行う葉肉細胞に行き渡らせるためには葉の内部にも隙間が必要ですが、隙間を形成する仕組みは全く不明でした。私は、気孔からホルモンの一種が分泌され、それを受け取った気孔近くの葉肉細胞だけが活性化され、細胞間に隙間を作り出す指令となることを発見しました。この仕組みは実験植物だけでなく野菜でも共通しているらしく、より二酸化炭素を吸収する品種が将来的に作れると期待されます。
高効率的合成に基づく稀少多環性マクロリド天然物の創薬展開
石原 淳(長崎大学 薬学部 薬品製造化学研究室・教授)
今回、我々はイグジグオリドという未来の抗がん剤の候補化合物に着目し研究を行いました。本化合物は天然界から極微量しか得らず、材料不足で創薬研究が進まないという問題がありました。今回、我々は簡便で大量供給可能な合成方法を開発しました。同時に基礎研究に必要な様々な類似化合物を作り出す方法を見出し、ガン細胞に対する活性を調べました。残念ながら、新薬に結びつく結果はまだ得られておりませんが、今後も、より活性が強く、ガン特異的に効く新しい化合物の合成を検討していきます。いつか新しい医薬品を皆様に提供できる日が来ることを望んでおります。
光学活性医薬品合成を指向したアシルピラゾールの触媒的不斉α-ハロゲン化反応の開発
石原 一彰(名古屋大学 工学研究科有機・高分子化学専攻触媒有機合成学研究室・教授)
カルボン酸誘導体のα位の水素をハロゲンで置換し、光学活性α-ハロカルボン酸誘導体を触媒的に不斉合成する方法を開発した。本法で生成するα-ハロカルボン酸誘導体からα-アミノ酸誘導体に化学変換することができることも確かめられており、様々なα-アミノ酸が不斉合成できることになる。α-アミノ酸は医薬品の原料としての用途価値があることから、本研究成果は医薬品の製造や創薬研究に有効である。
病原微生物の浸潤進化に学ぶ休眠遺伝子活性化法の開発
荒井 緑(慶應義塾大学 理工学部生命情報学科 ケミカルバイオロジー研究室・教授)
我々は近年,病原放線菌と動物細胞の共培養法を開発し,放線菌の休眠遺伝子活性化に成功し新規化合物を得ている.この新規手法は,病原微生物が動物に感染する際の状況を再現し,疑似感染状態を模倣したもので,国内外でも初めての例であり独創的で新規性が高い.本研究では,どうやって休眠遺伝子が活性化されるのかを探るとともに,新たに病原真菌と動物細胞の共培養に取り組み,休眠遺伝子活性化による化合物の取得に成功した.これらの現象は,異種生体間相互作用が基盤となる休眠遺伝子活性化であり,大変に興味深く,我々はそのような化合物生産を「浸潤進化」の結果であると考え,メカニズム解明に取り組んでいる.
赤色光作動性の遺伝子発現光操作技術の開発と改良研究
河野 風雲(東京大学 大学院総合文化研究科 佐藤守俊研究室・助教)
本研究では,遺伝子工学的手法を基にタンパク質工学を施した光遺伝学を基盤技術として,哺乳動物生体内で遺伝子発現の光操作を高い光誘導効率で実現するために,シグナル増幅法を組み合わせた赤色光作動性の遺伝子発現光操作技術の開発に取り組んだ.放射線耐性細菌由来の赤色光受容体バクテリアフィトクロムDrBphPを基に,赤色光による遺伝子発現の操作を実現する新規基盤技術を開発した.本技術はシグナル増幅法とさらに組み合わせることによって,遺伝子発現の劇的な増幅を実現することが期待される.それにより現在の光遺伝学が抱える青色光の組織透過性の問題に対して,赤色光受容体を用いることでその克服が期待される.また同時に既存技術の実用性の問題に対して,高い光誘導効率を実現する.本研究の成果は,現在の光遺伝学の基盤技術を大きく底上げし,当該領域全体に大きな波及効果が得られることが期待される.さらに,生きた哺乳動物生体内で実用的な光遺伝学の技術として,臓器再生医療や様々な疾患治療法など,これまでの光遺伝学が応用困難であった未開拓の研究領域に応用する展開が期待される.
不妊不育に関わる原因遺伝子の解明
石黒 啓一郎(熊本大学 発生医学研究所・准教授)
我々が同定した減数分裂開始のマスター転写因子MEIOSINによって直接制御される標的には多くの機能未解析の遺伝子が含まれている。これらMEIOSINの転写制御下に置かれている未解析の遺伝子には、減数分裂の進行に必要とされる未知のものが含まれる可能性があり、一挙に減数分裂の仕組みの解明に迫る足掛かりを得ることが期待される。本研究によって、このうちの一つであるFbxo47遺伝子やZfp541遺伝子が減数分裂において極めて重要な働きをすることや、これらの欠損によって雄性不妊を示すことを明らかにした。減数分裂開始因子の親玉を押さえたことで、体細胞分裂と減数分裂との本質的な違いを決定付けるメカニズムの全容解明に向けて、国際的にも圧倒的に有利な状況で今後の研究を推進することができる。また、疾患モデル動物による検証を組み合わせた研究により、減数分裂の基礎研究とともに不妊に関連する原因因子の特定に資することが期待される。
ゲノム・エピゲノム・トランスクリプトーム(GET)によるDNA複製の多層的な制御及び細胞老化におけるその生物学的な機能
シャリフ ジャファル(理化学研究所 生命医科学研究センター(IMS) 免疫器官形成研究チーム・専任研究員)
細胞老化は免疫応答などを司る幹細胞の増殖を制御し、健康寿命に密接に関わっている。さらに、細胞老化機構の異常は細胞の無限増殖を誘導することで癌などの原因にもなり得る。そのため、健康状態の維持や癌抑制などの観点から、細胞老化の分子機構の解明は重要な意味を持つ。本研究では、初代マウス胎児線維芽細胞(pMEF)と用い、活発に増殖する細胞とほとんど増殖を止めている老化細胞を比較した。この比較から、活発に増殖する細胞ではヒストンH2Bものユビキチン化(H2Bub)レベルが高く、一方で増殖をほとんど止めている細胞ではCTCFという分子の結合が強くなることを見出した。今後、本研究で明らかになったH2BubやCTCFなどの因子に着目していくことで、細胞老化の分子メカニズムをより深く理解し、さらにその先にある医薬品開発などにも結びつけたいと考えている。
アルツハイマー病発症機構解明に向けた神経細胞内MARK4基質の網羅的な同定
安藤 香奈絵(東京都立大学 大学院理学研究科神経分子機能研究室・准教授)
私たちは、アルツハイマー病など認知症の原因となる神経変性疾患の発症メカニズムを研究しています。これらの疾患では、記憶など認知機能を担う脳の細胞が死んでいきますが、それを止める手立ては今のところありません。なぜ脳の細胞が死んでしまうのかが分かれば、根本的な予防法、治療法の開発につながります。この研究では、アルツハイマー病脳で増加し、細胞死に関わると考えられている酵素について調べました。細胞死に関わる経路を解明することで、新しい薬や治療法の開発につながることが期待されます。
新規生体内β細胞Ca2+イメージング法による生体内インスリン動態解析
金丸 和典(日本大学 医学部細胞分子薬理学部門・准教授(研究所))
観測方法が存在しないために未解明な体内インスリン動態の謎は数多く存在する。本研究では生体内で唯一のインスリン供給源である膵β細胞のインスリン放出動態を、膵β細胞内のカルシウム動態で間接的にモニターするという、これまでは非常に困難であった手法の開発に挑戦した。モデル動物として遺伝子改変マウスを用いた実験により、生きたマウス体内での膵β細胞内のカルシウム動態の可視化解析に概ね成功している。この手法を用いたさらなる研究は、インスリン分泌機構とインスリン体内動態のさらなる理解、ひいては糖尿病の新規治療法のヒントを与える可能性が期待される。
社会的隔離による行動障害と脳内グリア機能の連関の解明
松井 広(東北大学 大学院生命科学研究科 超回路脳機能分野・教授)
新型コロナウイルスによる外出禁止は、社会との隔離がされている状態です。本研究では、社会的環境要因によって変化する脳内活動をマウスから記録しました。中でも、自閉スペクトラム症との関連が指摘されている小脳に注目しました。さらに、本研究では、神経細胞ではなく、神経活動の動作モードを左右するグリア細胞の活動を計測しました。従来、もっぱら運動学習に関わるとされてきた小脳が社会性行動に関わることが示唆されました。今後、小脳グリア細胞活動をターゲットにした創薬等によって、社交障害を克服する治療戦略が立てられる可能性が期待されます。
ICF症候群の間葉系幹細胞モデルにおけるDNAメチル化と転写制御のゲノムワイド解析
アディソン ウィリアム(九州歯科大学 分子情報生化学・助教)
出生時にみられる奇形のうち頭蓋顔面領域に発生するものが3分の1以上を占めています。この頭蓋顔面奇形において、手術などによる奇形の改善には大きな進歩が見られますが、奇形の発生に関わる分子を標的としたような治療法はほとんどありません。 その理由として、頭蓋顔面奇形の発生は複数の転写因子、成長因子および受容体などが複雑な交絡していることが挙げられます。したがって、頭蓋顔面奇形の病態生理を分子レベルで理解するための研究が必要です。最近、頭蓋顔面奇形が出現するICF症候群においてZBTB24という遺伝子に変異があることがみつかりました。そして今回この助成金をいただいたことで、ZBTB24の変異が頭蓋顔面奇形を引き起こす分子メカニズムの一端を明らかにすることができました。今後、本研究を発展させ、疾患のより深い理解、ひいては治療法の開発につなげていきたいと考えています。
ヒト老化細胞に形成される3Dゲノム構造とその形成に関わるタンパク質組成の解明
野間 健一(北海道大学 遺伝子病制御研究所・教授)
細胞老化は、細胞の異常な増殖を防ぐことを通じて、極めて重要ながん抑制メカニズムとして機能しています。申請者グループは、ゲノミクスとプロテオミクスの技術をヒト細胞に適用し、細胞老化の各段階における3Dゲノム構造の経時変化とその背景にあるタンパク質群の挙動を包括的に理解する事を目的に実験を行いました。その結果、老化細胞の3Dゲノム構造とそれを形成するクロマチンタンパク質の組成を明らかにすることができました。
AIモーションキャプチャーによる中枢神経損傷後生理機能回復-シナプスコネクターと再生阻害因子制御を利用した脊髄損傷後超回復モデル-
武内 恒成(愛知医科大学 医学部生物学・教授)
現在、根本治療法がない脊髄損傷に対して、我々は損傷部に発現する神経再生阻害因子であるコンドロイチン硫酸の発現を抑制する手法(再生環境の整備)と、新しい人工合成神経シナプスオーガナイザーCPTX投与による神経再編(人為的な神経回路再構築)の二つの新たな方法論の展開を進めている。今回、これまで治療が特に難しいとされる罹患後慢性期でのこれらの可能性を示すことが出来、さらにヒトでの治療に外挿するためにモデル動物の回復過程をAI機械学習で抽出することが出来るようになった。これらをさらに臨床での応用に向けて展開することを目指している。
光学活性化合物の迅速合成と機械学習を基盤とする医薬資源の探索
滝澤 忍(大阪大学 産業科学研究所・准教授)
本研究では、有毒な遷移金属を必要としない官能基選択性に優れた有機分子不斉触媒を活用して、「ドミノ倒しゲーム」の様な連続反応を積極的に合成プロセスにデザインすることで、医薬品候補迅速合成を達成しました。抗癌剤への応用が期待される新規Wntシグナル阻害活性シードの効率的な探索とその作業工程でのコスト(資源・時間・廃棄物等)削減を両立すべく、剛直な骨格を有するスピロオキシインドールをファーマコフォアとするデジタルデータベースを構築し、機械学習研究と融合することで、TCF転写阻害活性試験結果と光学活性スピロオキシインドール構造の相関解明を目指しました。
立体分岐型合成を実現するタンパク質配位子ライブラリーの開発
藤枝 伸宇(大阪府立大学 大学院生命環境科学研究科生物物理化学研究室・准教授)
新たな物質を作り上げる合成化学の究極的な目的の一つは原子配置を自在に制御することです。すでに科学が発展し、そんなことは当然のようにできると思われているかもしれません。しかし、非対称分子と呼ばれる複雑な化合物を合成することはいまだに極めて難度が高いとされています。そういった化合物は医薬品や農薬などの有用物質になるため、自在に高難度化合物を簡便に作り分ける手法、立体分岐型合成システムの構築が今なお活発に研究されています。そのため、今後、本研究で得られた結果が発展することで究極の触媒が完成し、効率的な有用物質生産へとつながると期待されます。
新型コロナウイルスの細胞内動態の解明
高松 由基(国立感染症研究所 ウイルス第一部・主任研究官)
ライブセルイメージングは病原体の細胞内複製機構を理解するための非常に強力で有用な技術である。本研究では、喫緊の国際公衆衛生上の重要課題である新型コロナウイルス:SARS-CoV2を研究対象とし、ウイルスの複製機構を解明することを目指す。SARS-CoV2の細胞内動態については不明な点が多く、移動に関わる宿主因子もわかっていない。病原体の細胞内動態を解明することは、侵入経路・輸送経路や介在タンパク質、出芽制御因子を介した治療法を開発するための基盤となることが期待される。
細胞ストレス応答と炎症反応の解析から迫る「疲労メカニズム」の分子細胞生物学的な解明
岩脇 隆夫(金沢医科大学 総合医学研究所 細胞医学研究分野・教授)
「疲労」は「発熱」や「痛み」と共に生体3大アラームと言われ、私たちの生命や健康を維持する上でカラダが発する重要なシグナルである。しかしその研究と理解は発熱や痛みに比べて遅れており、科学が進んだ現代でも疲労の実態は掴めていない。そこで本研究では疲労が生じる際や疲労が回復する際のカラダの仕組みを分子生物学および細胞生物学のレベルで解明することに目標を定めている。特に細胞ストレス応答で機能する分子や細胞の働きと疲労との関連性に着眼して研究を進めている。この研究は単に基礎的な生命科学へ貢献するだけでなく、疲労が生む社会問題(健康障害から事故・自殺に至るまで)に対する解決への新たな糸口になる可能性を十分に含んでいる。
Sirt1-NAD+経路による炎症性腸疾患とその関連大腸がんの抑制機構の解明
天野 恭志(近畿大学医学部 生化学教室・助教)
今回申請者は、炎症性腸疾患のモデル実験において、生体内でNAD+量を高めることで腸内細菌叢のバランスが回復することや、炎症性腸疾患に関連した大腸がんの成長を弱めることを示した。そして、細胞内のNAD+量を高めるとSirt1の機能を介して、ミトコンドリア機能が活性化することが明らかになった。
PDXモデルにおける乳癌転移に必須な宿主因子の解析と標的治療の探索
高井 健(埼玉県立がんセンター 乳腺腫瘍内科・医長)
乳癌の死亡の主な原因は転移であるため、転移の予防や治療が重要です。今回の研究では、乳癌マウスが転移を起こす肺において、好中球が増殖しており多くの遺伝子を活性化させていることがわかりました。この好中球が肺転移を促進する可能性があり、標的薬剤があれば転移の予防や治療に役立つかもしれません。抗癌剤やホルモン剤だけでは困難な転移の予防・治療に新しい選択肢を提供したいと考えています。
miRNA 生合成制御に関わる RNA 結合蛋白質の網羅的同定のための数理学生化学解析的アプローチの開発
岡村 勝友(国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 RNA分子医科学研究室・教授)
癌は遺伝子の病気と言われるように、癌組織では多くの遺伝子の異常が見られます。最近のゲノム解析技術の進歩により、遺伝子に異常やそれぞれの遺伝子の活性化状態を定量的かつ網羅的に解析できるようになりました。今回の研究ではそのような網羅的な定量情報の数理解析によりmiRNAと呼ばれる遺伝子群の活性調節に関わる遺伝子を推定し、その推定結果を実験的に検証しました。その結果、これまではmRNAという別のタイプの遺伝子の調節を行うと知られていた遺伝子が、miRNAの調節も行うことを見出しました。タイプの異なる遺伝子が協調的に制御される仕組みを理解することで、なぜ癌が起きるのかという根本的な疑問への答えへと繋がると期待しています。
Dysbiosis に基づく腸管上皮細胞代謝異常を標的とする新規 GVHD 機序の解明と治療応用
藤原 英晃(岡山大学病院 血液・腫瘍内科・助教)
白血病の根治治療として行われる同種造血細胞移植には致命的となる移植片対宿主病(GVHD)が併発します。その予防・治療には免疫抑制剤を用いた治療が行われますが過剰な免疫抑制は白血病の再発や感染症などの合併症が増加します。近年腸内細菌叢の乱れがGVHDの増悪に関連していることが明らかとなりましたが、その原因は不明です。本研究では免疫細胞による腸管上皮細胞のミトコンドリア障害による代謝異常が組織脆弱性と腸内環境の変化をきたすことを見出しました。今後は詳細な機序を明らかにすることで組織代謝を向上させ、免疫抑制剤を減量した効果的な治療を見出すことを目標に、研究を続けて参ります。
中枢への薬物輸送を可能にする超分子ヒドロゲルの開発
木村 真也(明治薬科大学 薬化学研究室・助教)
アルツハイマー病をはじめとする中枢神経疾患の治療薬開発は非常に困難です。その原因の1つとして、脳に存在する血液-脳関門と呼ばれるバリア機構の存在が挙げられます。血液-脳関門は、脳への異物の侵入を防ぐ役割を担っていますが、脳への薬の移行をも妨げてしまうのです。そこで、薬物送達システムと呼ばれる、薬を患部へ届ける技術が注目されています。本研究では、超分子ヒドロゲルという機能性材料に着目し、新たな薬物送達システムを開発します
胆汁酸をリードとした高活性な非セコステロイド型ビタミンD誘導体の創製
棚谷 綾(お茶の水女子大学 基幹研究院自然科学系・教授)
ビタミンDはカルシウムやリンの恒常性維持、骨代謝、免疫機能制御などの様々な重要な生理機能を司っています。これまで、骨粗鬆症や乾癬などの治療薬開発を目的に何千ものビタミンDの誘導体が創製されてきましたが、医薬品になった化合物を含めて高活性誘導体はいずれも天然のビタミンDと同じ骨格構造を持っています。私たちは、より幅広い疾患におけるビタミンDの医薬応用を目的に、新しい骨格構造をもつ化合物の創製を行いました。胆汁酸の1種であるリトコール酸の構造をもとに種々の化合物を設計、合成したところ、非常に高いビタミンD活性を有する新規化合物を見いだすことができました。
神経幹細胞が多種多様な神経を作り分ける分子機構の解明
鈴木 匠(茨城大学 発生生物学研究室・助教)
神経幹細胞から生み出された多様な神経が、正しい場所に移動し、最適な相手と結合することで正確な神経回路が構築される。神経幹細胞では、Temporal Factors(TFs)という転写因子群が特定の順序で発現することで、多様な神経を作り分けているが、TFsの下流でどのような遺伝子が制御され細胞運命を決定しているのかについては不明な点が極めて多い。本研究では、TFsの1つであるSlpの下流遺伝子を探索しSlpTC12遺伝子を同定した。今後SlpTC12の機能を解析することによって、神経幹細胞が多種多様な神経を作り分ける分子機構の解明の糸口が得られると期待される。
シングルセル解析とリピドーム解析を用いた、急性腎障害が慢性腎臓病へ移行する機序の解明
山本 毅士(大阪大学医学部附属病院 血液浄化部・医員)
2016年、大隅良典氏がオートファジー研究によりノーベル医学生理学賞を受賞されました。私たちはこれまで腎疾患におけるオートファジーの研究に取り組んできました。今回、急性腎障害の回復期において、オートファジー関連遺伝子Atg5は、傷害ミトコンドリアを選択的に除去するオートファジー(マイトファジー)と、同時にミトコンドリア再生を促進することによって、慢性腎臓病への進展を抑制することがわかりました。今後シングルセルとリピドームの統合的な解析を用い、細胞運命決定に関わる因子と病態関連脂質を同定し、創薬・バイオマーカー確立につなげたいと考えています。
肝臓における摂食依存性の遺伝子発現の細胞間相互作用を介した制御機構の解明
酒井 真志人(日本医科大学 大学院医学研究科 分子遺伝医学分野・教授)
肝細胞の代謝酵素の量は、摂食状態に応じてインスリン・グルカゴンなどのホルモンにより調節されています。一方、糖尿病では、そのような代謝酵素の量を調節する仕組みが破綻し、脂肪肝や高血糖の原因となります。そのため、肝細胞の代謝酵素の量を調節する仕組みの理解は、糖尿病・代謝疾患の研究の重要な課題のひとつです。肝臓は、肝細胞以外にも様々な細胞が集まってできています。本研究で、私たちは肝臓にいる免疫細胞であるクッパー細胞が肝細胞の機能調節をおこなう可能性を考え、検討しました。その結果、クッパー細胞には、肝細胞における摂食状態に応じた代謝酵素の量の調節を助ける働きがあることが明らかとなりました。
ヒト形質賦与マウス作製に向けたノンコーディングRNA情報活用システムズアプローチ
今村 拓也(広島大学 大学院統合生命科学研究科生命医科学プログラム・教授)
薬の開発を含む哺乳類の実験は、ネズミを中心に行われてきました。ネズミとヒトの脳は、異なるところも数多くありますが、遺伝子のはたらきは共通なのです。では、共通なのにもかかわらず、脳のかたちやはたらきに違いがあるのはなぜでしょうか?鍵を握るものの1つが「タンパク質に置き換わらないRNA」、ノンコーディングRNAです。すべての遺伝子はRNAに置き換わることで機能しますが、RNAにはタンパク質に置き換わるものと、置き換わらないものがあります。今回たくさんのヒト特異的機能ノンコーディングRNAを発見したことにより、創薬を今よりスピーディに行うことに貢献できます。
Ca2+シグナル制御因子を介した新規エネルギー代謝調節機構の解明
西谷 友重(和歌山県立医科大学 薬理学講座・教授)
肥満は糖尿病、心筋梗塞や脳梗塞など命にもかかわるような重大な病気の原因となり得ることから、その調節機構を明らかにすることは重要です。細胞内カルシウムは脳や心臓の働きに極めて重要なことが知られています。今回、そのカルシウムの働きを調節するNCS-1というタンパク質の欠損マウスが顕著な肥満となることから、NCS-1が肥満抑制に関わるのではないかと考え、その原因を探りました。その結果、NCS-1は摂食量や運動量には影響を与えず、基礎代謝を高めることにより肥満防御に働いていることが初めて明らかとなりました。今後はNCS-1関連シグナルを標的として、肥満を抑制する薬物の探索ができることが期待されます。
細胞外マトリクスを介した血管機能を制御する新しい分子メカニズムの解析とマウスモデルを用いた治療効果の検証
山城 義人(筑波大学 生存ダイナミクス研究センター・助教)
細胞外マトリクスFibulin-4(Fbln4)の血管内皮細胞における役割は未知であり、その破綻が様々な病態発症に寄与することを見出しているものの、その分子メカニズムは不明です。本研究では、内皮細胞におけるFbln4の役割を明らかにするために、ヒト血管内皮細胞やマウス内皮細胞でFbln4を欠損させ、その機能異常を精査しました。Fbln4欠損内皮細胞は、間葉系細胞に類似した形態変化を示し、その遺伝子発現も内皮細胞とは異なるように変化していました。また、内皮細胞や平滑筋細胞でのFbln4欠損マウスは大動脈弁の肥厚と大動脈瘤の悪化が観察されたことから、内皮細胞におけるFbln4が動脈弁-血管の恒常性を保護する役割を担うことが明らかとなりました。Fbln4の役割を補うことが、大動脈瘤の治療に必須であることが示唆されます。今後はヒト臨床検体における検証を重ね、臨床応用に繋げることを期待しています。
マイクロバイオームが亢進する生殖機能とその分子機構の解明
須山 律子(大阪大学 大学院生命機能研究科 生殖生物学研究室・特任助教)
体内、特に腸内に多く存在する常在細菌は宿主の免疫、代謝などの生理作用に影響を与えることから、疾患との関連のみならず、健康保持や免疫力向上の面でも注目されています。本研究では微生物の持つ生殖能力の向上機能に着目しました。我々はモデル生物であるキイロショウジョウバエを用いて、微生物叢によって引き起こされる卵巣の発達、それに寄与する分子メカニズムの解析を行いました。その結果、微生物叢により生殖幹細胞が増殖し、卵形成の各発生段階が影響を受けて卵成熟が促進されることがわかりました。さらに微生物叢によって活性化されるホルモン経路を同定し、また別法での低分子化合物のスクリーニングにより生殖幹細胞の増殖作用に特異的に機能する化合物を特定しました。これらの結果は特異的な分子経路の活性化や化合物の供与により生殖機能を向上させることができ、ヒトを含む哺乳類にも適応できることを示唆しています。
胎生時期に着目した偽性副甲状腺機能低下症の新規治療方法の開発
黒坂 寛(大阪大学大学院歯学研究科 顎顔面口腔矯正学教室・講師)
偽性副甲状腺機能低下症(Pseudohypoparathyroidism:PHP)は国内での有病率が3.4人/100万人と推定されている多臓器不全を伴う希少疾患である。PHPの原因遺伝子は Gタンパク質共役受容体に属するGNASとされている。本研究では現在のところ不明な点も多かったPHPの胎生期における病態に着目し新たな知見を得る事が出来た。本研究結果はPHPの新たな診断方法や治療方法の開発が行う上での基盤的データとなる。
神経性臓器連関のメカニズムから読み解く肝代謝恒常性とその破綻の解明
井上 啓(金沢大学 新学術創成研究機構 栄養・代謝研究ユニット・教授)
脳は、全身のエネルギー状態を感知し、代謝恒常性維持の中心臓器である肝臓を制御する。この脳-肝連関は、肥満・インスリン抵抗性で障害され、その障害は糖代謝異常の原因になる。脳-肝連関は、迷走神経α7型ニコチン受容体作用を介している。一方で、α7型ニコチン受容体作用は、炎症制御に関与することも知られている。本研究では、α7型ニコチン受容体欠損マウスの検討から、脳-肝連関の障害が、脂肪肝に伴う肝慢性炎症の病因となることを見出した。脂肪肝に伴う慢性炎症は、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)として、世界で4人に1人が罹患する保健上の課題である。本研究は、脂肪肝における脳-肝連関の役割解明により、肥満・インスリン抵抗性の病態理解を進めるものであり、また、新規NAFLD治療標的としての迷走神経α7型ニコチン受容体作用の可能性を示すものである。
成果報告によせて - 2019年度受賞者から
-
(受付順、敬称略)
がん酸化ストレス応答のシステマティックな理解
髙橋 重成(京都大学白眉センター・特定准教授)
かつて数十年もの間、ビタミンCやビタミンEをはじめとした抗酸化サプリメントは癌抑制効果があると信じられてきましたが、近年行われた大規模疫学調査により、抗酸化サプリメントの摂取はむしろ癌の発生率を上昇させることが明らかにされました。
癌細胞は、正常細胞が本来存在している場所を逸脱して生存・増殖することが知られていますが、近年の研究により、このようなニッチの逸脱は高いレベルの酸化ストレスにさらされることになり、抗酸化を含めた強固な酸化ストレス防御機能の獲得が癌化および癌の成長過程において必須であることが分かってきました。実際、放射線治療や一部の癌化学療法は酸化ストレスを亢進させることで癌細胞を攻撃することが知られており、癌細胞は正常細胞に比べて酸化ストレスに対して脆弱であるといえます。
このように、癌と酸化ストレスとの間には密接な関連性がありますが、腫瘍内1細胞レベルで酸化ストレスを可視化した例はこれまで存在しませんでした。 本研究では腫瘍内酸化ストレスの度合いを1細胞レベルで検出することに成功し、また強い酸化ストレスにされされているがん細胞は他とは違う特徴的な性質を有することが明らかになりました。 本研究による成果は、酸化ストレス防御を標的とした新しいがん治療薬の開発につながることが期待できます。植物の光受容体フィトクロムによる転写開始点制御の分子機構解明
松下 智直(九州大学大学院農学研究院・准教授)
同規模の転写開始点変化は、フィトクロムシグナルに限らず、ありとあらゆるシグナル・事象に伴って、真核生物において共通の分子機構で起こるものである可能性が高いと考えられるため、その分子機構が本研究により解明されれば、1つの遺伝子から機能の異なる複数のタンパク質を生み出す普遍的な仕組みを世界に先駆けて明らかにすることとなり、生物学上の大きな進歩となることは間違いないと考えられます。
ウサギ心房細動モデルに対する炭素線照射がコネキシンおよび交感神経発現と抗不整脈効果に及ぼす影響の検討
網野 真理(東海大学医学部内科学系循環器内科・准教授)
体幹部定位放射線治療などの放射線技術を “難治性致死性心室不整脈 (心室頻拍)”に対して応用する発想により,「X線を体外から照射して不整脈基質をわずか15分で焼灼する」という新しい治療法が2017年にワシントン大学にて実施され,その成果は瞬く間に循環器領域のトップニュースとなりました (NEJM, 2017).東海大学でも2019 年11月, 日本人で第一例目となる臨床治療を実施し(jRCTs032190041), その効果につき論文報告を行っています ( Heart Rhythm Case Reports 2021). しかし,なぜ放射線が不整脈治療に有効であるかの理由は十分に明らかではありません. 我々は世界に先駆けて1997年より「重粒子線(放射線のなかで健常組織への影響が少ない)を利用し, 心臓に及ぼす電気生理学的効果について」基礎研究を実施してきました (放射線医学総合研究所との共同研究). 放射線による抗不整脈作用の主要なメカニズムは,「ギャップ結合蛋白コネキシン43 (Cx43) の亢進による興奮伝導の回復」に起因することを発見しましたが, 今回の研究ではさらに,「心表面の過剰な交感神経増生の除神経作用を呈する」可能性を明らかにしました. 現在は重粒子以外にX線についても基礎実験を施行し, 放射性臓器障害を最小限にとどめつつ, 最大効果を得るためのデータを蓄積中です.
アスガルド古細菌に探る細胞形態の制御機構の分子進化
千住 洋介(岡山大学異分野基礎科学研究所・助教)
真核生物に近い系統と考えられている、アスガルドと命名された新規古細菌のメタゲノム解析から、細胞膜の形態変化を制御するタンパク質をコードする遺伝子が発見された。本研究課題では、アスガルド古細菌の新規タンパク質の立体構造を解き、生物物理的手法と細胞生物学を組み合わせてその機能を解明する。さらに、原核生物にも保存された真核生物と同様な細胞機能を見いだしていくことで、生命の起源の一端を解明していく。
薬物代謝を触媒するグルクロン酸転移酵素の量子ビームを用いた構造形成の解析
溝端 栄一(国立大学法人大阪大学大学院 工学研究科 応用化学専攻・講師)
生物の細胞はタンパク質でできています。タンパク質は様々な構造をもち、この構造はGroELと呼ばれる巨大なタンパク質の中で形づくられます。今回、体内の有毒物質や薬剤の解毒を担うタンパク質であるグルクロン酸転移酵素が、GroELにどのように認識されて構造が形成されるのか、そのメカニズムの一端を、クライオ電子顕微鏡を用いて可視化することができました。将来、がんや黄疸などの病気の治療につながる成果です。
血管内皮細胞における細胞内コレステロール輸送の新規分子基盤
前川 大志(愛媛大学 プロテオサイエンスセンター 細胞増殖腫瘍制御部門・テニュアトラック助教)
全身に行き渡る血管は人体最大の臓器の一つです。血管の内側に存在し、血流と直に接する血管内皮細胞は炎症反応や血管新生等の生理機能発揮に重要な役割を持ちます。近年の研究で、血管内皮細胞内でコレステロールが細胞膜に適切に存在する事が血管内皮細胞の機能に重要である事が分かってきました。一方で、血管内皮細胞内のコレステロールを適材適所に配置させる仕組みは良く分かっていません。本研究では、この仕組み (=コレステロールの細胞内輸送)の分子機構の一端を解明する事に成功しました。今後は当該分子機構を標的とする新しい医薬品 (血管新生阻害剤等)開発への応用が期待されます。
加齢に伴う腸管細胞の細胞競合機能低下に起因する発がん機序
昆 俊亮(東京理科大学生命医科学研究所・講師)
本研究成果より、細胞競合の機能変容によって、がん変異細胞が基底膜へとびまん性に浸潤する分子機構の一端を明らかにすることができました。具体的には、Wntシグナルの活性化によって、細胞非自律的にNF-κBシグナルが活性化され、さらにマトリックスメタロプロテアーゼであるMMP21の発現が増加することにより、がん細胞が基底膜浸潤能を獲得することが分かりました。びまん性の悪性腫瘍は一般的に予後が悪く、革新的な治療法が希求されているため、本研究により明らかとなったNF-κB-MMP21経路が治療標的となることが今後期待されます。
慢性胃炎粘膜における発癌リスク腺管の同定と発癌予防
清水 孝洋(京都大学医学部附属病院内視鏡部・助教)
H.pylori感染による慢性胃炎粘膜に発生する腸上皮化生は前癌病変であるのか傍癌病変であるのかは議論の分かれるところである。そこで、本研究では、慢性胃炎粘膜から腸上皮化生と非腸上皮化生を取り分け、網羅的なゲノム解析を行うことで、その点を明らかにしようとした。腸上皮化生には、早期胃癌とほぼ同じ数の遺伝子変異を認め、また早期胃癌でよく見られるコピー数異常も認めた。本研究の結果は、腸上皮化生から胃癌が発生することを直接証明したわけではないが、腸上皮化生が前癌病変である可能性を示唆する結果であった。腸上皮化生の発生予防や、腸上皮化生をターゲットとした治療に向けて現在研究を継続中である。
統合的インフォマティクス解析を用いた造血幹細胞の炎症記憶のメカニズム
滝澤 仁(熊本大学国際先端医学研究機構・特別招聘教授)
炎症は病原体に対する生体防御および組織修復を促進するための主要な免疫応答です。骨髄はほとんど免疫応答が起こらない免疫特権臓器の一つとして、長命の血液細胞および免疫細胞を保存するのに有利な環境を形成すると考えられてきました。しかしながら、近年、骨髄では実に活発で多様な免疫応答が行われており、血液の源泉である血液幹細胞の機能特性に多大な影響を及ぼすことが分かりつつあります。本研究では、炎症が血液幹細胞機能 を適応させ、感染症、炎症および血液悪性腫瘍などに対してより応答性のある血液・免疫系を構築する という“血液幹細胞の炎症記憶”という概念を検証します。得られる知見は、様々な感性症に対するワクチン戦略や老化に伴い増加する炎症疾患の制御や治療に対して非常に 有用な知見をもたらすものと期待されます。
新規抗結核薬の開発を目指した結核菌病原因子の作用機序の解明
高江洲 義一(琉球大学熱帯生物圏研究センター 分子感染防御学分野・准教授)
本研究では、結核菌(Mycobacterium tuberculosis)が産生する炎症抑制因子の作用機序の解明を目的として、まず宿主側標的タンパク質を同定し、その遺伝子を破壊した細胞を作製して、この宿主タンパク質が炎症誘導に重要な役割を果たす新規制御因子であることを見出しました。本研究の成果は、宿主免疫応答を増強するタイプの新たな抗結核薬、新しい結核ワクチン、さらには近年注目されている「訓練免疫」を増強することによる感染症の治療法や予防法の創出に繋がるものと期待されます。
自閉症スペクトラムにおける、オキシトシン作用機序の解明
奥山 輝大(東京大学定量生命科学研究所・准教授)
自閉症スペクトラムは、社会性コミュニケーションなどに異常を示す発達障害で、その病態神経メカニズムの解明は喫緊の課題の一つです。私たちの研究では、自閉症を引き起こす事が既に報告されている自閉症関連遺伝子の一つであるShank3遺伝子に注目し、脳内のどのような神経回路がどのように変容することで自閉症病態を引き起こすのかを明らかにしました。
概日時計による空腹代謝の調節
木内 謙一郎(慶應義塾大学医学部バクスター包括的 腎代替療法展開医学寄附講座・特任助教)
体内時計は昼夜の明暗の変化に予測して適応する分子であり、光や食事で時刻合わせをします。本研究では、体内時計がどのように空腹に対する応答を調節することで、臓器間の代謝協調性に寄与するのかを研究目的としています。これまでの検討で、肝臓や筋肉の絶食に対する応答は体内時計で調節されていることが明らかになっています。今後詳細な分子機序を検討することで、空腹によって分泌されるホルモンの効果が、ホルモン分泌の日内変動に加えて、効き目にも日内変化が存在し、それが体内時計によって調節されている可能性を明らかにしていきたいと考えています。
肥満に伴う細胞老化がベージュ脂肪前駆細胞の転写調節及び分化に及ぼす影響
池田 賢司(東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子内分泌代謝学分野・講師)
熱産生脂肪組織であるベージュ脂肪組織は、エネルギー消費量を増やし抗糖尿病、抗肥満作用を示すことから肥満症や2型糖尿病への治療開発が期待されています。ベージュ脂肪組織は、長期の寒冷暴露や運動などの刺激によって誘導されることが特徴です。ベージュ脂肪細胞は肥満や老化に伴い、その誘導が低下することが知られておりますが、その仕組みはこれまで明らかになっておりません。ベージュ脂肪細胞は脂肪前駆細胞から分化することが知られておりますが、その詳細は未だ不明な点が多いです。最近になってベージュ脂肪細胞、前駆細胞には様々なサブタイプが存在することがわかってきました。本研究では、ベージュ脂肪細胞の誘導機構を一細胞毎に調べることで、その仕組みを明らかにし、加齢や肥満状態でもエネルギー消費量を亢進する肥満症・2型糖尿病に対する新しい治療法開発に繋げることを目指します。
ミトコンドリア生合成の基盤となるミトコンドリア―核間ネットワークの解明
星野 温(京都府立医科大学循環器内科・助教)
ミトコンドリアは細胞のエネルギー産生の中心であるとともに酸化ストレスや慢性炎症、細胞死の制御に関連しておりその機能は細胞の恒常性維持に非常に重要です。不良ミトコンドリアはオートファジーによる分解され、新たなミトコンドリアが合成されますが、それらがどのようにして協調的に制御されているかはよく分かっていません。本研究では多面的オミクス解析でRREB1という転写因子がミトコンドリア分解後の生合成に重要であることが分かりました。今後さらにミトコンドリアとRREB1をつなぐ因子の同定に取り組んでいきます。
医薬品開発を志向する面性不斉アミノメタロセニルカルベン配位子の開発
吉田 和弘(千葉大学大学院理学研究院 化学研究部門・准教授)
中心不斉や軸不斉を持つことにより、その鏡像と重ね合わすことのできない化合物は鏡像異性体と呼ばれています。鏡像異性体は互いにその生物活性を異にするた め、これらを区別して合成することは医薬化学及び有機合成化学における重要課題となっています。本研究は、このような鏡像異性体を作り分ける技術の中で、最も理想的とされている「触媒的不斉合成(微量の不斉源より大量の光学活性化合物の合成を可能とする技術)」分野における研究です。将来の産業に役立つ、力量ある触媒の開発を目指しています。
マイクロRNAが制御するウイルス感染細胞の遺伝子発現ネットワークと細胞死誘導機構の解明
高橋 朋子(埼玉大学理工学研究科・助教)
ウイルスが細胞に感染すると、生体を防御するための免疫応答が誘導されます。我々は、細胞内ウイルスセンサータンパク質のひとつであるとされながらも機能が不明であった「LGP2」がRNAサイレンシングの促進因子である「TRBP」と相互作用することで、TRBPが結合する特定のマイクロRNAの成熟過程を阻害し、ウイルス感染細胞の細胞死を促進することを明らかにしました。
LGP2とTRBPによるマイクロRNAを介した細胞死の制御は、ウイルス感染細胞における新しい生体防御機構として機能していると考えられ、抗ウイルス治療や核酸医薬開発への応用が期待されます。前頭前野-視床室傍核回路の幼少期社会経験による発達
山室 和彦(奈良県立医科大学 精神医学講座・助教)
オキシトシンが社会行動に関わることが知られているが、その機序はいまだに不明のままである。私達は前頭全皮質-視床室傍核の神経回路が者かい行動に関わることを報告した。その視床室傍核にはオキシトシン受容体が発現している神経細胞が豊富にあることが知られており、今回は視床室傍核のオキシトシン受容体が発現している神経細胞が社会行動に関わることを明らかにした。今後はさまざまな精神疾患に関わる社会行動への薬物治療への応用が期待される。
記憶B前駆細胞の同定による記憶B細胞産生機構の解明
井上 毅(大阪大学免疫学フロンティア研究センター 分化制御研究室・特任准教授(常勤))
免疫記憶応答はワクチン療法の根幹となる免疫反応であり、記憶B細胞の産生、活性化原理の解明は、インフルエンザ・新型コロナウイルスなどに対する効果的なワクチン開発において重要な課題である。我々は様々なマウスモデルを駆使して記憶B細胞の分化メカニズムの解明に注力し、エネルギー代謝や生存シグナルの獲得など記憶B細胞への分化運命決定に必要な様々な細胞特性を明らかにしてきた。このような基礎研究による知見の蓄積が新規ワクチン開発戦略に貢献できれば幸いである。
ロジウム触媒による動的速度論的光学分割を伴う不斉ヒドロアシル化反応
大西 英博(北海道大学大学院薬学研究院・准教授)
ロジウム触媒を用いた分子間ヒドロアシル化反応は、アルデヒドとアルキンから不飽和ケトンを合成する効率的な手法です。しかしながら、この方法を利用して光学活性な不飽和ケトンを合成した報告はわずか一例しかありません。そこで、本研究では、動的速度論的光学分割を利用して、この反応を不斉合成へと応用すべく検討しました。その結果、フェノールを添加剤として用いると、ラセミ体のアルデヒドとアルキンから良好な収率及び中程度の不斉収率で不飽和ケトンが得られることがわかりました。不斉収率は未だ満足するものではありませんが、フェノールのような弱酸性の物質を添加すると、ヒドロアシル化反応に大きく影響を与えるという現象を初めて見出しました。
メモリー様2型自然リンパ球の分化制御機構の解析
海老原 敬(秋田大学 大学院医学系研究科 微生物学講座・教授)
アレルギー炎症は増悪していく疾患傾向を持ちますが、その原因については未だ分かっていないことが多いです。私達は、免疫細胞の中でアレルギー炎症の記憶を持ち、アレルギー疾患の増悪に寄与する2型自然リンパ球(ILC2)の研究を行いました。ILC2は炎症を経験した後、多様な細胞集団へと変化しますが、炎症の後も生き残り炎症の記憶を持つようになる細胞集団と死にゆく運命の細胞集団の区分は明らかになっていませんでした。私達は、Tigitという抑制性受容体を発現したILC2は活性化により常に死んでいく運命にあることを明らかにしました。
生体内免疫応答と修復機構の統合的解析による尿路結石溶解療法の開発
安井 孝周(名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野・教授)
尿路結石の再発率は5年で50%と高いが、予防法は確立していない。尿路結石の形成機序は、結石内に90数%含まれる無機成分からのアプローチが主体であった。私たちは結石内にわずか数%しか含まれていない有機物質(マトリックス)が結石形成に重要な作用をしていると考え、細胞傷害を介し、マトリックスの発現を介して尿路結石が形成される分子機構を解明した。尿路結石モデルマウスでの腎結石が自然消失する」という現象を捉え、この現象に着目し、治療法開発にむけた尿細管上皮細胞・Mφ・脂肪細胞らの免疫応答と細胞間ネットワークの機序解明を行った。
心臓隔壁欠損モデルを用いた先天性心疾患機構の解明
松花 沙織(神戸大学大学院理学研究科生物学専攻・助教)
心臓は生命維持に必須な器官です。心臓流出路は、初めは総動脈幹という一本の管ですが、次第に内部に隔壁ができ、大動脈と肺動脈の2本に分離します。この隔壁は心臓神経堤細胞によって形成されています。心臓神経堤細胞の欠損・発生異常は総動脈幹が分離しない総動脈幹遺残症(PTA)を引き起こします。心臓神経堤細胞の重要性は明らかであるにも関わらず、心臓神経堤細胞形成に関わる遺伝子制御機構についてはほとんどわかっていません。これまでの私の研究で、心臓神経堤細胞で特異的に発現するMafB遺伝子が心臓神経堤細胞の初期発生に必須であることを明らかにしました。ニワトリ胚内でMafBの機能を欠失させることで、心臓神経堤細胞由来の隔壁を失った総動脈幹遺残症 (PTA)モデルニワトリ胚を作り出し、それを利用して心臓隔壁欠損を引き起こす分子機序の解明を目指しています。
老化個性の可視化ツールの開発
平野 恭敬(京都大学大学院医学研究科・特定准教授)
老化は各器官、例えば神経系や心血管系、消化器系、運動器系といった様々な器官の機能障害を引き起こし、高齢者の社会的活動を著しく制限する。老化に伴う機能低下は、各個体で訪れる時期は様々で、また均一にすべての器官で機能低下を示すわけではない。従って老化に伴う器官機能不全に立ち向かうためには、特定の器官で機能低下を示した個体を識別した上で、解析し、さらには機能低下を改善させる方法論を見出していかなければならない。そこで私は、個体間の老化プロセスの違い「老化個性」に焦点を当て、それを可視化する方法論の確立が必要不可欠であると考え、老化個性を可視化する本研究を行った。
脳内インビボイメージングシステムによるCentral Nervous System Lupus病態解明への挑戦
宮部 斉重(日本医科大学先端医学研究所 細胞生物学部門・講師)
近年、サイトカイン阻害を目的とした生物学的製剤が続々と開発され、効果的に活性化免疫細胞を抑制可能となり、自己免疫疾患の予後は劇的に改善しました。一方で、これらは全身性に免疫細胞の“活性化”を阻害する為、重篤な感染症や二次発癌などの副作用が問題となっています。生命現象の根底にある細胞の“動き”は炎症病態の根底にあり、その機序を解明する事で細胞の“動き”を臓器特異的に制御可能な次世代免疫療法の開発につながると期待されます。
もやもや病の分子病態解明
森戸 大介(昭和大学医学部・講師)
もやもや病は東アジア地域の子どもに多い脳血管疾患です。脳の真下のあたりの動脈が狭くなり、血が通りにくくなります。その結果、脳への血液供給が不足し、脳梗塞などが起こります。なぜ動脈が狭くなるのか、なぜこの箇所で起こるのかなど、ほとんど謎のままです。私たちはもやもや病の原因遺伝子と考えられる新たな遺伝子ミステリンを物質として取り出すことに成功しました(分子クローニング、2011)。以来、解析を進め、この遺伝子から合成されてくるタンパク質ミステリンの分子としてのはたらきや、体の中での機能、またもやもや病患者さんから見つかった遺伝子変異により機能がどのように変化するかを順番に明らかにしてきました。まだ研究の途上ですが、もやもや病発病メカニズムのヒントをつかみつつあります。本財団や公的組織をふくむ各方面からの支援を受けながら、近い将来の病態解明を目指して研究を続けています。
網膜オルガノイド形成におけるアクチン細胞骨格の動的ゆらぎ特性とその役割の解明
奥田 覚(金沢大学ナノ生命科学研究所・准教授(Jr.PI))
上皮組織では,多数の細胞が密に並んだシート状の組織であり,シート内の各細胞は,脳の初期発生等の過程に置いて多層化したり脱離したりします。この細胞脱離の仕組みの理解は,胚発生・組織再生・がん疾患などの幅広い現象の解明にとって重要な課題です。本研究では,上皮組織のシート構造を簡単化して捉え,力学エネルギーに基づいた理論的な解析を行うことにより,上皮組織に内在する力学的な不安定性が細胞脱離を引き起こす仕組みを明らかにしました。
化学療法抵抗性を示す静止期癌細胞形成システムの解明
二村 圭祐(大阪大学大学院 医学系研究科・遺伝子治療学・准教授)
がん治療上の問題点の1つとして、がん細胞が抗がん剤の抵抗性を獲得することがあげられます。抗がん剤の多くは細胞増殖が盛んな細胞に対して効果を示します。がんの中には細胞増殖が極めて遅いがん細胞が存在すると考えられており、このような細胞増殖の遅いがん細胞には抗がん剤は効きにくいと考えられます。ところが、このようながん細胞がどのような性質を持つのかあまりはっきりしていません。私達は、細胞増殖の遅いがん細胞の性質を明らかにして、この細胞を除去する治療法の開発を進めています。
TGF経路依存性浸潤型スキルス胃癌の機序解析と治療応用
早河 翼(東京大学医学部附属病院消化器内科・助教)
本研究では、予後不良の癌であるスキルス胃癌の新規治療標的を、独自のマウスモデルを用いて同定した。樹立したスキルス胃癌マウスサンプルの網羅的遺伝子発現解析によって、この癌で特徴的に発現上昇する遺伝子としてLRG1とCD38を同定した。これらの分子は腫瘍内の血管新生や線維化に重要であり、特異的抗体によるマウスモデルの治療によって、スキルス胃癌の進展を抑制することが可能であった。LRG1・CD38標的治療は、腫瘍間質相互作用を阻害することでスキルス胃癌の治療に有用であると考えられる。
免疫受容体による糖鎖認識を介した破骨細胞分化修飾能の分子基盤
有吉 渉(九州歯科大学感染分子生物学分野・教授)
真菌や細菌、海藻などが含有する糖鎖であるβ-glucanは、免疫系細胞が持つ受容体であるdectin-1に認識されることで、種々の生物学的機能を発揮します。私達はβ-glucanが、破骨細胞前駆細胞上のdectin-1に結合し、破骨細胞への分化や骨吸収活性を低下させることを証明しました。そこで本申請では、β-glucanの破骨細胞の分化抑制メカニズムに着目し、破骨細胞分化に重要な分子に対する負の調節機能を発揮することを見出しました。β-glucanの創薬への応用が、骨粗鬆症や歯周病などに対して、破骨細胞の骨吸収活性の低下を介した効果的な治療法の提案へと繋がると考えており、今後も研究を続けて参ります。
ショウジョウバエの加重共発現遺伝子ネットワークの構築
関谷 倫子(国立長寿医療研究センターアルツハイマー病研究部 発症機序解析研究室・室長)
キイロショウジョウバエは有用な遺伝学モデルとして使用されていますが,最近では神経変性疾患をはじめとした様々なヒト病態モデルが開発され,疾患研究,創薬分野においても多用されています。一方,生体内(特に脳内)での変化を包括的に捉え,疾患の発症機序解明,治療薬標的の同定へとつなげる1つのアプローチとして,遺伝子ネットワーク解析が有用であることが分かってきました。疾患研究において,さまざまなモデル動物と遺伝子ネットワーク解析を用いることで,疾患・創薬研究は飛躍的に進むことが予想されます。遺伝子ネットワークレベルでのショウジョウバエとヒトとの類似性と違いを解析し理解することで,疾患研究におけるショウジョウバエの有用性も高まると考えられます。
環境刺激による植物のシュート再生促進メカニズムの解明
松永 幸大(東京理科大学理工学部応用生物科学科 松永研究室・教授)
植物が環境刺激を受けることで器官再生が促進するメカニズムを明らかにすることができた。ヒトや動物とは異なり脳や神経系を持たない植物が、外部環境の変動を捉えて、器官再生にどのように結びつけているのかを分子的メカニズムの一端がわかった。今後、このメカニズムを利用して、植物の再生促進法の開発が可能になることが期待される。
IL-27による疼痛制御機構の解析
吉田 裕樹(佐賀大学医学部分子生命科学講座・教授)
インターロイキン27(IL-27)は、免疫抑制作用を持つサイトカインとして、自己免疫疾患や感染時の過剰な炎症(サイトカインストームなど)に対する治療応用に関する研究が進んでいます。今回、IL-27による全く新しい痛み知覚制御作用を発見し、現在その詳細を解析しています。これは、モルヒネや消炎鎮痛剤とは異なる作用によるものであり、新しい疼痛の治療法の開発につながることが期待されます。
社会性行動に関連する分子・神経機構の解明
古市 貞一(東京理科大学理工学部応用生物科学科・教授)
自閉スペクトラム症(ASD)は,社会的コミュニケーションの欠損と常同行動・興味の限局を特徴とし世界各国で高い有病率を示します。原因が不明で完治療法がないため,病因究明や治療法の確立が課題となっています。遺伝要因が強い多因子疾患と考えられていますが,ヒト脳での遺伝子解析には限界があります。本研究では,高社会性を示すB6マウスと比較して,BTBR/Rマウスの社会性が低下していること,両マウスの脳内の遺伝子発現(トランスクリプトーム)の比較解析とバイオインフォマティクス解析によりASDの遺伝因に示唆的な情報を示すことができました。今後, BTBR/RマウスがASD関連の研究開発に寄与する有用な動物モデルとなると期待されます。
硫化水素で活性化される近赤外色素プローブの開発:バイオイメージングと医療への応用
石垣 侑祐(北海道大学大学院理学研究院化学部門 有機化学第一研究室・助教)
電気化学的な刺激によって色調が変化するエレクトロクロミック材料(EM)は様々な応用の観点で注目を集めています。目に見える波長(約400-780 nm)よりもエネルギーの弱い近赤外光(約780-2500 nm)を吸収するEMは、バイオイメージングなどへ応用できますが、重金属が入っていない有機分子で作ることは容易でないため、報告例が限られていました。そこで本研究では、近赤外光を吸収する新たな有機EMを設計・合成しました。電気化学的な刺激によって生じる近赤外色素では、1400 nmに及ぶ光を吸収するため、バイオイメージングと医療への応用が期待されます。
腫瘍間質由来エクソソームによる胃がん治療抵抗性機構の解明
石本 崇胤(熊本大学病院消化器癌先端治療開発学・特任准教授)
胃がんに対して抗がん剤治療が効きにくくなる「治療抵抗性」に関わる因子として、CAFsが分泌する細胞外小胞 (EVs)中のアネキシンA6が胃がん細胞に取り込まれることで、抗がん剤の効果が低下することが分かりました。アネキシンA6タンパク質やEVsを分泌するCAFsをターゲットにした新たな癌治療法の可能性を見出しました。
蛋白質工学によって解明するアミロイド凝集の異常安定化
真壁 幸樹(山形大学大学院理工学研究科真壁研究室・准教授)
この研究ではアルツハイマー病などの病変部位で見つかる、蛋白質凝集体の性質を明らかにするために、病変蛋白質そのものではなくて、別の扱いやすい蛋白質に凝集体の構造を移植して評価を行いました。特に、βシートと呼ばれる蛋白質の分子構造が集まって、病気の凝集体になるところをモデル系によって、詳細な構造で評価しました。詳細な構造から、そのようなβシートは単独でも安定に構造ができていることがわかりました。これは病気を引き起こす凝集が非常に安定なことと関連があるかもしれません。
シロイヌナズナの表皮細胞分化を制御する脂質種の同定
阿部 光知(東京大学大学院総合文化研究科・准教授)
陸上植物は、乾燥をはじめとする環境ストレスや病害を引き起こす有害な生物に囲まれて生きています。そこで、植物は特殊化した細胞(表皮細胞)を外部環境との境界に発達させ、自らを保護しているのです。本研究によって、外部環境との境界、すなわち「位置」を認識し、正しい場所に表皮細胞を分化させる際に、特殊な脂質が重要なはたらきをしていることがわかりました。今後、地球環境の劇的な変化が予想されることから、過酷な環境でも丈夫に生育可能な植物の作出につながると期待しています。
成果報告によせて - 2018年度受賞者から
-
(受付順、敬称略)
GATA3転写複合体解析を基盤とした生活習慣病における2型ILC2細胞の新たな機能的役割
田中 知明(千葉大学大学院医学研究院・教授)
転写因子GATA3という分子は、免疫細胞であるT細胞の生存や炎症性サイトカイン産生を司る役割が詳細に研究されてきた分子である。一方で、2型自然リンパ球という免疫細胞が糖代謝を改善させる作用にも、GATA3の多面的な役割が新たに見出されている。本研究では、肝臓にいる2型自然リンパ球が、肥満や糖尿病などの代謝疾患病態に良い影響を及ぼすことを明らかにした。今後、これらの詳細な分子メカニズムを明らかにすることで、肥満や糖尿病のインスリン抵抗性に対する新たな治療標的となることが期待される。
植物の生長を司る葉緑体局在変化の新たな制御機構の解明
後藤 栄治(九州大学 大学院農学研究院・助教)
光合成の場である葉緑体は、光の強度に応じて細胞内の空間配置を変化させます。この光に依存した葉緑体の局在変化は、植物特有の青色光受容体フォトトロピンによって制御されます。フォトトロピンは、細胞膜に加えて葉緑体の周りにも存在することが知られていますが、葉緑体の周りにあるフォトトロピンの機能については分かっていません。そこで私たちは、遺伝子工学技術を利用して、葉緑体のまわりにのみフォトトロピンが存在する植物体を作出し、葉緑体のまわりに存在するフォトトロピンが葉緑体の局在変化を誘導することを明らかにしました。
機械学習と次世代シーケンス技術を用いた、同種造血幹細胞移植後の腸内細菌叢と、腸管GVHD発症リスクとの関連解析
新井 康之(京都大学医学部附属病院 血液内科・医員)
近年、「腸内細菌叢」の乱れが様々な疾患や健康状態に関係していることが分かってきました。白血病やリンパ腫といった、血液疾患に対しても同様のことが言えるのではないか、またそのことが治療にヒントを与えるのではないかと考え、この研究を行っています。将来的には本研究から発展した薬作りに役立てたいと考えています。
粘膜組織における組織局在型メモリー T 細胞の重要性
飯島 則文(医薬基盤・健康・栄養研究所・サブプロジェクトリーダー)
様々なウイルスを含む病原体は、多くの粘膜組織より侵入することにより我々の身体機能に重篤な症状を引き起こすことが知られている。これまでワクチンなどの予防を目的とした治療方法が全く効果がないウイルス等に対しては、粘膜などの感染部位で長期間、その機能が維持される組織局在型メモリー T 細胞 (tissue resident memory T cells; TRM) を標的とした治療方法が重要な役割を果たすと考えられる。TRM は、侵入した病原体を感染した粘膜部位で速やかに除去することができるため、重篤な症状を引き起こす前に生体を防御することが可能である。今後、TRM を標的とした新規治療方法の確立がこれまでにワクチンが確立していない病原体に対しては重要な役割を果たすと確信している。
胎生期心室筋形成における転写制御機構と細胞系譜の解析
渡邉 裕介(国立研究開発法人、国立循環器病研究センター、分子生理部・室長)
ヒト新生児の100人に1人が先天性心疾患を発症しており、心臓が正常に形態形成される過程を解明することは、それら疾患発症機構の理解や治療に繋がります。本研究では、心室筋で発現し、その形成に必須であるHey2因子がどのような遺伝子発現制御を受けているかを解析しました。その結果、Tbx20とGataといった転写因子がHey2遺伝子の発現に必須であることを明らかにしました。本研究は、心室筋形成における分子機構の1つを解明するものであり、ヒトの心臓形成を理解する上で重要な知見となりました。
複雑系脳オルガノイドによるヒト脳発生の解明と中枢神経疾患への応用
六車 恵子(関西医科大学 医学部 iPS・幹細胞応用医学講座・教授)
ヒトiPS細胞と自己組織的な分化培養技術を融合させることにより、脳に類似した構造体(脳オルガノイド)を繰り返し何度でも作製できるようになりました。この技術は、ヒト脳の発生や組織構造の形成、神経細胞の機能に関する研究を培養皿の中で行うことを可能にしました。本研究分野の発展は目覚ましく、病態のモデル化による発症機序の解明が進められ、新規治療法の開発や創薬開発に結びつくことが期待されています。
代謝シグナル複合体 mTORC1 の新規制御メカニズムの研究
渋谷 周作(山口大学共同獣医学部獣医衛生学分野・テニュアトラック助教)
細胞は周りにアミノ酸が豊富なときにはタンパク質を合成し、逆にアミノ酸が足りないときには自身のタンパク質を壊してアミノ酸を作って飢餓に備えようとします。このように栄養の豊富さに対応するための仕組みは、生物が活動するために必要不可欠なものですが、その詳細はいまだ不明な点が多く残されています。栄養素への細胞応答を解明することは、生物学的に重要なだけでなく、肥満や生活習慣病などの過栄養を原因とする問題に対する取り組みとしても重要であると考えています。
心筋タイプ別誘導法を用いたin vitro機能性心臓組織の構築
竹内 純(東京医科歯科大学・准教授)
本研究は、ヒト・マウス間で保存され、かつ、1)心室筋―心房筋の発生運命決定に関わる、2)線維芽細胞から直接心室筋―心房筋への運命転換に関わる共通因子を見出すことを目的としている。本研究期間内に3段階のバイオインフォマティクス解析を経て、各々の細胞運命を決定する共通因子を選出することができた。また、複数遺伝子同時破壊マウスの作成にも成功したことで、マウス発生工学技術開発の発展も見込まれる。本研究結果は、今後、心房筋および心室筋別々の条件下で心筋性質の理解・心筋移植および創薬スクリーニングなどの研究発展に貢献すると期待されることから、今年度中に論文投稿・採択を目指す。
テトラヒドロフラン環の構築法を革新するα-ケトエステルの不斉環化付加反応の開発
坂倉 彰(岡山大学大学院自然科学研究科応用化学専攻・教授)
テトラフラン環,すなわち酸素原子を一つ含む五員環構造,は,ポリエーテルイオノフォアやマクロライドなど,様々な生物活性物質に含まれる重要な構造である。テトラフラン環構造をもつ新規医薬品を開発するためには,テトラヒドロフラン環を立体選択的に化学合成する必要がある。本研究では,テトラヒドロフラン環を合成するための新しい方法を開発することを目的として,シリルメチルシクロプロパン化合物とα-ケトエステルとの環化反応の検討を行った。その結果,目的とするテトラヒドロフラン環を合成するには至っていないが,その過程で,1,2-付加生成物やジヒドロピラン化合物を立体選択的に合成できるという新しい知見を得ることができた。
急性腎障害において炎症の遷延化をもたらす新規微小環境の病態生理的意義の解明
菅波 孝祥(名古屋大学環境医学研究所分子代謝医学分野・教授)
近年、様々な慢性疾患に共通の病態基盤として「慢性炎症」が注目されている。そのメカニズムの1つとして、死細胞が発するメッセージを炎症細胞が受容・応答することが概念的に理解されているが、実際の病態における分子実態は不明の点が多い。我々は、急性腎障害モデルを用いて、新規死細胞センサーのMincleが、壊死尿細管を感知して炎症慢性化に働くことを見出した。Mincleは、壊死尿細管の周囲に集積するマクロファージに限局して発現し、β-グルコシルセラミドとコレステロールを認識してマクロファージの炎症性サイトカイン産生を促進するとともに、死細胞貪食を抑制すると考えられた。
神経活動依存的発現を示す新しい脂質修飾酵素による神経・認知機能調節機構
奥野 浩行(鹿児島大学大学院医歯学総合研究科生化学・分子生物学・教授)
我々の認知機能は大脳神経細胞の活動によって担われています。神経細胞が活動すると多数の遺伝子の発現量が変化しますが、その役割は多くが不明です。本研究ではその一つ、zdhhc18という遺伝子に注目しました。未知であるzdhhc18の機能を知るため、ゲノム編集技術を応用した発生工学手法を用いてzdhhc18を欠損したマウスを作出することに成功しました。今後はこのマウスの大脳や神経細胞の機能・形態異常の有無を調べます。本研究は認知症や精神疾患の治療薬や治療法の開発につながることが期待されます。
酸化的官能基化を基盤とするフィトクロム型発色団の合成と機能解明
宇梶 裕(金沢大学理工研究域物質化学系・教授)
“植物の眼”ともいえる光受容色素タンパク質フィトクロムは,赤色領域の光吸収による立体構造変換により,植物の発芽や生長等の機能制御を行っている。しかし,発色団の立体構造と機能の関係解明はほとんど進んでいなかった。本研究では,「フィトクロム型発色団の化学合成」という独自のアプローチで解明に挑んだ。特にピロール化合物の酸化的官能基化という手法を基盤とした合成を通して,光無しでも発芽機能を発揮すると期待できる立体固定型発色団の基本骨格の合成に成功した。今後,合成した化合物をフィトクロム関連色素タンパク質へ取込みにより,光情報伝達機能解明と光無しでも発芽可能なシステム開発への発展が期待される。
新規塩基編集ツールの開発
谷内江 望(東京大学先端科学技術研究センター谷内江研究室・准教授)
近年、細胞内ゲノムDNA中の特定の狙った配列を自在に編集することができるゲノム編集技術が急速に発展しており、農業、医療分野を含めた生物学分野全体に大きな変革をもたらしつつあります。これまでに、CRISPR-Cas9というゲノム編集ツールや、DNA配列を編集する塩基編集ツールが開発されてきました。これらは精密なゲノム編集技術として注目を集める一方、ゲノムに書き込まれた生命プログラムを編集するという点においては、その自由度が限られていました。本研究では狙ったDNA配列のC→Tおよび A→Gの異種塩基置換を同時に達成できる新たな塩基編集ツール「Target-ACEmax」の開発に成功しました。本新規ゲノム編集ツールは、様々な細胞においてより多様な塩基編集を可能にし、品種改良、遺伝子治療、動物の発生における細胞系譜の追跡など、様々な分野において幅広い応用が期待されます。
細胞内一酸化炭素によって調節されるサーカディアンリズム機構の解明
北岸 宏亮(同志社大学理工学部機能分子・生命化学科・准教授)
本研究では,すべての生物が持つ体内時計システムにおいて,有毒ガスとして知られる一酸化炭素が生体内において役立つ機能を持つことを実験的に証明した。一酸化炭素は生体内において常に微量ずつ合成されており,何らかの生理機能を持つことが提唱されてきたが,その機能の全容は未解明であった。今回,我々は生体内において合成された一酸化炭素を選択的に除去するオリジナルの試薬hemoCD1をつかって,動物体内の一酸化炭素を除去したときに起きる体内時計システムの変化について検討を行ったところ,体内時計の制御システムが大きく乱されることを明らかとした。生体内一酸化炭素の新たな生理機能の側面を明らかにした世界で初めての成果が得られた。
加齢に伴う皮膚内分泌環境恒常性維持機構の破綻により生じる老人性脱毛症の分子機構解明
原口 省吾(昭和大学医学部生化学講座・助教)
年齢が進むにつれて精巣や卵巣などの性腺機能が低下し、性ホルモンの血中濃度は減少します。男性ホルモン・女性ホルモンと言われることで、男性には男性ホルモンしかなく、女性には女性ホルモンのみと誤解されている場合も多いですが、Fig. 1に示しているように、そもそも男性ホルモン・テストステロンは女性ホルモン・エストラジオールを合成する材料にもなり、男女ともに男性ホルモン・女性ホルモンを体内で合成しています。本研究では、60歳以降で見られるびまん性(頭部全体に広がる)の脱毛の発症の一因に、性腺機能低下が引き金となって皮膚局所に存在する性ホルモン合成系が乱されてしまう点にあることを解明しました。
RNA情報発現系の破綻による脳神経疾患の分子病態解明
飯島 崇利(東海大学創造科学技術研究機構医学部門・准教授)
自閉症をはじめとした脳発達障害や精神疾患などではRNAスプライシングの異常が見つかっていますが、これらの病気の発症や病態との因果関係はまだはっきりとしていません。本研究では神経系における時空間的なRNAスプライシング機構の解明をメインに研究を行い、SAM68と呼ばれる神経系スプライシング因子をノックアウトした動物では、IL1RAPと呼ばれる神経分子のスプライシング異常を起因とした神経障害が現れることが示されました。今後このようなスプライシング異常の解明が脳の病気の理解の鍵に繋がることが大いに期待できます。
オートファジーによる核膜孔複合体の分解の分子基盤と生理的意義の解明
中戸川 仁(東京工業大学 生命理工学院・准教授)
オートファジーは、2016年のノーベル賞の受賞対象となった生命現象ですが、その分子機構及び生理機能にはまだ多くの謎が残されています。また、近年、神経疾患などの病気との直接的関連から、細胞内の特定の成分のオートファジーによる選択的分解が特に注目を集めています。本研究では、モデル生物である出芽酵母を用いて、核膜孔複合体という巨大なタンパク質複合体がオートファジーで選択的に分解されることを明らかにしました。本研究によって得られた成果は、ヒトを含めた他の生物における研究の端緒となり、核膜孔複合体が関与する疾患や老化への対処療法を開発するための基盤情報となることが期待されます。
B型肝炎ウイルスの再活性化・再燃に伴う細胞内自然免疫応答の包括的理解
阿部 隆之(神戸大学大学院 医学研究科 感染制御学分野・准教授)
C型肝炎ウイルス(HCV)に対する直接作用型の抗ウイルス剤(Direct Acting Antivirals: DAAs)の開発により、HCVの治療成績の飛躍的向上が期待されている。しかしながら、近年、DAA製剤の投与によるHCVの治療後に、B型肝炎ウイルス(HBV)の再活性化及び再燃に伴う劇症肝炎の死亡例が報告されているが、その詳細な分子機序は明らかとされていない。この事例は、インターフェロンフリーの治療指針が主流となっている現況においては、解決すべき喫緊の課題である。これまでのHCV培養系の確立や、近年のHBV感染受容体の同定に伴い、HCV及びHBVの個々の感染生活環の概要が明らかにされつつあるが、HCV/HBV重複感染モデルにおける知見は乏しい研究背景にある。本研究の成果は、肝炎ウイルスの感染生活環を支持する主要な宿主因子及び様々な肝細胞培養系を組み合わせることで、汎用性の高い新たなHCV/HBV共培養系を確立できたことにある。今後、この実験系を用いることで、HBVの再活性化及び再燃に伴う劇症肝炎の分子機序の解明に役立つことが期待される。
植物細胞壁ペクチンの生合成に関わる糖転移酵素の同定
石水 毅(立命館大学生命科学部生物工学科バイオエネルギー研究室・准教授)
植物細胞がもつ細胞壁は、植物の成長、外敵からの防御、植物のしなやかさを生み出すことなどに関わっていると考えられていますが、研究が進んでいません。私は、この助成金により、植物細胞壁を作る酵素を検出する方法を確立しました。この方法を用いて、植物細胞壁を作る酵素遺伝子を発見することができるようになります。これらの遺伝子が発見されると、植物細胞壁の役割や機能を解明したり、食糧エネルギー資源になる植物の生産に応用したりすることができるようになります。
生殖幹細胞の維持と分化を制御するRNA修飾とプロセシングの解明
甲斐 歳恵(大阪大学大学院生命機能研究科生殖生物学研究室・教授)
ゲノムDNAの配列に変化を起こさず、DNAやRNAの修飾によって、遺伝子発現を変化させる「エピジェネティック制御」は、発生や分化、あるいは環境応答などで重要な役割を担っている。その中でも、アデノシンのメチル化などのRNA塩基修飾が注目を集めている。本研究では、最近実用化されているRNA解析技術を用いて、生殖幹細胞由来mRNAの塩基修飾部位を解析し、生殖幹細胞の特異的なエピジェネティック制御機構を明らかにする。
血管内腔圧による血管新生の新たな制御機構の解明
福原 茂朋(日本医科大学 先端医学研究所 分子細胞構造学分野・教授)
生体組織が傷害を受けると、それを修復するため血管新生により新たな血管網が作られます。今回、私たちはゼブラフィッシュを用いた蛍光イメージングにより、創傷治癒における血管新生を生きた個体で観察し、損傷血管が修復する際、血流に対して下流の損傷血管は伸長するのに対し、上流損傷血管は血流に起因する内腔圧により伸長しないことを発見しました。そのメカニズムとして、内腔圧は上流損傷血管を拡張し、内皮細胞に伸展刺激を負荷することで、内皮細胞の運動を抑え、血管伸長を阻害していることを明らかにしました。本研究により、組織修復における血管新生の新たな制御機構が明らかになり、創傷治癒を促進させるための治療法の開発につながる可能性があります。
肝星細胞分泌WntリガンドACLPに着目した、肥満関連肝がんの新たな治療法の開発
冨田 謙吾(防衛医科大学校消化器内科学教室・准教授)
肥満にともなう肝がん患者は急増しており、病態機序の解明と治療法の開発は緊急課題である。私たちは、ACLP (Aortic carboxypeptidase-like protein) が肝星細胞特異的に産生される分泌性糖タンパク質であり、肥満により産生が増強される新規のWnt リガンドであることを見いだした。本研究では肝星細胞由来のACLP という見地から、肥満関連肝がん発症・進展の病態機序を解明し、新たな治療法を確立することを目的とした。肥満関連マウス肝がんモデルを作成したところ、肝星細胞特異的ACLP欠損マウスでは、有意に肝がん発症が抑制されており、ACLPが肥満関連肝がんの有望な治療標的であることが明らかとなった。
超高感度発光イメージングTgマウスの構築
近藤 科江(東京工業大学・教授)
がんの新たな治療戦略として、がん細胞の周囲に存在する間質細胞を標的にする方法が注目されています。間質細胞は、がん細胞の増殖を助け、転移を促進する悪性化の過程に大きな役割を果たしていることが、最近の研究から明らかになってきました。本研究では、我々が開発した超高感度生体発光イメージング系を用いて、悪性化に関与する間質細胞を腫瘍の成長過程を通して体の外から観察することで、悪性化機構の解明に有用な情報収集を試みました。生体レベルでの観察を基に、今後、腫瘍内の時間空間的な解析を進めることで、新たな診断マーカーや治療法の開発に繋がると期待されます。
オープンクロマチン領域解析によるB細胞特異的エンハンサーの同定とその制御機構の解明
藥師寺 那由他(東京理科大学生命医科学研究所免疫生物学研究部門伊川研究室・助教)
がん免疫治療法への利用が期待されるナチュラルキラーT(NKT)細胞は、生体内にはわずかしか存在せず、試験管内で治療に必要な細胞数まで増殖させることは非常に難しい。我々はヒトNKT細胞由来iPS細胞を再度NKT細胞へと分化・増殖させることで、この問題に取り組んでいる。今回、我々はヒトiPS細胞からNKT細胞への分化運命を制御するようなDNA領域の探索とその制御機構を明らかにすること目指した。その結果、NKT細胞への分化過程で活性化する約6,800箇所のDNA領域を見出した。今後この領域に対する解析をさらに進めていくことで、最終的には分化誘導期間の短縮と高い誘導効率を兼ね備えた次世代の分化誘導法の確立を目指していく。
内在性レトロウイルスによる細胞外粒子形成の分子機構の解明
三好 啓太(国立遺伝学研究所 系統生物研究センター 無脊椎動物遺伝研究室・助教)
生物は非常に多くの細胞によって構成され、それぞれの細胞は特異的な特徴や性質を持ちます。また、その性質は様々な要因により決定されます。例えば、周りの細胞から放出された微粒子が情報を持ち、受け取った細胞の運命決定を行うことが知られるようになってきました。本研究では、微粒子を介した細胞間の情報のやり取りを分子レベルで明らかにしたいと考えています
植物の体軸形成の分子基盤の解明:オーキシン排出担体PINの局在を制御するPINクラスターの構造とその機能
楢本 悟史(東北大学大学院生命科学研究科植物発生分野・助教)
オーキシンは植物の発生・成長に重要な役割を果たすことから、農学的に重要とされ、除草剤や単為結果誘導剤として利用されてきた。本研究により得られた知見を発展させ、オーキシンの作用機構の理解を深めることは、将来の持続的な社会を実現する上で有用な、新たな農業方策の礎となると期待される。
海馬歯状回の局所回路におけるシナプス可塑性のメカニズムと生理的役割
橋本谷 祐輝(同志社大学 研究開発推進機構・准教授)
海馬は記憶や学習に重要な役割を担う脳領域であると考えられてきました。海馬の神経回路は主に歯状回、CA1,CA3という領域で形成され、その間のシナプス結合がこれまで盛んに研究されてきました。本研究では歯状回門に位置する苔状細胞と呼ばれる興奮性ニューロンに焦点を当て、そのシナプス可塑性の分子メカニズムを調べました。苔状細胞は近年注目されるようになり多くの研究成果が発表されつつあります。今後は海馬の神経回路および記憶への寄与を考えるうえで苔状細胞が重要な位置を占める可能性を秘めており、本研究もその一助になると期待されます。
骨髄異形成症候群患者における造血幹細胞ニッチの遺伝子発現解析
錦井 秀和(筑波大学医学医療系血液内科・准教授)
骨髄に存在する造血幹細胞は造血幹細胞ニッチと呼ばれる微小環境により維持されると考えられているが、骨髄異形成症候群(MDS)や急性骨髄性白血病(AML)における骨髄環境の変化の詳細やその病的意義には不明な点が多い。今回の研究で我々は患者サンプル・マウスモデルを用いて新規多重染色システムを用いた造血幹細胞ニッチの可視化・各ニッチ細胞の遺伝子発現変化の詳細を明らかにし、ニッチ細胞の機能的変化が造血器腫瘍における正常造血障害の一因となっている事を明らかにした。現在この結果をもとに、造血器腫瘍の造血障害に対する治療標的の探索を行っている。
接着制御因子デスモプラキンによる新規うつ治療シグナルの解明
瀬木ー西田 恵里(東京理科大学 基礎工学部 生物工学科 瀬木研究室・准教授)
海馬は学習・記憶に関わる重要な部位です。海馬の歯状回は、神経細胞が層状に並んでおり、お互いに接着する特徴的な構造を持っています。また、この部位では成体でも神経の新生が起きることが知られています。本研究では、歯状回神経に特異的に発現するデスモプラキンという接着構造を制御する因子に着目し、その機能の解析を行いました。私たちは、デスモプラキンの機能意義を調べるために、成体マウスでの海馬歯状回でのデスモプラキン発現を減少させました。その結果、神経の成熟マーカーの発現増大や神経新生の減少が観察され、デスモプラキンが海馬の神経機能調節に重要な役割を持つことが明らかになりました。
上皮癒合に着目したGRHL3 因子の機能解析
木村-吉田 千春(大阪母子医療センター研究所 病因病態部門・主任研究員)
日本人の間で発症頻度が高いことで知られている「口唇口蓋裂」先天異常の実験モデルマウスを作製することを目的に、Grhl3遺伝子欠損マウスの表現型解析を行った。結果、我々が作製したGrhl3遺伝子欠損マウスでは口唇口蓋裂の異常は見られなかったが、口腔内の横口蓋ヒダに一部形成異常やマーカー遺伝子の発現異常が見られた。今後、Grhl3遺伝子と共に働く遺伝子(例えばIRF6遺伝子など)の遺伝子欠損マウスと交配させダブル変異マウスを作製し、口唇口蓋裂の発症の有無を検討する予定である。
カルシウム輸送障害による新規骨石灰化不全症の同定と病態メカニズム解明
鈴木 喜郎(岩手医科大学医学部 生理学講座統合生理学分野・准教授)
私は骨疾患の原因の1つとしてCa2+輸送上皮におけるCa2+輸送機能低下に着目して研究を行った。本研究の結果、体内にCa2+を取り込むTRPV6というイオンチャネルの遺伝子変異によって家族性の骨疾患を発症することが明らかになりつつある。骨疾患は骨の土台となるコラーゲンなどのタンパク質成分の異常だけでなく、石灰化のための材料となるCa2+の体内動態を含めて解析する必要があることがわかった。今後、その分子メカニズムの詳細を明らかにすることによって、TRPV6が骨疾患の治療の際の良いターゲットになることを示していきたい。
核内ノンコーディングRNAの分解制御による自然免疫応答のコントロールに関する研究
秋光 信佳(東京大学アイソトープ総合センター・教授)
Salmonella enterica serovar Typhimurium (Salmonella), a pathogenic bacterium, is a major cause of foodborne diseases worldwide. In this study, we revealed the molecular mechanism of Salmonella genes in the regulation of host gene expression through nuclear RNA degradation
長距離・局所をつなぐ投射特異的な大脳回路構築のメカニズム解明
田川 義晃(鹿児島大学医学部医学科神経筋生理学分野・教授)
この研究は、哺乳類の脳の代表的な神経経路の1つである脳梁神経回路の形成において、発生・発達期に特有の自発神経活動の役割を調べたものです。脳の中には異なった経路に投射する神経細胞が混在していますが、投射先ごとに機能的にまとまり、同期した神経活動をすることで、正しい回路が形成されるメカニズムがあることが明らかになりつつあります。神経回路の形成メカニズムを明らかにし、それを調節する分子を明らかにすることは、神経回路形成・発達に障害が生じる脳疾患のモデル動物作成につながると期待されます。
固形腫瘍におけるATR阻害薬の治療効果予測バイオマーカーの同定
小村 和正(大阪医科大学 泌尿生殖・発達医学講座 泌尿器科学教室・助教)
現在、ゲノム医療の普及促進の一つの大きな課題として、解析後のアウトプットとなる臨床治験を含む治療選択肢の拡充が挙げられると申請者らは考えている。癌治療、研究において特定のKey Moleculeによる多彩な形質変化を明らかにすることは、患者様の発現差異による層別化を可能にし、さらにその変化に伴う治療ターゲットの発見がテーラーメード医療を可能にする。本研究においてもATR inhibitorによる治療効果予測因子であるDNA複製ストレスのバイオマーカーとしてKDM5Dの欠失を明らかにしたことにより、個別化医療Precision Medicineに新たな展開をもたらせるものと期待している。
ペプチドフォルダマー創薬研究
出水 庸介(国立医薬品食品衛生研究所有機化学部・部長)
ペプチド医薬品をはじめとする中分子医薬品は、低分子医薬品と抗体医薬の利点を併せ持つ新たな医薬品として期待されています。私は本研究で、病気に関連する様々な菌に対して有効な抗菌ペプチドの開発を行いました。本研究を通じて、未だに有効な治療方法が見つかっていない病気に対する、新しい治療薬や治療法の開発に貢献します
乳癌における腫瘍内エピゲノム不均一性の解明
丸山 玲緒(公益財団法人がん研究会がん研究所がんエピゲノムプロジェクト・プロジェクトリーダー)
がんは1種類の悪性細胞が大量に増殖した単なる「細胞のかたまり」では決してなく、様々な種類の細胞が協調してひとつの「細胞社会」のようなものを形成していることが分かってきました。この「細胞社会」は患者さん一人一人で異なり、さらには時々刻々と変化しています。がんを克服するためには「がんとは何か?」を知る必要があり、それは腫瘍を構成する細胞一つ一つの「個性」を理解し、それらが作り出す「社会」の成り立ちを理解することであると信じています。本研究はその第一歩であり、まずは患者さんから頂いた乳がんの細胞の特徴を見ることに成功しました。「がん細胞社会」の理解、そしてがん克服を目指し、引き続き努力していきます。
がん進展と炎症による代謝リプログラミング機構の研究
谷口 浩二(慶應義塾大学医学部 微生物学・免疫学教室・特任准教授)
現在の日本人の死亡原因の一位はがんであり、その約9割はがんの転移によると考えられています。がん転移の予防や治療に有効な方法がなく、新しい予防・治療方法の開発が強く望まれています。がんが全身に広がった状態では、化学療法や放射線療法に加えて、がん免疫療法の効果が期待されていますが、まだ効果は十分ではありません。今回の研究ではがん細胞に起こる代謝変化に着目して、新しい観点からのがん転移の予防法と治療法の開発を目指しています。
成果報告によせて - 2017年度受賞者から
-
(受付順、敬称略)
脂肪細胞の形質制御における代謝エピジェネティクス
稲垣 毅(群馬大学 生体調節研究所・教授)
肥満症や糖尿病といった生活習慣病は、遺伝要因と環境要因によって発症する。しかしながら、生体がさらされてきた外部環境がどのように細胞に記憶されているかの分子機構は不明な点が多い。エピゲノムはゲノム配列によらない遺伝子発現の制御機構であり、可塑性が高いシステムであるため、外部環境を記憶するシステムとして優れていると考えられている。今回、エピゲノム酵素の働きの制御に関わる細胞中の代謝物濃度を測定する方法を立ち上げ、さらにヒストン修飾というエピゲノムマークを網羅的に解析する手法を立ち上げることで、代謝環境のエピゲノム記憶を制御する機構に迫った。その結果、肥満症と関連が深い脂肪細胞分化の過程で、代謝物濃度とエピゲノムの変化が見いだされた。
超解像度ケミカルイメージング顕微鏡の創成
高橋 康史(金沢大学・准教授)
細胞―細胞間のコミュニケーションや細胞の代謝により、細胞近傍の化学物質の濃度プロファイルは時々刻々と変化している。そのため、この細胞表面の化学物質の濃度プロファイルを捉えることは、非常に重要である。しかし、一般的に利用されている化学物質のセンシング技術は、位置情報と時間情報が失われた状態で計測が行われている。その一つの理由として、化学センサーの感度と、非常に柔らかい細胞近傍にセンサーを配置することが困難なためである。そこで、走査型プローブ顕微鏡のプローブとして、微小な電極やナノピペットに化学修飾を施したケミカルセンサーを用いることで、細胞近傍の化学物質の濃度プロファイルを形状方法とともに3次元的に取得した。
体の前後軸形成における下半身の位置を決めるバウプランの分子実体の解明
鈴木 孝幸(名古屋大学・講師)
私たち人を含む脊椎動物は体の中心に背骨を持っており、頭から頸椎、胸椎、腰椎、仙椎、尾椎に分けられる。興味深い事に、私たちの体の下半身には、仙椎の位置に後ろ足や生殖器、腎臓などの臓器があり、これらの器官の場所はどの動物においても同じである。今回我々は、このような下半身の位置がそれぞれの動物で異なりながらも、何故下半身に位置する器官の位置関係が保存されているのか、そのメカニズムを明らかにすることを試みた。その結果、Gdf11という1つの遺伝子が働くタイミングを生み出す機構がそれぞれの動物で異なることが、ヘビのような特異な体の形を生み出していることが明らかとなった。
視床下部と末梢臓器を結ぶ、糖代謝を制御する神経回路の解明
近藤 邦生(生理学研究所・助教)
脳の視床下部は体内の血糖値を一定の値に保つために重要な働きをしています。そのために視床下部は、白色脂肪から分泌されるレプチンなどの様々な体内・体外のシグナルを受け取り、末梢組織の糖の産生・消費をコントロールしています。今回私は、視床下部から糖の消費を担う2つの末梢組織(骨格筋・褐色脂肪)へシグナルが送られる際に使われる神経回路網の構造を明らかにしました。今回明らかになった神経回路の機能を解明することで、将来的に糖尿病や肥満の治療法の開発につなげていきたいと考えています。
アロマターゼ阻害薬治療を受けた転移性乳がん患者における血中循環腫瘍ゲノムの解析
ロー シューキー(公益財団法人がん研究会 がん研究所・グループリーダー)
これまで、診断目的のためにがん患者から生検を得る方法として、侵襲的な針による生検が行われることが多かった。しかしながら、この侵襲的な方法は複数回実行することは難しい。また、がんは非常に不均一であり、そして腫瘍のプロファイルは経時的に変化するため、原発腫瘍からの生検は、腫瘍における特定の時点でのゲノムプロファイルのみしか反映されないことになる。一方で、リキッドバイオプシー、特にctDNAは、血液、尿、脳脊髄液および唾液から抽出することができる。 ctDNAから得られるゲノムプロファイルは、非侵襲的で迅速かつ複数回入手することができることから、とても重宝されている。
本研究では、先進的である次世代シーケンシング技術を用い、血漿(血液サンプル)からの変異を検出することを目的とした。我々はこの研究から、血漿中に1つ以上の変異を有する20/26人の進行性乳がん患者を検出した(検出率:77%)。がんに関連する突然変異は全部で44個検出され、このうちESR1遺伝子の突然変異は薬剤耐性と関連があることが知られている。ctDNAのモニタリングは、病状のモニタリング、薬剤耐性および臨床的再発の早期発見に有用なツールである。骨粗鬆症克服を目指した新たな骨芽細胞シグナルネットワークの解明
松本 佳則(岡山大学・助教)
健康で豊かな長寿社会を実現させる為には、骨粗鬆症の予防、改善が急務です。50歳以上の日本人女性の3割が骨折や寝たきりの原因となる骨粗鬆症を発症する為、骨形成、骨吸収を担う骨芽細胞及び破骨細胞を制御する機序の解明は骨粗鬆症の克服に必須の研究テーマですが、未だその詳細は不明です。本研究では、骨形成を担当する骨芽細胞の新たな制御機構を明らかにしました。更なる研究を積み重ね、骨粗鬆症の治療へと応用出来るよう、今後も精進致します。
心臓細胞アトラスによる循環恒常性制御機構の解明
野村 征太郎(東京大学医学部附属病院・特任助教)
【背景】
心臓に高血圧などの負荷がかかると心臓は肥大してポンプ機能を維持しようとしますが、負荷が持続すると心機能が低下して心不全を発症します。しかし、これまでその詳細なメカニズムはわかりませんでした。
【目的】
心筋シングルセル解析により心不全発症メカニズムを明らかにする。
【結果】
我々は、シングルセル解析・機械学習により世界で初めて心筋リモデリングの過程における分子プロファイルの挙動を明らかにしました。その結果、心筋細胞の肥大化にはミトコンドリア生合成の活性化が重要であること、肥大心筋細胞は代償性心筋細胞と不全心筋細胞へと分岐すること、不全心筋細胞への誘導にはDNA損傷(DNAに傷が入ること)とがん抑制遺伝子であるp53の活性化が重要であることを明らかにしました。さらに、遺伝子発現パターンから患者の予後・治療応答性を予測できることを実証しました。
【今後の発展性】
明らかとなった分子メカニズムを標的として心不全の新しい治療法の開発が進むと考えられます。また本研究の成果は、あらゆる心臓疾患の病態の解明に役立つだけでなく、個々の心不全患者さんの治療方針を決める上で実際の臨床の現場に応用されることが期待され、これにより循環器疾患の精密医療(個別化医療)が実現すると考えられます。新規臓器欠損モデルの開発
磯谷 綾子(国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学・准教授)
近年、再生医療研究において、動物の体内に臓器を作らせる、異種間キメラ動物が注目されつつあります。異種間キメラ動物体内で臓器を作らせるためには、臓器欠損モデルの作出が欠かせないため、本研究において、新たな臓器欠損モデル動物の作製法の開発を試みました。我々は、Crispr/Cas9システムに着目し、細胞死誘導するsgRNAを同定し、機能を細胞レベルで確認しました。さらに、このsgRNAを恒常的に発現するマウス系統を樹立しました。今後、Cas9を臓器特異的に発現するマウスと組合せる事で、臓器欠損モデルを作製することができると期待しています。
中心小体におけるカートホイール構造構築の分子機構の解明
吉場 聡子(東京大学大学院 薬学系研究科・薬学部・特任助教)
細胞のなかにある1組の中心体は、細胞が分裂し2つに分かれるときにそれぞれの極となって分裂を正しく導く重要な役割を持っています。中心体の数の増加や機能の異常は、がんの発症やさまざまな病気と密接に関係していることがわかっています。中心体がどのように形成されるのかについて研究することで、細胞のがん化のメカニズムや関連する病気の原因が明らかになり、将来的には治療に役立つことが期待されます。
βアミロイドによるNa+,K+-ATPaseの不活化機構の構造的解明
金井 隆太(東京大学・助教)
アルツハイマー病は脳内でアミロイドβの凝集・蓄積により発症します。近年、アミロスフェロイド(ASPD)と呼ばれる、アミロイドβの特定の凝集体がNKAα3と呼ばれる神経細胞に特異的な膜蛋白質に結合し、強い神経毒性を示すことが分かってきました。そこで、私達は将来的にアルツハイマー病の治療薬創出を目指して、ASPDがどのようにしてNKAα3に結合し、その機能を破壊するのかを研究しました。その結果、ASPDはNKAα3が機能する際に生じる構造変化を阻害しているらしいことが分かりました。実際の創薬にはまだ遠いですが、これからも研究を続けていきたいと思います。
ドロップ・テクノロジーを用いたRNA蛍光センサーの進化的創出
松村 茂祥(富山大学 大学院理工学研究部(理学)・助教(テニュアトラック))
近年、蛍光を発する人工RNAの開発が急速に進んでおり、細胞内の任意のRNAの蛍光標識および可視化、細胞内RNA動態のリアルタイム解析などへの応用が期待されている。本研究は、これらの蛍光RNAを細胞サイズのマイクロドロップレットへ封入し、人為的に「進化」させることで、望みの特性をもつ蛍光RNAを自在に創製する方法論を確立し、ライフサイエンスにおけるRNAイメージングなどへの貢献を目指すものである。
がんの病態形成に関わるChk1標的因子の機能解明と革新的治療法の確立
島田 緑(山口大学 共同獣医学部・教授)
乳癌は日本人女性が罹患する悪性腫瘍の第1位であり、その罹患数ならびに死亡数は増加の一途を辿っています。ホルモン療法および抗HER2療法では効果がないトリプルネガティブ乳癌に対しては治療法は限定されており、予後は極めて不良であることから、有効な分子標的薬の創出が緊急に迫られています。本研究では、トリプルネガティブ乳癌で高発現しているCalcineurin脱リン酸化酵素を阻害するFK506が乳癌の増殖を抑制できることがわかりました。
緑藻の概日時計をリセットする未知の赤色光受容伝達経路の解明
松尾 拓哉(名古屋大学 遺伝子実験施設・講師)
私はクラミドモナスという緑藻の一種を使って体内時計を研究しています。私たち人間と同様、緑藻の体内時計も光によってリセットされます。しかしその分子メカニズムはよく解っていませんでした。私はこの研究により、その未知のメカニズムに関わる遺伝子を明らかにしました。その遺伝子の解析から、緑藻は他の生物には見られない独特な光応答メカニズムを持つことが見えてきました。この研究成果は、生物の光応答メカニズムの進化の理解につながると考えています。
膵β細胞における脂肪酸伸長酵素Elovl6の役割の解明
松坂 賢(筑波大学・准教授)
本研究では、パルミチン酸(C16:0)からステアリン酸(C18:0)への伸長を触媒する酵素Elovl6に着目し、2型糖尿病モデルdb/dbマウスの膵β細胞でこの酵素を欠損させると、2型糖尿病の発症・進展が抑制される可能性があることが示唆されました。本研究をさらに進めることにより、膵β細胞におけるElovl6の阻害や脂肪酸バランスの管理が、2型糖尿病の新規治療法となることが期待されます。
ヒトiPS細胞由来エリスロポエチン産生細胞を用いた腎性貧血に対する再生医療と新規治療薬の開発
長船 健二(京都大学iPS細胞研究所 長船研究室・教授)
現在、慢性腎臓病の進行によって慢性腎不全となり透析療法を受けている多くの患者さんがいます。慢性腎不全の合併症として腎性貧血があり、遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤投与による治療が行われておりますが、貧血の生理的なコントロールは依然として困難です。本研究において、我々はヒトiPS細胞からエリスロポエチンを産生する細胞を作る方法を開発し、さらに本細胞からのエリスロポエチン分泌を促進する活性を有する化合物を発見しました。今後、本化合物を用いた腎性貧血に対する再生医療と新規治療薬の開発が期待されます。
発生期脳神経細胞の生死を決める機構
仲嶋 一範(慶應義塾大学・教授)
マウス胎生期の大脳半球をある条件下で培養すると、神経細胞死が外側から背内側に向かって進行し最終的に全体が死滅することを見出した。その際、死んだ領域とまだ生き残っている領域の境界は極めて明瞭であり、かつ細胞死が起こらない筋状の領域が前後方向にほぼ一定間隔で現れた。複数の脳を半透膜で包んで共培養する実験から、この神経細胞死を完全に防ぐことのできる強力かつ低分子量の内在性因子が脳から分泌されていることを発見した。この因子を今後の研究で同定できれば、発生期の脳に内在する低分子量の強力な神経細胞死抑制因子として、臨床応用も視野に入ると期待される。
リプログラミング技術を応用した心臓ペースメーカー細胞の誘導法の確立
中尾 周(立命館大学・助教)
加齢に伴う心拍数の低下(徐脈)は、ときに息切れや動悸、失神を生じるほどに進行し、その主な治療法である機械式ペースメーカーの移植には、感染、故障、高額などの問題が残されている。本研究では、徐脈性不整脈に対する新たな再生医療の開発を展望として、心臓ペースメーカー細胞を体細胞から作り出す方法の確立を目的とする。この方法は、iPS細胞などの未分化細胞へ脱分化させる過程をスキップできることから、時間と費用を大きく節約できる特長がある。また、ペースメーカー細胞の性質を獲得させるための因子を特定するための手掛かりとして、病気モデルや胎児期の心臓形成に着目し、データの集積・解析を進めている。
NMR計算と全合成を基盤とした稀少ポリケチドホルモサリドAの構造決定
占部 大介(公立大学法人 富山県立大学・教授)
天然には、抗がん活性や抗菌活性など創薬において魅力的な生物活性を有する有機化合物が数多く存在します。一方で、天然から得られる量が限られている希少天然物の基礎研究は進展していません。本研究では、渦鞭毛藻から単離された希少天然物ホルモサリドAの初期段階の基礎研究として、その構造決定に取り組みました。現在までに、コンピューターを使ったホルモサリドAの構造推定に成功し、有機合成による推定構造の確認に着手しています。近い将来ホルモサリドAの構造が決定できると考えています。
マイクロRNAを用いた時空間制御可能なアポトーシス誘導法の開発
渡邉 和則(岡山大学・助教)
国内外の研究者により光による細胞機能制御法が開発されている。本研究では、申請者らが同定したアポトーシスを誘導するマイクロRNAであるpre-miR-XXと、光依存的にRNAを細胞内に輸送できるPCDR法を組み合わせることで、アポトーシスを時空間的に制御することを目的とした。その結果、PCDR法でpre-miR-XXを細胞内で導入することで、アポトーシスを高効率に誘導できるだけでなく、アポトーシスを時空間的に制御できることも明らかになった。本手法は副作用の小さいがん治療法として発展していく可能性を秘めている。
未開拓創薬有用天然物:ドラグマシジンEの不斉全合成研究
根本 哲宏(千葉大学大学院薬学研究院・教授)
ドラグマシジンEは、生体内で重要な役割を果たすセリン-スレオニンホスファターゼの阻害作用を示す化合物として知られているが、天然から得られる量はごく微量であり、詳細な研究には合成化学的な供給法の開発が不可欠となっている。私たちは、本天然有機化合物の合成法を開発し、医薬品開発への可能性を調査するために研究を進めている。これまでに、本化合物の主要骨格の構築法は開発したものの、鏡像異性体の作りわけに関しては一層の検討を要する。標的分子骨格の新規合成法開発を含めた、網羅的な研究を進めることで、本天然有機化合物の供給法を今後開発していきたい。
神経生理学と深層学習の組み合わせによる柔軟な判断の神経基盤の解明
熊野 弘紀(山梨大学・特任助教)
ヒトは環境に応じて柔軟に判断を切り替え、そのときの環境に応じた行動をとることができる。これまでに我々は、判断を切り替える際には、判断をくだすのに必要な情報を収集する過程が環境に応じて異なることを見出した。本研究では、前頭前野がどのようにダイナミックに情報収集過程を制御しているかを理解するために、前頭前野の広い範囲から皮質脳波を計測した。その結果、環境に関する情報は眼窩前頭皮質で最初に現れ、前頭前野の広い領域に伝播する可能性が示唆された。今後は、前頭前野に存在する環境情報がどのように判断をつかさどる神経回路に作用し柔軟な行動が可能になるのかを、神経生理学的手法と深層学習を併用して明らかにしたい。
ダウン症関連遺伝子DYRK1Aを標的とした新規アルツハイマー病治療薬の開発
浅井 将(東京理科大学薬学部・助教)
認知症患者は、団塊世代が75歳以上となる2025には700万人に達すると見積られており、その最大の原因疾患はアルツハイマー病である。アルツハイマー病の根本的治療薬は存在せず、多くの化合物の治験が中止となっている。本研究では、治療薬開発の着眼点を変え、早期からアルツハイマー病を発症するダウン症からヒントを得て、21番染色体に存在するリン酸化酵素に辿り着いた。この酵素はアルツハイマー病に増悪的に作用し、患者脳で発現が亢進していることから、その阻害剤は複数の作用点を有し、副作用が少ない治療薬になり得る。茶カテキン等が阻害活性を有していることから、さらなる開発が望まれる。
癌内皮細胞を標的とした抗癌剤感受性増大法の開発
村田 幸久(東京大学・准教授)
がん細胞と同様に、がんに伸びて酸素や栄養を届ける血管細胞も抗癌剤耐性能を獲得することが知られている。私たちは、このがんの血管に特異的に発現している酵素を発見し、この酵素の阻害ががん血管の薬剤耐性を解除することを発見した。この酵素の阻害剤と抗癌剤を同時に投与することで、がんに伸びる血管を効率よく抑えて、がんの増殖をとめることが可能となる可能性がある。
ストア作動性Ca2+流入シグナルソームの分子機序と生理的意義
馬場 義裕(九州大学生体防御医学研究所・教授)
本研究の目的はカルシウム流入に必須の分子であるSTIM1の活性を制御する新規分子を同定することです。免疫細胞の分化や活性においてカルシウム流入は極めて重要であり、免疫不全、自己免疫疾患、アレルギーの発症にも関与します。そこで、本研究成果はこれら疾患に対する新規薬剤の創薬につながる可能性があります。本研究では新規のSTIM1結合分子を同定でき、カルシウム流入に関与する可能性が示唆されたことから、今後さらに研究を進めていきたい。
正常と腫瘍血管内皮を規定するエピゲノムプログラムの解読
鈴木 拓(札幌医科大学・教授)
腫瘍血管新生はがんの発生や成長に重要な役割を担っており、有望な治療標的と考えられています。我々は大腸がん組織の遺伝子発現解析から新たな腫瘍血管関連因子としてAEBP1を同定しました。我々の研究からAEBP1は大腸がん組織の血管内皮細胞で高発現していること、そしてAEBP1が腫瘍血管新生を促進することが分かりました。マウスを用いた実験でAEBP1の阻害ががん組織の成長を抑制する効果が認められたことから、AEBP1はがん治療標的となりうる可能性が示されました。
がん分子標的薬によって誘導される悪性腫瘍化RNAファミリーの解明
近藤 茂忠(大阪府立大学・教授)
現在、がん関連分子を標的とした分子標的薬治療は悪性腫瘍の標準化学療法となっている。しかしながら、がん細胞は分子標的薬に対して抵抗性を獲得することが臨床的に大きな問題となっている。これまでに、3つの分子標的薬耐性メカニズム〔① 標的分子の耐性変異獲得、② バイパス経路の活性化、③ 標的分子の下流経路の活性化〕が明らかとされている。本研究では全く新しい耐性獲得メカニズムの可能性を見出した。
血管の統合性制御に基づく、転移抑制法の開発
新藤 隆行(信州大学大学院医学系研究科・教授)
血管の恒常性は、液性因子とその受容体システムによって制御されています。私達は、アドレノメデュリン(AM)が主として血管から分泌され、様々な生理作用を有することを明らかとしてきました。AMとその受容体活性調節タンパクであるRAMP2は、血管恒常性維持に重要な働きをしています。この研究において、私達は、血管内皮細胞特異的なRAMP2ノックアウトマウスや、RAMP2過剰発現マウスを用いて、AM-RAMP2系の癌転移における意義をはじめて明らかとしました。
注目すべきは、血管内皮細胞にRAMP2を過剰発現したマウスでは、癌の転移が抑制され、生存率が改善したことです。この結果から、血管の恒常性維持に注目することで、癌転移を抑制する新しい治療法につながることが期待されます。自己免疫疾患の発症を抑制する胸腺上皮細胞への分化決定機構の同定
秋山 泰身(理研 統合生命医科学研究センター・チームリーダー)
免疫応答の司令塔であるTリンパ球のほとんどが胸腺で産生されます。胸腺でT細胞が産生する際、自己の組織に応答するTリンパ球も生じます。そのほとんどは胸腺であらかじめ除かれますが、それらがうまく除かれない場合、自己免疫疾患の原因になると考えられています。本研究では、胸腺で自己組織応答性Tリンパ球を除去し、自己免疫疾患の発症を抑制する上皮細胞に着目し、それらの細胞がどのような機構で発生するのか調べます。本研究の成果は、将来的に自己免疫疾患の発症予防や治療に貢献することが期待されます。
ストレスセンサーとしての核小体を介した細胞機能の制御
木村 圭志(筑波大学・准教授)
核小体は核内に存在する多種類のタンパク質とRNAから成る構造体で、リボソーム生合成やストレス応答など多くの細胞機能に関与します。細胞が種々のストレスに細胞がさらされた際には、核小体が崩壊しそれに伴って局在を変化させた核小体因子が種々の細胞機能に関与します。また、細胞分裂に伴って核小体が崩壊し多くの核小体因子が局在を変えることから、核小体と細胞分裂の関連性が示唆されてきましたが、その実態は分かっていませんでした。本研究で我々は、核小体因子であるNWC複合体が、分裂期の染色体周辺に結合し動原体の機能を制御することにより正常な細胞分裂に寄与することを見出しました。
血管発生・形態形成とヒト血管病におけるシグナル伝達機構:多階層オミックス解析による研究
中川 修(国立循環器病研究センター 研究所 分子生理部・部長)
細胞分化・増殖・移動など多様な生命現象の組み合わせにより、複数の起源を有する前駆細胞から心臓・血管の発生・形態形成が行われ、多様な細胞群が協調して働く成熟機能システムを実現するメカニズムは非常に複雑であり、その破綻が先天性心疾患・遺伝性血管疾患のみならず成人の循環器疾患の病因に深く関わることは明らかです。心血管系の発生・形態形成過程において様々な細胞間・細胞内シグナル伝達系が働くことが知られていますが、私たちはそれらシグナル伝達系の活性化や阻害によって内皮細胞の遺伝子発現様式・タンパク質分子発現様式などがどのような影響を受けるかを検討しました。今後も心血管形成におけるシグナル伝達機構の研究を続け、ヒト心血管疾患の病因・病態解明と診断法・治療法開発を目指したいと考えております。
細胞外DNAの形成機序とその生理作用に関する研究
斉藤 寿仁(熊本大学大学院先端科学研究部・教授)
DNAは核内に保持されるだけでなく、細胞外に放出されることがある。例えば、白血球が細胞外に形成するNeutrophil Extracellular Traps(NETs)のDNAは、細菌の侵入とシグナル因子の拡散を調節することで、免疫応答に関わる。しかしながら、細胞外DNAの形成と機能についての詳細は、不明な点が多い。本研究では、白血病由来細胞HL-60を小胞体ストレス誘導剤Tunicamycinで処理することで細胞外DNAを誘導する実験系を構築した。細胞外DNAに関する未踏破の研究領域に踏み込んだことで、遺伝暗号やエピジェネティクス以外のDNA機能の重要性を指摘し、新たな保健医療技術を開拓するための知的基盤を構築した。
5-HT2A 受容体刺激薬の精神疾患治療薬としての有用性
衣斐 大祐(名城大学・助教)
うつ病患者の30%は既存の抗うつ薬が効きにくい難治性である。
最近の臨床研究から幻覚薬でセロトニン5-HT2A受容体(5-HT2A)刺激薬のシロシビンが、難治性うつ病患者に対して、即効的かつ持続的な抗うつ作用を示した。そこで我々は、5-HT2A刺激薬による抗うつ作用についてマウスを用いて調べたところ、5-HT2A刺激薬は、うつ病モデルマウスにおいて、即効的かつ持続的な抗うつ作用を示した。さらにその作用には外側中隔核におけるGABA神経の活性化が関与していることが証明された。本研究によりうつ病治療における5-HT2A刺激薬の有用性が示されれば、本研究が新たな抗うつ研究の礎となることが期待できる。Developmental Biology in Plants
鄭 恵国(北海道大学国際連携機構・助教)
我々の研究は初期陸上植物の植物体の発生調節におけるROPシグナル伝達経路の重要性を強調している。
エネルギー状態に基づき授乳行動を制御する新規オキシトシン神経機構の解明
室井 喜景(帯広畜産大学・准教授)
哺乳類の母親は乳で仔を育てます。エネルギーを失うことは自分の生存に不利なことですが、母親は授乳により自分のエネルギーを自ら進んで仔に分け与えます。本研究ではそんな母親の性質を司る仕組みを明らかにすることを目指しました。今回の研究で、低エネルギー状態でもオキシトシンが脳に作用することで母親は授乳し続けることがわかりました。これまでにオキシトシンは乳腺に作用し射乳を促すことがわかっていましたが、母親の行動にも影響し授乳を促すことが明らかになりました。オキシトシンが自己犠牲的なお母さんの性質の一面を担っていると考えられます。
胸腺上皮細胞分岐分子機構の解析
大東 いずみ(徳島大学先端酵素学研究所・准教授)
免疫の中枢器官である胸腺を構成する皮質、および、髄質上皮細胞は、生体防御に必須なT細胞の産生を担います。本研究では、皮質/髄質上皮細胞の分化を制御するメカニズムの解明を目指しました。上皮細胞の分化制御メカニズムを解明することは、将来、免疫不全症や自己免疫疾患の根本的治療法開発につながると考えられます。また、本研究を進める中で、胸腺上皮細胞で発現する遺伝子が精巣でも発現しており、生殖能獲得に重要であるという、予想外の結果を得ました。男性不妊発症のメカニズム解明や、治療法開発につながることが期待されます。
肝脂質代謝におけるHeat shock protein 40 Member C1の意義
中司 敦子(岡山大学病院 腎臓・糖尿病・内分泌内科・助教)
近年脂肪肝や脂肪肝炎が増加していますが、発症・進展のメカニズムについて未解明な部分も多くあります。細胞は生存・機能に必要な蛋白を合成しており、蛋白が正しい構造になるのを手助けする多種類の“シャペロン分子”が存在しています。近年、それぞれが、シャペロン機能とは無関係の、独自の「固有機能」を持つことが分かってきました。Dnajc1はいまだ未解明な点が多い分子ですが、我々が以前の研究で、肝細胞の細胞質のみならず細胞表面にも存在し、糖脂質代謝に関係する可能性を見出したシャペロン分子の一つです。Dnajc1は肝臓で糖代謝を改善させ、炎症を抑制する結果が得られました。さらに今後研究を進め、脂肪肝・脂肪肝炎の予防や治療に結び付けたいと考えています。
CCR1陽性骨髄由来細胞をターゲットにした新たな大腸癌治療
河田 健二(京都大学・講師)
大腸癌に対する新規治療法として、腫瘍微小環境にある宿主因子である骨髄球、とくに好中球に着目して研究を進めています。マウスモデルや臨床検体を用いて検討してきた結果、ケモカイン受容体であるCCR1とCXCR2がとくに重要なターゲットになり得ることを明らかにすることができました。臨床の現場で役立つところまではもう少し時間がかかるとは思いますが、さらに研究を進めていけたらと考えています。
性決定システムの進化機構の解明
竹花 佑介(長浜バイオ大学・准教授)
ほとんどすべての動物にオス・メスがあるのと対照的に、オス・メスを決定する仕組みは動物種によってさまざまです。しかし、この性決定の仕組みがどのように多様化してきたのかは、ほとんどわかっていません。今回の研究により、メダカ属という近縁なグループ内で、下流遺伝子の重複転座によって異なる性染色体が独立に進化してきたことや、XY型とZW型で性決定遺伝子の作用点が異なることを示すことができました。これらの成果は、性決定の仕組みが(従来考えられてきたよりも)さらに多様である可能性を示唆しています。
3次元神経病理学に向けた特異的ケミカルプローブの設計戦略
田井中 一貴(新潟大学脳研究所・特任教授)
現在の神経病理学では、薄切標本に基づく2次元平面の病理学的解析が基盤となっていますが、平面の病理学的解析だけでは対処困難な多くの課題があります。私たちは、この課題を解決するために「立体的な脳組織を立体のままもれなく観察すること」を実現する、組織透明化技術に基づく3次元イメージングCUBICを開発しました。今回の助成研究では、ヒト脳組織の高度な透明化に取り組むと共に、透明化手法に適用可能な種々の染色手法を確立しました。本手法を用いて、3次元画像に基づく病理診断技術の実現を目指します。
浸透圧調節を担う塩類細胞における分子基盤の構築
宮西弘(宮崎大学・助教)
淡水と海水の両方で生きられる魚は、異なる塩分環境に適応するため、鰓に存在する塩類細胞の機能を、環境に合わせてイオンの取り込む(淡水中)、または排出(海水中)するように切り替えます。しかし、塩類細胞の分化および機能的可塑性に関する機構は分かっていません。まず我々は、転写因子FOXI1が、全てのイオン取り込み型および排出型の塩類細胞の分化に必須であることを証明しました。FOXI1のさらに下流のシグナリングを明らかにするために、イオン取り込み型および排出型の塩類細胞特有の遺伝子プロファイルを明らかにしました。さらなる解析をとおして、なぜ魚が川や海で生きられるか?を明らかにするとともに、FOXI1の関与が示唆されるヒトの難治性難聴の発症機序の基礎知見に繋げていきます。
筋衛星細胞の未分化性維持機構の解明と筋ジストロフィー治療法への応用
林晋一郎(国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所・室長)
遺伝性の筋疾患である筋ジストロフィーの根本的な治療法は未だ確立されていません。筋幹細胞を移植する方法が根治療法の一つとして期待されていますが、生体外で筋幹細胞の未分化性を保持したまま培養することが難しく、筋幹細胞の未分化性維持機構の解明が課題となっています。本研究では筋幹細胞の未分化性をレチノイン酸受容体アゴニストによって維持できること、また、そのシグナルはRARを介していることを明らかにしました。本研究をさらに進め、難治性筋疾患治療法開発に役立てたいと考えています。
成果報告によせて - 2016年度受賞者から
-
(受付順、敬称略)
Long non-coding RNAによるストレス応答性スプライシングの制御機能の解明
廣瀬 哲郎(北海道大学 遺伝子病制御研究所・教授)
21世紀のポストゲノム時代に入り、ヒトゲノムの75%もの領域から正体不明なノンコーディングRNA(lncRNA)が産生されていることが明らかになり、その機能に注目が集まっている。Sat IIIと呼ばれるlncRNAは、熱ストレスが細胞に加わった際に合成され、核内ストレス体という顆粒状の核内構造体を組み立てる機能を果たしている。実施者は、今回この核内ストレス体の果たす機能を調べた結果、Sat III lncRNAが核内ストレス体内に係留しているSRタンパク質という制御因子のリン酸化状態をコントロールして、遺伝子発現過程の一段階であるRNAスプライシングを制御していることを発見した。このメカニズムは、lncRNAが細胞のストレス状態からの回復を効率よく行うために働いていることを示しており、ヒトの身体のストレス遭遇時に重要な役割を果たしている可能性が浮上した。
性染色体組み換え抑制の起源
菊池 潔(東京大学大学院農学生命科学研究科・准教授)
ヒトのY染色体は著しく退化しており、大多数の遺伝子を失っています。このような退化したY染色体は多くの動植物にみられます。この性染色体の退化は「組み換え抑制」によってもたらされますが、「その原因は染色体間の逆位である」と説明されてきました。しかし、この説は、ヒトやハエの退化しきった性染色体をもとにした説であり、真の原因はわかっていません。我々は、退化直前・直後の性染色体をもつ魚類群を発見しました。これらを調べたところ、逆位が組み換え抑制のトリガーではなさそうだということがわかりました。抑制がある種とない種で、性決定領域のDNA配列は類似していることから、エピゲノム機構が、組み換え抑制に関わる可能性が高いと考えられました。
シングルセルトランスクリプトーム解析による神経情報処理の新規機構の同定
太田 茜(甲南大学・特別研究員)
温度は生物の生死に直結する環境情報である。本申請者はこれまでに、C. elegansの低温耐性を指標に、温度応答のシンプルな実験系を確立した (Ohta et al., Nature commun,2014)。具体的には、頭部の感覚ニューロンが温度を感知し、インスリンを分泌することで、腸などに働きかけ、温度耐性を獲得させる。さらに、腸が精子に働きかけ、精子が頭部の温度受容ニューロンをフィードバック制御する (Sonoda, Ohta et al., Cell reports, 2016)。本研究を通じて我々は、低温耐性に関して、温度受容ニューロンで機能する新規の分子を同定した。
ライブイメージングとシミュレーションを用いた澱粉粒の形状決定機構の解明
松島 良(岡山大学 資源植物科学研究所・准教授)
澱粉粒とは、植物細胞内で合成された澱粉が形成する粒子のことである。澱粉粒は、アミロプラストという植物オルガネラの内部で合成される。澱粉粒の形状は植物種によって多様性を示し、その形状は澱粉の利用用途と精製効率を規定する重要形質と考えられている。しかし、澱粉粒の形状が決定される仕組みは未解明である。本研究では、蛍光タンパク質を用いて、生きた細胞内でアミロプラスト並びに澱粉粒を可視化する観察系を構築した。今後、澱粉粒やアミロプラストを形態学的に解析する上で、極めて重要な研究ツールになり得るだろう。
前立腺癌におけるRNA結合タンパク質PSFを介したゲノムワイドでの転写、翻訳制御機構
高山 賢一(東京都健康長寿医療センター研究所 老化制御 健康長寿ゲノム探索・研究員)
前立腺がんは世界的にみて男性に発生するがんとして最も多いがんです。男性ホルモンであるアンドロゲンによりがんの成長、病気の進行を促進することが知られておりアンドロゲンを抑制する薬剤が治療に用いられるものの治療抵抗性に陥ることが問題となっています。治療抵抗性の出現にはアンドロゲンの受容体の発現上昇が知られていますが、その機序がよくわかっていません。遺伝子の発現にはDNAからの転写により生成されるRNAから蛋白合成を通じて行われます。本研究はRNA結合タンパク質であるPSFがアンドロゲン受容体およびRNAの成熟に関与する遺伝子群のRNAに作用することでその安定性、発現を促進していることを明らかとしました。RNA成熟に関与する遺伝子群の発現上昇が引き起こされアンドロゲン受容体の活性化、がんの悪性化につながる新たな作用機序を見出しています。
海馬における経路特異的な情報処理機構の解明
水関 健司(大阪市立大学大学院医学研究科・教授)
海馬と呼ばれる脳の領域は、個人的な経験を思い出す能力であるエピソード記憶に重要な役割を果たします。本研究では、海馬からどの脳領域へどのような情報が伝達されるのかを明らかにするための基盤的な技術を開発しました。今後は開発した技術を用いて、海馬と他の脳領域がどのように情報をやり取りして記憶をサポートしているのかを明らかにしたいと考えています。アルツハイマー病などの認知症では、ごく初期から海馬に変性がみられます。海馬における情報処理のメカニズムを少しでも明らかにして、将来的に認知症の新規治療法を確立するための基盤を作りたいと考えています。
抗腫瘍活性海洋産アルカロイドをモチーフとする天然物創薬
好光 健彦(岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科(薬学系)創薬有機化学分野・教授)
海綿から見出されたアゲラスタチンAは,抗がん剤の開発において大変魅力的な物質として興味を集めています。これまで我々は,アゲラスタチンAの化学構造を人工的に改変し,抗がん剤のリード化合物を創り出す研究を進めてきました.本研究では,こうした創薬研究の基盤を成す化学合成法の開発,化学合成によって得た化合物の中から有望な物質を見出すこと,そして,アゲラスタチンAの作用機序の解明に役立つ分子プローブの合成に取り組みました.その結果,各種誘導体の新規合成法の開発並びにリード化合物の設計指針となる知見を得ることに成功しました。
血管ニッチによって制御されるステムセルエイジングと加齢関連疾患発症機序の解明
南野 徹(新潟大学循環器内科・教授)
本研究で私たちは、心不全に伴って心臓で炎症が惹起される機序について明らかにしました。このような炎症の亢進が、心不全悪化につながっていることから、今後新たな治療の標的となりうると考えられます。
小分子RNAを介したゲノム三次構造制御によるトランスポゾン抑制機構の解明
岩崎 由香(慶應義塾大学医学部分子生物学教室・専任講師)
生物の設計図であるゲノムは、自身のコピー数をどんどん増やしてしまう「利己的な遺伝子」として知られるトランスポゾンの転移により、傷ついてしまいます。piRNAと呼ばれる小さなRNAが、このトランスポゾンを抑え込む働きをしており、この制御が正常に機能しないと不妊等が引き起こされることが知られています。そこで本研究では、piRNAがどのようにトランスポゾンを抑制するかを解析しました。研究成果として、piRNAによるトランスポゾンの抑制においては、核内でゲノム(クロマチン)がどのように折りたたまれているかが制御されることが重要だということが分かりました。
アルキンの転位を起点とする水を酸素源とするスピロケタールの触媒的合成法の開発
武藤 雄一郎(東京理科大学・助教)
本研究では、これまでの常識では考えられなかったルテニウム触媒をもちいる内部アルキンの1,2?転位を起点とする[5,6]?スピロケタールの触媒的新規合成法の開発に挑戦しました。[5,6]?スピロケタールは、ベルケリン酸やγ-ルブロマイシンなど抗腫瘍生物活性物質の活性を担う重要な骨格です。今後の薬理学研究に向けてスピロケタールライブラリーを構築するためには、それらを自在に合成できる新たな反応の開発が必要不可欠です。低収率ではありますが、[5,6]?スピロケタール新しい合成法の開発に成功し、段階的に反応を行うことによって反応機構についても明らかとしました。
脳内低酸素応答の病態生理学的意義およびその介入による中枢神経疾患への応用
白川 久志(京都大学 薬学研究科 生体機能解析学分野・准教授)
脳血流の軽度な低下は、脳梗塞や心不全にかかったり、継続的なストレスを受けたりすることで起き、さらに高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病による動脈硬化により慢性化されます。これまでに我々は、軽度な脳血流の低下であっても長く続くことで白質傷害を主に介して、軽度な認知機能障害になることを示してきましたが、本研究により低酸素感受性を有するTRPA1チャネルがこの軽度な認知機能障害に対して保護的な役割を果たしていること、並びにこのTRPA1を刺激することにより病態を改善できる可能性を示すことができました。今後はこのTRPA1チャネルを介した保護機構をより詳細に解析したいと思います。
エリスロポエチン受容体を介した慢性骨髄増殖性腫瘍の発症機序の解明
多胡 めぐみ(慶應義塾大学薬学部・准教授)
慢性骨髄増殖性腫瘍 (MPN) の効果的な治療薬を開発する上で、未だ不明な点の多いMPNの発症メカニズムを解明し、理解することが重要です。今回の研究では、MPNの原因となることが知られているチロシンキナーゼJAK2変異体が、サイトカイン受容体EpoRを介してSTAT5やERKなどのシグナル伝達分子を活性化し、細胞増殖や腫瘍形成を誘導するメカニズムを明らかにしました。本研究を通して、EpoRがMPN治療薬の標的分子となりうる可能性が高いことが示されました。
成長因子受容体を介した成熟心筋細胞の増殖誘導とその分子機構の解明
平井 希俊(関西医科大学 薬理学講座・講師)
心筋細胞は生後細胞周期の休止期に入りその後増殖することはない。そのため心筋梗塞で心筋細胞が失われると心機能障害をきたし心不全を発症してしまう。本研究ではマウスで成長因子受容体シグナルを活性化することにより、成熟心筋細胞の増殖を誘導しうるかどうかを明らかにすることを目的とした。本研究の結果、心筋細胞で成長因子受容体を過剰発現させ、その細胞を1細胞レベルで直接可視化できるマウスの作製に成功した。今後、このマウスを用いて、成熟心筋細胞の増殖を誘導することが可能であれば、梗塞後心不全に対する新規治療の開発への展望が開けるだろう。
希少がんである神経内分泌腫瘍のがん抑制遺伝子PHLDA3の遺伝子診断による 新しい予後・治療薬選択の診断法開発~神経内分泌腫瘍患者の個別化医療を目指して~
大木 理恵子(国立がん研究センター研究所 基礎腫瘍学ユニット・独立ユニット長)
神経内分泌腫瘍は全身の様々な臓器に生じますが、希少がんであるため研究開発は遅れており、有効な診断法・治療法がありません。私たちは、肺と膵臓の神経内分泌腫瘍において、PHLDA3遺伝子は高頻度にゲノム異常によって機能が失われていることを発見し、PHLDA3遺伝子が肺と膵臓の神経内分泌腫瘍において、がん抑制遺伝子として機能している事を明らかにしました。さらに、PHLDA3機能が失われている症例は悪性度が高く予後不良である事が示されました。これらの知見を元に、神経内分泌腫瘍のヒトや動物のサンプルを解析し、その本態を解明し、治療と診断に貢献したいと考えております。
病態特異的ヒストンメチル化制御異常の白血病発症における役割
上田 健(近畿大学医学部・講師)
急性骨髄性白血病で高発現を認めるエピゲノム制御因子が白血病の病態にどのように関与しているかを明らかにする研究を進めています。
全身投与可能ながん標的化改変ヘルペスウイルスによる転移性悪性腫瘍の治療法開発
内田 宏昭(東京大学医科学研究所・講師)
がん細胞だけに特異的に侵入し、静脈内投与可能な標的化腫瘍溶解性ウイルス療法が開発できれば、原発巣のみならず全身の転移巣にも有効な治療法となりえる。私たちは、単純ヘルペスウイルス(HSV)にがん細胞表面抗原を認識する単鎖抗体を組み込むことにより、標的細胞のみに侵入可能な標的化HSVの構築に独自に成功した。この標的化HSVは、現在臨床開発が進められているウイルス複製の段階でがん選択性を発揮するHSVに比して、より静脈内投与に適していると考えられる。
液中先端増強超解像ラマン顕微鏡による細胞膜のin vitro観察及びその機能解明
バルマプラブハット(大阪大学・教授)
細胞膜は細胞同士を隔てる単なる仕切りではなく、細胞外からの情報をやり取りしたり、必要な物質を細胞内に輸送したり、私たちの健康を維持するために必要な機能を沢山持っています。また、多くのウィルスや薬も細胞膜を足掛かりとして作用するので、細胞膜の様々な現象を単分子レベルで解明することは、創薬の発展にもとても重要です。しかし、ありのままの細胞膜を単分子レベルで観察する手法は非常に困難です。私たちは、これを実現すべく生体環境で使える先端増強ラマン散乱顕微鏡という装置を開発しました。単分子レベルの分解能でありのまま細胞膜を観察できるため、今後細胞膜の研究にますます役立つことと期待しています。
免疫-神経-代謝システム間連携による心臓恒常性維持と心不全発症機序の解明
眞鍋 一郎(千葉大学・教授)
心不全は急速に増加しており、新しい治療法を開発することは喫緊の課題です。私たちは、心臓に存在するマクロファージ(免疫細胞の一種)に注目して、その機能の解析を行いました。心臓マクロファージは心臓へのストレスに対して心臓を守る機能を持っています。また、アンフィレグリンという分子を作ることが大事なことを見いだしました。心臓マクロファージの機能は、心臓-脳-腎臓をつなぐネットワークによって制御されています。また、心臓の中では、心臓に存在する心筋細胞等の細胞との関連によって制御されています。本研究で同定したメカニズムは今後の心不全治療法の開発に役立てることができると考えています。
睡眠下のシナプス可塑性とリプレー現象の記憶固定化における役割
林 康紀(京都大学医学研究科システム神経 薬理学教室・シニアチームリーダー)
記憶は学習後、海馬に短期的に保持されたのち皮質に移行し長期的に保存されます。これは記憶の固定化と呼ばれ、我々の日常において重要な機能です。しかしその詳細なメカニズムは分かっていません。我々は記憶の固定化においてLTP(シナプス長期増強)が重要な役割を担っていると考えました。本研究では光照射によってLTPを解除する方法を開発しました。光照射によってLTPの解除することで、LTPが生じる詳細な場所と時間を知ることが可能になりました。したがいまして本技術は、記憶の固定化の過程(特に睡眠中)のいつどこでLTPが生じて固定化が完了するかを知ることができる画期的な技術と言えます。
生殖幹細胞の性決定機構の解明
田中 実(名古屋大学・教授)
生殖幹細胞が卵になるか精子になるかの仕組み(生殖細胞の性決定)を理解することは、基礎生物学のみならず、生殖医学や再生医学、さらには育種分野においても極めて重要である。にもかかわらず、この仕組みはほとんどわかっていない。今回の研究により、この生殖細胞の性決定を司る遺伝子の候補を絞り込むことができた。さらには今まで知られていない生殖細胞の特性も明らかにできた。生殖細胞は単に卵や精子になるだけではなく、メスになるためには必要不可欠の細胞であり、この特性は生殖細胞が本来もつ特性(すなわち自身が卵になったり精子になったりすることとは関係ない)であることを示すことができた。
肺腺がんでのROR1によるカベオラ形成とカベオラエンドサイトーシス制御機構の解明
山口 知也(熊本大学大学院生命科学研究部・准教授)
これまで私達は、リネジ生存癌遺伝子であるTTF-1によって転写活性化されるROR1が、EGFRやMET、IGF-IR等の多様な受容体の活性化の維持に寄与することで、肺腺がんにとっての重要な生存シグナルを担うことを明らかにしてきた。本研究では、受容体としてのROR1の新たな機能に着目し、肺腺がん細胞におけるカベオラの詳細な生理機能の解明を目的とした。 本研究により、ROR1はカベオラ依存的なエンドサイトーシスによって生じたエンドソームにおいて様々なアダプター蛋白質をリクルートし、肺腺がん細胞の生存シグナルを経時的、及び空間的に制御していることが判明した。
本研究の成果は、ROR1とエンドサイトーシスに関わるCAVIN3との相互作用を標的とした、これまでにない肺腺がんの生存シグナルを特異的に抑える独自性の高い革新的な阻害剤の開発につながると期待される。環境要因とエピゲノムによるエネルギー代謝制御
松村 欣宏(東京大学先端科学技術研究センター・准教授)
脂肪組織は全身のエネルギー代謝を担う重要な組織で、脂肪組織の機能破綻はメタボリックシンドロームの発症と関係しています。白色脂肪細胞は脂肪を蓄える一方で、ベージュ脂肪細胞は脂肪を燃焼し熱を産生します。環境は後天的なゲノム修飾であるエピゲノムを介して、脂肪細胞の性質を決めると考えられています。本研究により、寒さの刺激は脂肪を燃焼するベージュ脂肪細胞を作り、過剰なエネルギーは脂肪を蓄える白色脂肪細胞を作ることが分かりました。
ミトコンドリア・ダイナミクスと抗ウイルス自然免疫
小柴 琢己(九州大学・准教授)
近年の研究から、ミトコンドリアには今までに知られていない新たな生理機能として、RNAウイルスに対する自然免疫に密接に関わる仕組みが備わっていることが明らかになってきた。しかしながら、このミトコンドリアを介した自然免疫の作動はどのような機構により調節されているのか?不明な点が多く残されている。本研究では、ミトコンドリアの形態的な特徴に着目し、ダイナミックな構造特性が自然免疫応答に必要であることを明らかにした。
神経前駆細胞の安定的培養法の確立に向けた、エピゲノム的制御機構の解明
笹井 紀明(奈良先端科学技術大学院大学・准教授)
再生医療の研究に対して、ES細胞やiPS細胞を用いた神経分化の研究が盛んに行われています。特定の神経へと分化させる上においては、分化した細胞の純度や効率が問題になっています。本研究ではこれらの問題を解決するために、「神経前駆細胞」を利用することを試みました。この細胞は、神経にしか分化しないために、分化させた時に純度の高い細胞が得られ、また効率も良いと推定されます。本研究ではこの神経前駆細胞を安定的に維持するために必要な遺伝子の同定を試み、その一端を明らかにしました。
大腸がん幹細胞の未分化性維持におけるヒストン修飾調節機構の解明と創薬への応用
浜本 隆二(国立がん研究センター研究所・分野長)
本研究代表者は、ヒストンメチル化異常の細胞がん化における重要性を世界に先駆けて明らかにし、その後も常に世界最先端の研究を行ってきた結果、ヒストンを含めたタンパク質メチル化は非常に多様性のある現象であることを解明してきた。一方、最近ヒトがんにおけるがん幹細胞の重要性が明らかになってきており、がん幹細胞を標的とした分子標的治療薬を開発することにより、効果的ながん治療を行うことができる可能性が示唆されている。本研究は、大腸がん幹細胞における、タンパク質メチル化の重要性を明らかにし、ヒストンメチル化関連酵素を標的とした、革新的な新規分子標的治療薬を創生することを目的として施行した。
炎症収束機構の破綻によるリンパ腫進展メカニズム
片山 義雄(神戸大学・講師)
我々がリンパ腫の患者さんから独自に発見したTFLという分子は、炎症の収束に必須の分子でした。この分子がないと、一旦起こった炎症が収束せずに続いてしまうのです。悪性リンパ腫は血液悪性腫瘍の一種ですが、発熱や体重減少、寝汗など全身性炎症症状が特徴です。マウスモデルを用いた本研究で、我々はマウスリンパ腫モデルの予後がTFL分子の有る無しで変化することと、その変化に重要なTFLによってコントロールされている可能性の高い分子を見いだしました。成因のわかっていない悪性リンパ腫の進展を癌という観点ではなく炎症収束機構の破綻と捉える考え方ができる可能性を示唆しており、通常用いられている抗がん剤ではなく炎症を標的としたリンパ腫治療の可能性を探る糸口になるかもしれません。
骨粗鬆症マウスを利用した新規骨芽細胞機能調節分子CRIM1の同定と機能解析
古市 達哉(岩手大学農学部共同獣医学科・教授)
私たちは骨粗鬆症を発症する新規変異マウスを同定し、imlaマウスと命名しました。本研究では全エクソーム解析と連鎖解析という方法を用いて、imlaマウスにおける骨粗鬆症の原因遺伝子としてCrim1を同定しました。Cim1は骨を作る骨芽細胞に発現しており、骨芽細胞の機能を調整することによって、骨量を制御している可能性が示されました。今後は骨量制御におけるCRIM1の役割を明らかにし、CRIM1を標的とした骨粗鬆症治療薬の創薬研究基盤の確立を目指して、研究を展開します。
ペルオキシソーム欠損症:小脳における病態発症の分子メカニズムの解明
藤木 幸夫(九州大学 生体防御医学研究所・特任教授)
細胞小器官ペルオキシソームの形成障害は、大脳や小脳における神経発生・分化障害・神経変性を特徴とする先天性致死疾患ペルオキシソーム欠損症をもたらすが、その発症メカニズムは不明である。我々は病態発症の分子機構解明を目的として、ペルオキシソーム欠損症モデルマウスを作出し、検証を進めるなかで小脳における神経栄養因子NTの発現量増加を見出している。また、このモデルマウス小脳の神経初代培養実験により、過剰なNTが小脳プルキンエ細胞の形態異常を導くことやサイトゾルの還元化がその発現量増加に関与することを明らかにした。これらの研究成果は、未だ治療法が確立していないペルオキシソーム欠損症の治療法開発にも繋がるものと期待される。
竹由来抗菌セルロースナノファイバー/コラーゲン透明コンポジットの創製
小林(岡久)陽子(京都工芸繊維大学・助教)
竹材の表皮や筍皮の細胞には抗菌性があることが経験的に知られており、古来より食品の保存や薬品などに用いられてきました。本研究では、このような竹の持つ抗菌・抗酸化成分を利用した抗菌ナノセルロース医療用材料の創製を目的に、抗菌成分の抽出、活性試験、および抽出残渣からのセルロースナノファイバー製造を行いました。その結果、抽出した成分からは黄色ブドウ球菌のようなバクテリアのみならず、真菌類への阻害効果が示唆されるなど、新たな効果が発見され、また抽出残渣からはセルロースナノファイバー製造に成功しました。高い生体適合性を有しながらも機械的特性の低さからこれまで利用が制限されてきたコラーゲンなどの医療用ゲル材料補強に、今回得られた筍皮由来抗菌成分およびナノファイバーを用いることで、幅広い用途展開につなげて行きたいと考えています。
分化後神経細胞への直接的遺伝子治療法確立のための基盤技術開発
生沼 泉(兵庫県立大学大学院生命理学研究科・教授)
もし、本研究期間に至適化に成功した成熟後神経細胞へのノックイン手法により中枢神経回路の可塑性ともいえる再生現象が引き起こされれば、「中枢神経自らは再生しない」という科学的常識を覆し、生物学の教科書にある「常識」を書き換えるほどのインパクトを与えるともに、幹細胞移植に依らない非侵襲的再生治療法の実現のための基盤研究として、iPS細胞開発以来の大きく、新たな視点が与えられる。
血管内腔圧制御による血管新生モードのスイッチング機構
西山 功一(国際先端医学研究機構・准教授)
血管新生は、もともとある血管から新しく血管をつくりだす現象である。我々の体が作られる時のみでなく、その後の修復過程や様々な病気の発症や進行時に見られる極めて重要な現象であり、その全貌を十分に理解する必要がある。今回の研究では、血管内腔を流れる血液(血流)により生じる内腔圧が血管新生を抑制するメカニズムを明らかにした。また、血管をとりまく細胞ペリサイトが血管内腔圧の作用を調節することで血管新生を制御する新しい血管新生メカニズムが示唆された。本研究は、血管新生の理解に貢献すると共に、血管新生を標的とする新たな治療法創生に資する。
PKGのTOR複合体調節機構と細胞内局在化機構を標的とした新たな心不全治療戦略
中村 太志(熊本大学医学部附属病院 循環器内科・准教授)
サイクリックGMP依存性プロテインキナーゼ(PKG)の活性は、サイクリックGMPの結合により惹起される従来の調節機構以外に、酸化還元(レドックス)によるサイクリックGMP非依存性の調節機構がわかり、心血管における意義が注目されている。本研究は、細胞の成長や増殖、生存を調節する哺乳類ラパマイシン標的蛋白質(mTOR)のシグナルを抑制するチュベリン(TSC2)上に、新規のPKGリン酸化部位を見出し、病的心肥大における同部位のリン酸化の意義を明確にすることを目的にした先駆的な研究です。本研究成果を契機に、心不全治療における新たな分子標的戦略の発展が期待されます。
ウイルスが宿主自然免疫応答を抑制する新規メカニズムの解明
押海 裕之(熊本大学大学院生命科学研究部免疫学分野・教授)
自然免疫応答は、ウイルス感染初期の生体防御に必須の役割を果たす。しかし、多くのウイルスはこの自然免疫応答を抑制する能力を進化の過程で獲得しているため、ヒトに感染し病気を引き起こす。B型肝炎ウイルスは、ヒトの肝がんの主要な原因の一つである。本研究では、B型肝炎ウイルスが細胞外小胞を利用して自然免疫応答を抑制するメカニズムを解明することで、B型肝炎ウイルスが持続感染するメカニズムの一端を解明した。今後、この過程を阻害するような、新たなB型肝炎治療薬開発につながると期待される。
大腸がんの時空間的進展にかかわる制御性T細胞関連のエクソゾーム内包microRNA
三森 功士(九州大学病院別府病院 外科・教授)
近年、癌に対する免疫応答が注目されるようになり、悪性黒色腫等では、抗PD-1抗体であるニボルマブが臨床応用されています。しかし、適応は一部の癌腫に限定されており、大腸癌では臨床試験の段階です。免疫応答機構の存在に関わらず、大腸癌の克服に至っていないのは、大腸癌の局所での免疫応答が正常に機能していないことが示唆せれ、大腸癌における免疫応答と腫瘍細胞の反応機序の解明は重要な課題です。
そこで、我々は、がん抗原に対する免疫応答を制御する制御性T細胞に注目し、研究を進めています。さらに、免疫機構で、重要な役割を担う遺伝子・タンパク群の中で、情報伝達分子の役割を担うmicroRNAに注目し、制御性T細胞とmicroRNAの関連性を解明しようと考えています。sTn糖鎖抗原による低酸素環境下でのがん細胞の生存戦略の解明
大坪 和明(熊本大学・教授)
がんが転移する過程においてがん細胞は酸化ストレスに曝されるため死滅します。しかし、この酸化ストレスへの耐性を獲得した一部のがん細胞は生存し転移を果たします。これまで、この酸化ストレスへの耐性獲得のメカニズムは殆ど明らかになっていませんでした。私たちはがん細胞が作り出すシアリルTn糖鎖抗原ががんの浸潤能を活性化するとともに抗酸化酵素の産生を誘導することで、がん細胞の生存と転移を直接促進することを明らかにしました。この発見はがん細胞の転移の仕組みを明らかにするのみならず、新しい抗がん剤の開発にとって重要な知見であります。
成果報告によせて - 2015年度受賞者から
-
(受付順、敬称略)
がん抑制遺伝子と低酸素応答遺伝子ネットワークの機能的・作用機序的クロストーク
原田 浩(京都大学大学院医学研究科・特定准教授)
がんには個性があり、治療が効きやすいタイプや効きにくいタイプ、転移をし易いタイプやしにくいタイプなど、患者さんによって患っているがんのタイプは様々です。私達は、がんの悪性度と治療抵抗性を左右する原因遺伝子の一つとして、LY6Eを発見しました。そしてLY6E蛋白質を豊富に含むがんは増殖が極めて速く、治療がなかなか効きにくいこと、そして結果的に患者さんの生存期間が短くなってしまうことを確認しました。この研究結果を基に、LY6Eを標的とする新たな治療法の開発に向け、研究を続けています。
結核菌の病原性脂質を認識する自然免疫受容体を介した宿主免疫の制御機構
原 博満(鹿児島大学大学院医歯学総合研究科・教授)
結核は世界人口の1/3が罹患する世界最大の細菌感染症であり、年間200万人を超える人が命を失い続けています。しかし、結核を薬で完治させることは難しく、効果的なワクチンも未だに存在しません。結核を克服するためには、宿主免疫による結核菌の認識と応答の仕組みと、結核菌が免疫を回避する仕組みの両方を分子レベルで理解する必要があリます。我々の研究によって結核菌の病原性脂質による免疫抑制の分子機構が明らかになれば、新しい概念での結核の予防薬や治療薬の開発に繋がるものと期待しています。
自然免疫をダイナミックに制御する糖鎖修飾の研究
後藤 聡(立教大学理学部・教授)
免疫は私達の身体を守るのに重要な役割を果たしています。その免疫は、感染していないときには働かないように抑えられていなければなりません。一方、いったん病原体などが感染したときには免疫は十分に活性化されなければなりません。本研究では、その免疫の動的な制御に糖鎖が重要な役割を果たしていることを見出しました。非感染時には糖鎖が免疫の活性化を抑え、感染時には糖鎖が減少することで免疫を十分に活性化させていました。将来的には、糖鎖を使った免疫の活性化を制御する技術が期待されます。
神経回路形成因子LOTUSの発現制御による多発性硬化症の治療法開発
竹居 光太郎(横浜市立大学大学院生命医科学研究科・教授)
国の難病に指定されている多発性硬化症に見られる神経変性はNogo受容体という分子が関与していると報告されているため、私達が発見したNogo受容体の働きを阻止するLOTUSという分子とこの病気との関連について病態モデルマウスを用いて調べたところ、予想に反して、LOTUSは血中のリンパ球と結合して炎症を引き起こすサイトカインの一種をリンパ球から分泌させて炎症を引き起こす可能性が示されました。即ち、LOTUSはこの病気の発症に関連することが示唆されました。LOTUSが引き起こす炎症を止めることでこの病気の発症や進行を抑制することができるのではないかと考え、その方策を明らかにするための研究を行っています。
骨髄線維症幹細胞におけるエピジェネティック制御異常の分子基盤
指田 吾郎(熊本大学国際先端医学研究機構・特別招聘准教授)
原発性骨髄線維症とは骨髄の中で血小板を作る巨核球と顆粒球系細胞が腫瘍性に増殖して骨髄の線維化と造血障害に加えて、脾臓などで異所性造血を生じる予後不良ながんである。病気の原因として、遺伝子変異があり、約半数の患者でJAK2キナーゼの活性化変異があり、その他に共存する遺伝子変異としてエピゲノム制御因子であるEZH2やTET2が知られ、悪性度との関連が言われている。骨髄線維症マウスの造血幹細胞を採取して、患者の腫瘍細胞でも発現上昇が知られるHmga2を骨髄線維症の病態進展に責任のあるがん遺伝子として同定した。 今後、新規に作製したHmga2発現を造血幹細胞で特異的に誘導できるマウスを用いて、詳細な骨髄線維症の発症メカニズムを解明するとともに、標的遺伝子の検索を通した新規治療戦略の進展が期待できる。
リボソームRNAプロセシング異常という白血病発症の新しい概念の提示と検証
松井 啓隆(熊本大学大学院生命科学研究部 臨床病態解析学分野・教授)
近年の遺伝子解析研究の飛躍的な進歩により、白血病や骨髄異形成症候群といった血液腫瘍の原因となる遺伝子異常は、ほぼ全て明らかにされたといえます。一方で、こうした遺伝子異常が実際にどのように血液細胞を腫瘍細胞へと変貌させるのか、という根源的な疑問は、遺伝子解析だけで解くことができないものであり、地道な分子生物学的研究を必要とします。こうしたなか私たちは、最近血液腫瘍の原因となることがわかったDDX41という遺伝子の変異に着目し、この変異により作られる異常なDDX41が、リボソームと呼ばれる細胞内のタンパク質精製工場の機能を障害することを、多面的な解析手法により示してきました。今後さらに詳細なメカニズムを解明すべく、研究を続けていきたいと考えています。
ヒトにおける樹状細胞による抗原特異的制御性T細胞の誘導の研究
山崎 小百合(名古屋市立大学医学研究科・教授)
様々な免疫反応を抑制する制御性T細胞の抗原特異性を樹状細胞という特別な抗原提示細胞でコントロールする研究をこれまでマウスで行ってきた。抗原特異的な制御性T細胞を誘導する事ができれば、癌や感染症に対する免疫反応を抑制せずに、自己免疫疾患、アレルギー、移植片拒絶を治療する事が可能となる。本研究では、これをヒトの細胞に応用することを行った。ヒトの樹状細胞でも抗原特異的に制御性T細胞を誘導できる条件決定を行うことができた。
慢性ストレス・慢性疼痛による抑うつ・不安に関わる神経機構の解明
南 雅文(北海道大学大学院薬学研究院・教授)
ヒトを含む哺乳類は、身を守るための生体防御システムとして、抑うつや不安などの負情動生成機構を獲得・進化させてきたと考えられます。したがって、うつ病や不安障害のメカニズムを理解するためには、生体防御システムとしての負情動生成機構を明らかにした上で、患者や病態モデル動物における変化を解析することが必要となります。私たちは、分界条床核と呼ばれる脳部位に着目して研究を進め、分界条床核から扁桃体中心核に投射する神経細胞の活性化が不安情動を引き起こすことを明らかにした。また、慢性痛時に分界条床核内シナプス伝達の可塑的変化が起こることも見いだしています。これらの神経機構がうつ病や不安障害に関与している可能性があります。
遺伝子改変iPS細胞を用いたRBM20変異による心筋症発症機序の解明
宮岡 佑一郎(東京都医学総合研究所 生体分子先端研究分野 幹細胞プロジェクト・協力研究員)
拡張型心筋症は、心臓移植の最多の要因である。近年、RBM20という遺伝子の変異が拡張型心筋症の原因であることが明らかとなったが、ラットなどのモデル生物を用いた研究では、心筋症発症機序の理解が十分ではなかった。そこで、私達はヒトiPS細胞にRBM20の変異を導入し、心筋細胞へと分化させ、詳細に解析することにより、これまでに知られていなかったRBM20の変異が心筋症発症につながる分子機構を解明した。本研究の成果が、新たな治療法の開発につながることが期待される。
スギヒラタケ食中毒事件の化学的解明
鈴木 智大(宇都宮大学 バイオサイエンス教育研究センター・准教授)
スギヒラタケは東北、北陸、中部地方を中心に広く食用とされてきたキノコですが、2004年以降、スギヒラタケの摂食者が急性脳症を発病しました。本課題を遂行することによって、このキノコの毒性に関与する可能性がある毒性物質数種の構造決定を行う事ができました。この酵素は新たな酵素学として科学的価値だけでなく、様々な応用の可能性を秘めており、新たな酵素の創出も期待できます。さらにスギヒラタケ摂取患者に見られる病変は、既存の病気のものとは異なる未知の発生機序を強く示唆しています。今後も毒性メカニズムの解明のために、研究を継続する予定です。
1細胞を対象としたゲノムワイドDNA複製解析の開発によるDNAポリメラーゼ挙動の解明
大学 保一(東北大学 学際科学フロンティア研究所・助教)
個々の細胞には個性があります.遺伝情報であるゲノムを複製するシステムはすべての細胞において,全く同じパターンで起きるわけではありません.複製が開始される場所,細胞に多種存在するDNAを合成する酵素:DNAポリメラーゼの使われ方が異なっています.本研究では,1つ1つの細胞で,ゲノムDNA全体に渡り,個々のDNAポリメラーゼ分子の役割を明らかにする実験系の構築を行いました。
成熟心筋細胞の細胞周期と分裂能を調整する新規lincRNA(Linc-Heart)の同定と昨日解析
片岡 雅晴(慶應義塾大学医学部・特任講師)
本研究では成熟心筋細胞の細胞周期を調整する新規のlincRNAを同定し、linc-Heartと命名した。今後、linc-Heartが成熟心筋細胞の細胞周期を調整する詳細なメカニズムを解明し、心筋細胞周期の再活性化による病的心臓治療への応用の可能性を広げたいと考える。 本研究成果を応用することによって、これまでの試みから逸脱した全く新しい概念として、もともと存在している正常な成熟心筋細胞を細胞増殖させることにより治療する、という発想が可能な時代が到来する可能性がある。ヒト心筋梗塞後のリモデリング抑制や心筋症での心機能改善等へ応用できる可能性が広がり、臨床への将来的な貢献が多いに期待できる。
正の選択を介したT細胞の機能的教育が生体内免疫応答に果たす役割
高田 健介(徳島大学疾患プロテオゲノム研究センター・准教授)
リンパ球のひとつであるT細胞は、病原体や癌細胞に対する防御に不可欠な役割を果たしています。T細胞は胸腺という器官で非常に複雑な過程を経て作られます。私たちは、胸腺に存在する特殊な酵素の解析を通し、胸腺での分化の過程が、成熟した後のT細胞の機能を決定づけることを明らかにしてきました。今回、ワクチンの基本原理としても重要な免疫記憶というT細胞の機能に、胸腺での分化過程が関わっている可能性を見出しました。機能的に優れたT細胞が作り出される仕組みを理解することは、免疫の異常が関係する様々な病気の予防や治療、優れたワクチンの開発に役立つと期待されます。
L型カルシウムチャネルの正常な細胞内局在・機能維持におけるジャンクトフィリンの役割
中田 勉(信州大学医学部・講師)
骨格筋が正常に収縮するためには,L型カルシウムチャネルが結合膜構造と呼ばれる部位に集積することが必要不可欠である。しかし,その集積の詳細な分子メカニズムは明らかになっていない。本研究では,結合膜構造に存在するジャンクトフィリンと呼ばれる分子が,L型カルシウムチャネルに結合し,正常な結合膜への局在化や機能を調節していることを見いだした。今回得られた結果は,骨格筋の収縮メカニズムを解明する上で,重要な知見のひとつであると考えられる。
エピジェネティック修飾による初期化プログラムとキメラ形成分子機構の解明
岡村 大治(近畿大学農学部・講師)
我々はこの研究を通じて、小分子化合物 L-Ascorbic Acid (ビタミンC)の添加により、将来精子や卵子の元となる”マウス始原生殖細胞(PGCs: primordial germ cells)”から、新規多能性幹細胞が樹立することを見出しました (vcPGC細胞)。ビタミンCは、DAN脱メチル化に機能するTetファミリーと協調的に機能することが広く知られており、マウス始原生殖細胞はDNA脱メチル化によるエピジェネティック修飾の変化により、新規多能性幹細胞として再プログラム化されていると考えられます。本研究の成果は、細胞の初期化プロセスにおけるエピジェネティック修飾の役割を解明する、非常に有用なモデルとなることが期待されます。
ヒトiPS細胞を用いた2型糖尿病感受性遺伝子による糖尿病発症機序の解明
淺原 俊一郎(神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学・医学研究員)
日本人2型糖尿病患者では、膵β細胞の脆弱性が問題であることが明らかになっており、その原因の一つとしてKCNQ1遺伝子の変異が注目されています。我々は、Kcnq1変異マウスではKcnq1ot1という分子の量が減ることによって膵β細胞量が減少することを報告しましたが、ヒトでも同様のことが起こっているかは不明です。そこでヒトiPS細胞を膵β細胞に分化させ、マウスの実験結果と比較することにしました。今回の研究では膵内分泌細胞への分化を達成しましたが、膵β細胞への分化誘導には至りませんでした。今後はプロトコールを改良し、さらに実験を進めていく予定です。
NIMA関連キナーゼによる植物細胞の伸長成長制御機構の解明
本瀬 宏康(岡山大学・自然科学研究科 理学部・生物学科・准教授)
植物は分裂組織から根や葉・花などの様々な器官を形成します。このプロセスでは、個々の細胞がどの方向にどれくらい成長するかが重要になります。植物細胞の成長方向は、細胞内の骨格である微小管が一定の方向に並ぶことで規定されます。しかし、微小管がどのようなしくみで一定の方向にきれいに並ぶのかわかっていません。私たちは、NEKというチューブリンタンパク質をリン酸化する酵素が、余分な微小管を除去して整理整頓することで、微小管がきれいに並び、細胞の成長方向が決定されることを見いだしました。このしくみは陸上植物の進化の初期に獲得されたと考えられます。
細胞ストレス応答反応の解析から挑む「過食」の分子メカニズム
岩脇 隆夫(群馬大学大学院医学系研究科・講師)
満腹時および空腹時における摂食行動の制御機構は詳細なところまで明確になっている。しかしながらストレスが引き起こすとされる過食や拒食のメカニズムは殆ど分かっていない。私たちはマウスを用いた実験で次の意外なことに気が付いた。細胞の健康状態を悪化させるストレスを与えると過食行動が引き起こされるのである。この現象は「やけ食い」のような心的ストレス性の摂食異常を分子レベルで解明する糸口になるかもしれない。本研究を通じて私たちはストレス応答反応が果たしているであろう摂食行動制御に関する新たな役割を理解しつつある。
神経軸索再生誘導に必要な小胞体経由シグナルの解析
久本 直毅(名古屋大学大学院理学研究科・准教授)
神経細胞は、軸索という長い突起を介して電気信号を伝達しており、外傷などで軸索が切断されると神経として機能できなくなります。しかし、多くの神経は軸索を再生する能力を潜在的に持っています。今回、モデル動物である線虫C.エレガンスを用いた解析により、コラーゲンがDDRと呼ばれるコラーゲン受容体を介して切断された軸索再生を促進することを新たに発見し、その分子メカニズムを解明しました。本成果で得られた基礎的知見は、神経再生促進技術の改善・改良の手助けになることが期待されます。
細胞膜を貫通するDNAナノ構造体による分子デリバリーシステムの開発
遠藤 政幸(京都大学 物質-細胞統合システム拠点・特定拠点准教授)
本研究では、DNAナノ構造体の構築技術を利用し、ターゲット分子を細胞内に送り込む分子輸送システムを開発する。DNA鎖からなる分子針を持つDNAオリガミ構造体を用いて、脂質二重膜との相互作用を高速原子間力顕微鏡(AFM)によって観察した。次に、生化学反応系を導入したリポソーム(脂質膜)に、DNA構造体を結合し、ターゲット分子が脂質膜を貫通し、リポソーム内の生化学反応を開始できることを見出した。これら構築した技術を使って、細胞膜を貫通し、細胞内に分子を送り込む新たな分子システムの構築を検討する。最終的に細胞死の誘導、遺伝子発現の抑制、免疫増強など細胞機能制御や細胞応答を見る。
生物活性架橋多環式メロテルペノイドの全合成研究
中村 精一(名古屋市立大学大学院薬学研究科・教授)
バークレーオン類は、米国の銅鉱山跡にできた湖で採取された菌から見つけられた化合物群ですが、バークレージオンが抗がん作用を示すことで知られているなど、創薬のリード化合物として注目を集めています。本研究では、菌がこれらの化合物を作り出す方法を模倣することで、これらの化合物群を化学合成することに挑戦しました。本研究は、当該天然物はもちろんのこと、類縁構造を持つ化合物群の供給に道を拓くものであり、将来的な医薬品開発につながることが期待されます。
大脳皮質局所神経回路のシャンデリア細胞の機能的役割
窪田 芳之(自然科学研究機構生理学研究所・准教授)
大脳皮質は多くの領域から構成され,それぞれが機能分担をすることで知覚,運動,思考といった我々の知的活動を支えています。大脳皮質の局所神経回路は、多種類の神経細胞と他の領域からの入力線維から構成されており、非常に複雑な情報処理をしていると考えられています。この仕組みを知るためには、皮質内神経回路の構造と機能を明らかにする必要があります。本研究では、シャンデリア細胞やバスケット細胞と呼ばれている大脳皮質の抑制性神経細胞の機能的役割に焦点をあて、この局所神経回路の機能構造を解析しました。これらの神経細胞は、ターゲットの錐体細胞の活動に強力な抑制効果をもたらしているという結果を得ました。
ヒト末梢血と腫瘍組織中濾胞性制御性T細胞の特徴
ウィング ジェイムズ(大阪大学免疫学フロンティア研究センター実験免疫学・特任助教)
制御性T細胞(Treg)は、免疫恒常性を維持する上で重要な役割を果たしている。 TregのサブセットであるTfrは、抗体反応を制御することに特化しているが、特にヒトにおいてはよく理解されていない。 本研究では、ヒト血液中のTfrの詳細な特徴を明らかにした。この成果は、SLEおよび関節炎などの自己免疫疾患における役割を理解する上で重要である。 さらに、以前はナイーブなTregであると考えられていた細胞の大多数が、実際には新しいメモリーTreg集団である可能性があることを示し、これらの細胞の免疫学的役割およびその制御の理解と応用に重要である。
癌の浸潤・転移で認められる細胞形態・運動のモード変換を1分子構造変化から解明する
坂根 亜由子(徳島大学大学院医歯薬学研究部医科学部門生理系生化学分野・助教)
最近、癌細胞が転移・浸潤していく上で、細胞の形態および運動能の変換が重要な役割を担っていることが明らかになりつつある。したがって、癌の転移・浸潤過程で認められる細胞形態・運動能の変換の分子機構を理解し、その変換を自由に調節することが可能となれば、癌の転移・浸潤に対する新たな治療法の開発や創薬にもつながることが期待される。これまで本分子機構には多くの分子が関与し、それらの分子間相互作用が複雑に絡み合って成立すると考えられていたが、本研究ではJRABというたった1分子の構造変化に依存したアクチン細胞骨格の再編成が細胞の形態・機能の変換を時空間的に制御しているという独創的な成果が得られた。
ミトコンドリアに作用する新規アポトーシス阻害剤の開発
松本 健司(徳島文理大学薬学部・講師)
アポトーシスは、生理的な細胞死とも呼ばれ、癌、エイズ、アルツハイマー病など多くの疾病に関わっており、アポトーシス阻害剤はこれら難治性疾患の治療薬として期待されています。ボンクレキン酸(BKA)は、ミトコンドリアに作用するアポトーシス阻害剤として知られていますが、非常に高価で大量入手が難しいために詳細な作用機序は未だ十分には解明されていません。本研究では、我々の開発したボンクレキン酸の全合成を足掛かりに、大量供給法の確立および高活性な新規アポトーシス阻害剤の創製を目指しています。
慢性疼痛と不安神経症が共存する大脳神経可塑性の機序解明
古賀 浩平(弘前大学大学院医学研究科・助教)
慢性疼痛は侵害受容と心因性の要因からなり、前帯状回はこれら2つの要因に関わる重要な大脳皮質である。本研究では、前帯状回の抑制性シナプス伝達の可塑性に着目し、慢性疼痛が形成する大脳皮質の局所神経回路を理解することを目的に研究を行った。その結果、慢性疼痛モデルは前帯状回の抑制性シナプス伝達に可塑的な変化を示すことが明らかとなった。特に、GABAの放出が抑制される仕組みとして、GABAをシナプス小胞に貯蔵するトランスポーターである小胞GABAトランスポーターのタンパク質の発現量が関与する可能性が示された。
新規胃癌腹膜播種責任分子synaptotagmin13 の発現および機能解析
神田 光郎(名古屋大学医学部附属病院 消化器外科二・助教)
57751分子の網羅的遺伝子発現解析から、進行胃癌の転移再発形式の中で最も高頻度かつ難治性である腹膜播種に特異的発現するsynaptotagmin 13を発見しました。synaptotagmin 13を阻害することで、胃癌細胞の活動性を低下させ、腹膜播種形成を抑制できることが明らかになりました。 synaptotagmin 13は、すでに腹膜播種のある胃癌だけでなく、治癒切除術の後、腹膜播種を再発した胃癌でも高発現していることが分かりました。難治性の胃癌腹膜播種の新たな診断、治療への応用を目指しています。
網羅的エピゲノム解析を用いた機能的がん関連線維芽細胞の探索
下田 将之(慶應義塾大学医学部・専任講師)
がん組織は、がん細胞とそれを支える間質と呼ばれる成分から構成されています。がん間質に出現する活性化した線維芽細胞は「がん関連線維芽細胞(cancer-associated fibroblast:CAF)」と呼ばれ、新たな治療標的の一つとして注目されています。本研究では、網羅的解析手法および生物学的機能解析手法を用いてCAFの層別化を行うとともに、機能的なCAFの細胞特性を明らかにすることにより、CAFを標的とした新規診断法および治療法の開発を目指した基礎的データの取得を行っていきたいと考えています。
スプライシング異常による未成熟mRNAの蓄積を防ぐチェックポイント機構の解析
甲斐田 大輔(富山大学 先端ライフサイエンス拠点・准教授)
本研究は、ヒトをはじめとした真核生物のDNA上にある遺伝情報が、どのようにして正確に読み取られ、タンパク質へと翻訳されるかという、生物学的に非常に本質的な質問の答えを探すものです。本研究の結果から、スプライシングの異常時には異常なpre-mRNAの蓄積を防ぐため、転写伸長を止めてしまうという一種のチェック機構が働いていると考えられます。
細胞外基質の固さの認知によって惹起される神経堤細胞集団の流動化の研究
栗山 正(秋田大学大学院医学系研究科・准教授)
細胞は集団で移動する方がバラバラの細胞が動くよりもはるかに効率が良いことが分かっています。しかし、がん細胞が塊になっていると狭い所で詰まってしまうため生体内でがんが集団移動するとは信じられていませんでした。先の研究でがんに似た神経堤細胞が適度に流動性を持つ集団として移動している事が分かりました。つまり「がんは水の様に器に沿う」のです。次の疑問として器の形を認識して形を変えるのか、元から水の様なのかがありました。本研究助成から、神経堤細胞が器を触って「硬さ」を感じて形を変えていることが分かってきました。この制御方法が分かればがんを閉じ込めることができるようになるでしょう。
高等植物における新規サイレンシング機構の解明
三柴 啓一郎(大阪府立大学大学院生命環境科学研究科・准教授)
遺伝子組換え植物は食料問題や環境問題などの解決に貢献できるものとして、世界中で研究開発が進められています。しかし植物種によっては遺伝子導入が困難なことや、導入した遺伝子が期待通りに働かないことが問題になることがあります。私たちは、組換え植物で広く利用されている35Sプロモーターが、園芸植物であるリンドウでは発現抑制が起きることを見出しています。本研究では、この発現抑制を引き起こす配列を明らかにしました。この成果は、組換え植物の発現制御技術の発展に役立つものと考えています。
多細胞システムの起源に単細胞ホロゾアのゲノム編集で迫る
菅 裕(県立広島大学生命環境学部・准教授)
動物のからだはたくさんの細胞からできています。細胞同士は連絡を取り合いながら高度な分業体制をとっており、このことは動物が地球のエコシステム上で優位な地位を占めるに至る一因となったと考えられています。しかし一方で、人類が苦しめられている癌は細胞増殖の制御が狂うことが原因で起きており、多細胞生物にしかありえない病気といえます。我々の研究は、動物に最も近縁な単細胞生物「単細胞ホロゾア」と総称される生物を材料に、動物多細胞性の進化の秘密を探り、多細胞システムが本質的に抱える問題にも迫ろうとするものです。
樹状突起の形成と再生における微小管の配列制御のしくみを解明する
ムーア エイドリアン(理化学研究所脳科学総合研究センター・チームリーダー)
神経系が正しく機能するためには、神経細胞は神経樹状突起を介して適切な伝達経路からの入力を受け取る必要がある。よって、神経樹状突起の発達に異常が起こると知的障害および神経発達障害を引き起こす可能性がある。本研究では、神経樹状突起の発育時に起こる【2つの】未知かつ独立して存在する微小管核による中心体形成について明らかにした。我々は、神経系の中心体形成過程において重要な役割を果たすことが知られている微小管核形成は、異なる分子メカニズムを介して起こること示した。また、微小管核形成は神経樹状突起が成長、枝分かれするのを促すことで、神経損傷などが起こった際に神経樹状突起が再生するのに非常に重要な役割を果たすことを示唆した。
成熟脂肪?血管内皮細胞ネットワークによる脂肪組織恒常性維持メカニズムの解明
池田 宏二(神戸薬科大学 臨床薬学研究室・准教授)
肥満は世界的に増加を続けており、その健康被害は甚大です。肥満時には脂肪細胞が病的に肥大し、脂肪組織が機能不全に陥る結果、全身のエネルギー・糖代謝が障害されると考えられていますが、その詳細な分子機構は明らかではありません。脂肪組織は非常に発達した血管網を有しており、その血管密度は脂肪細胞機能と密接に関わっています。私たちは脂肪細胞と血管内皮細胞のコミュニケーションに注目し、Nrg4という分子を発見しました。Nrg4は脂肪細胞から分泌され、血管新生を誘導して脂肪組織の血管密度を高めます。肥満時にはNrg4の発現が減少することが明らかとなり、Nrg4の発現を増やすことで肥満時にも脂肪血管密度を維持し、脂肪組織の機能障害を予防できると考えられます。
単独miRNAが転写因子をレスキューする
幸谷 愛(東海大学総合医学研究所・准教授)
細胞の運命決定においては転写因子が重要な働きをするというのが従来の一般的な考え方でした。私たちは、その考えに沿わない、新しい現象を見出しました。その機序を本研究課題で解析し、細胞運命決定には転写因子のみならず、小分子RNAという因子も深く関与することを明らかにしました。